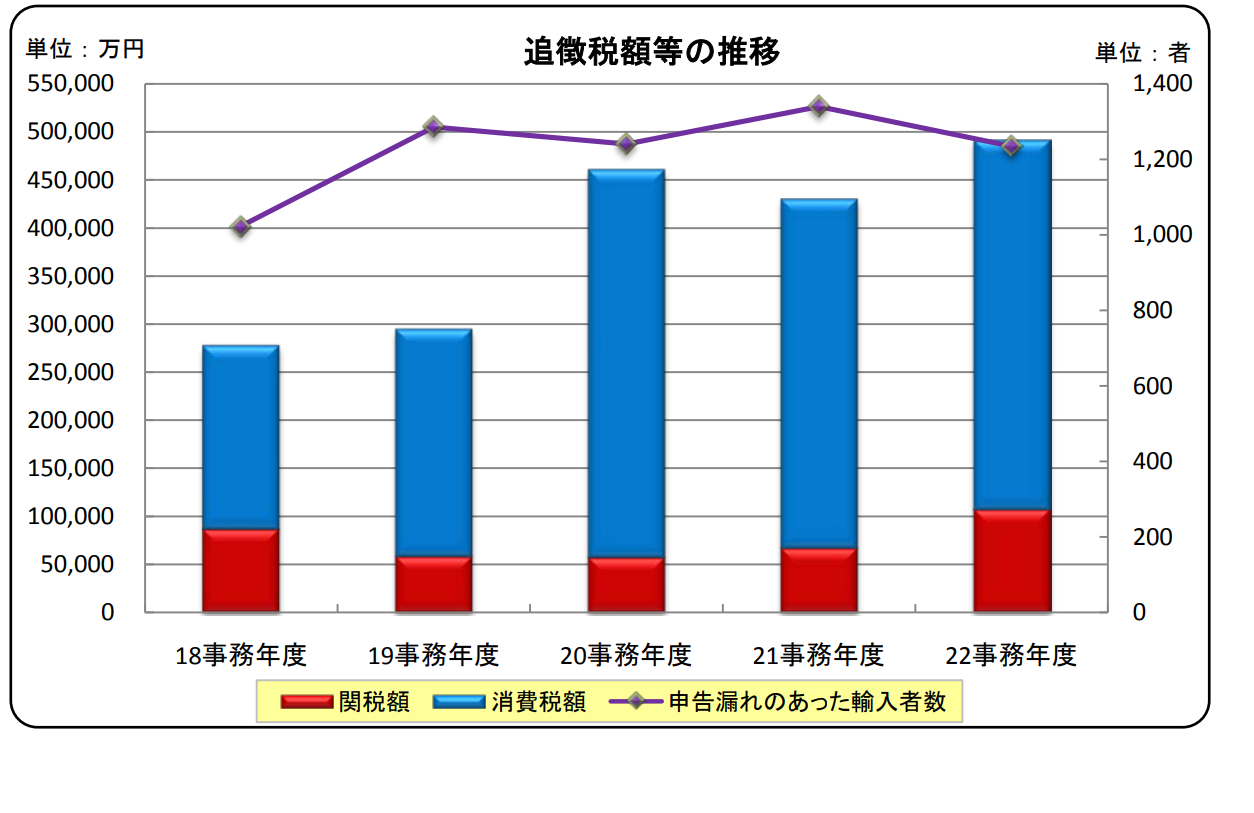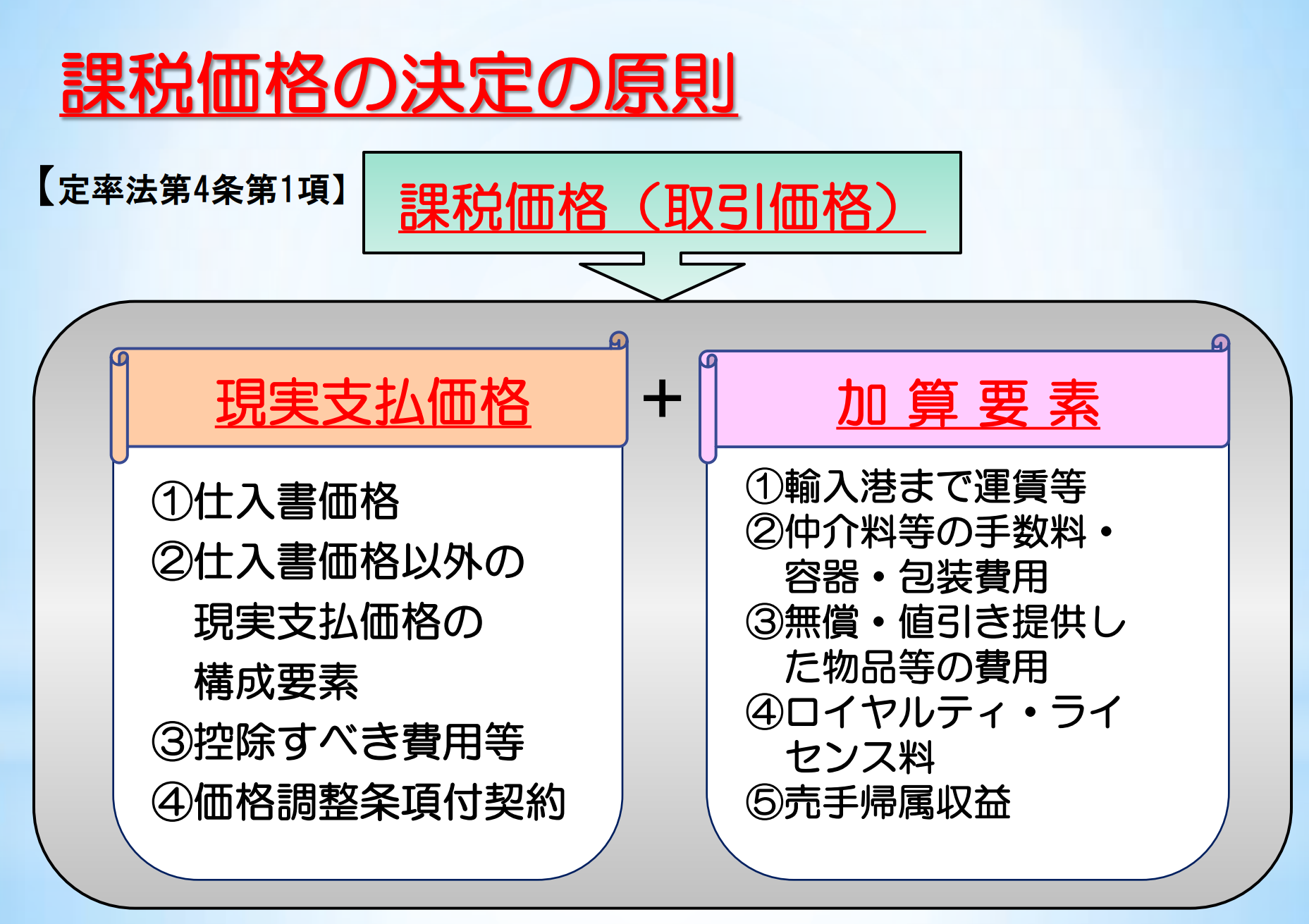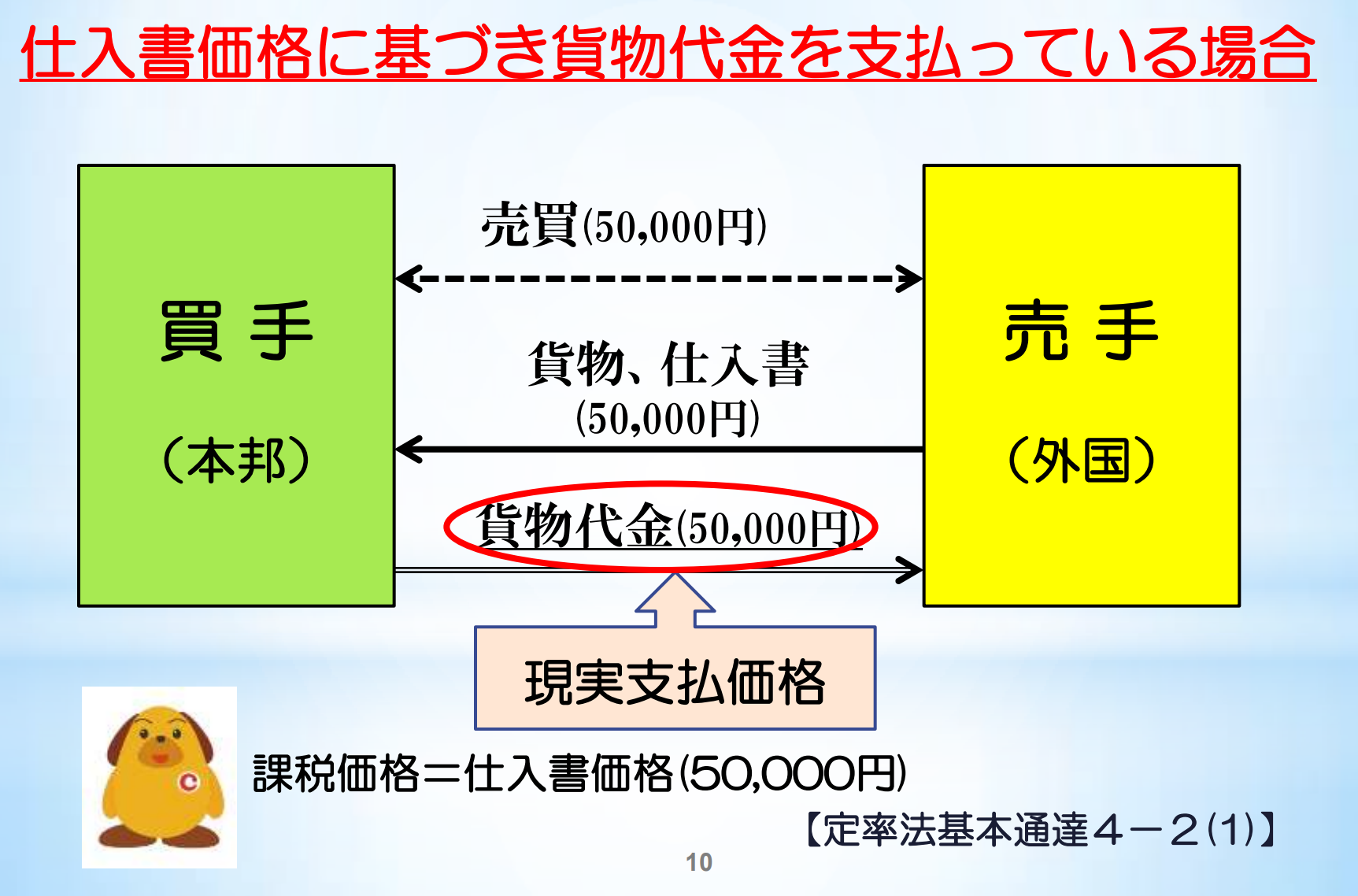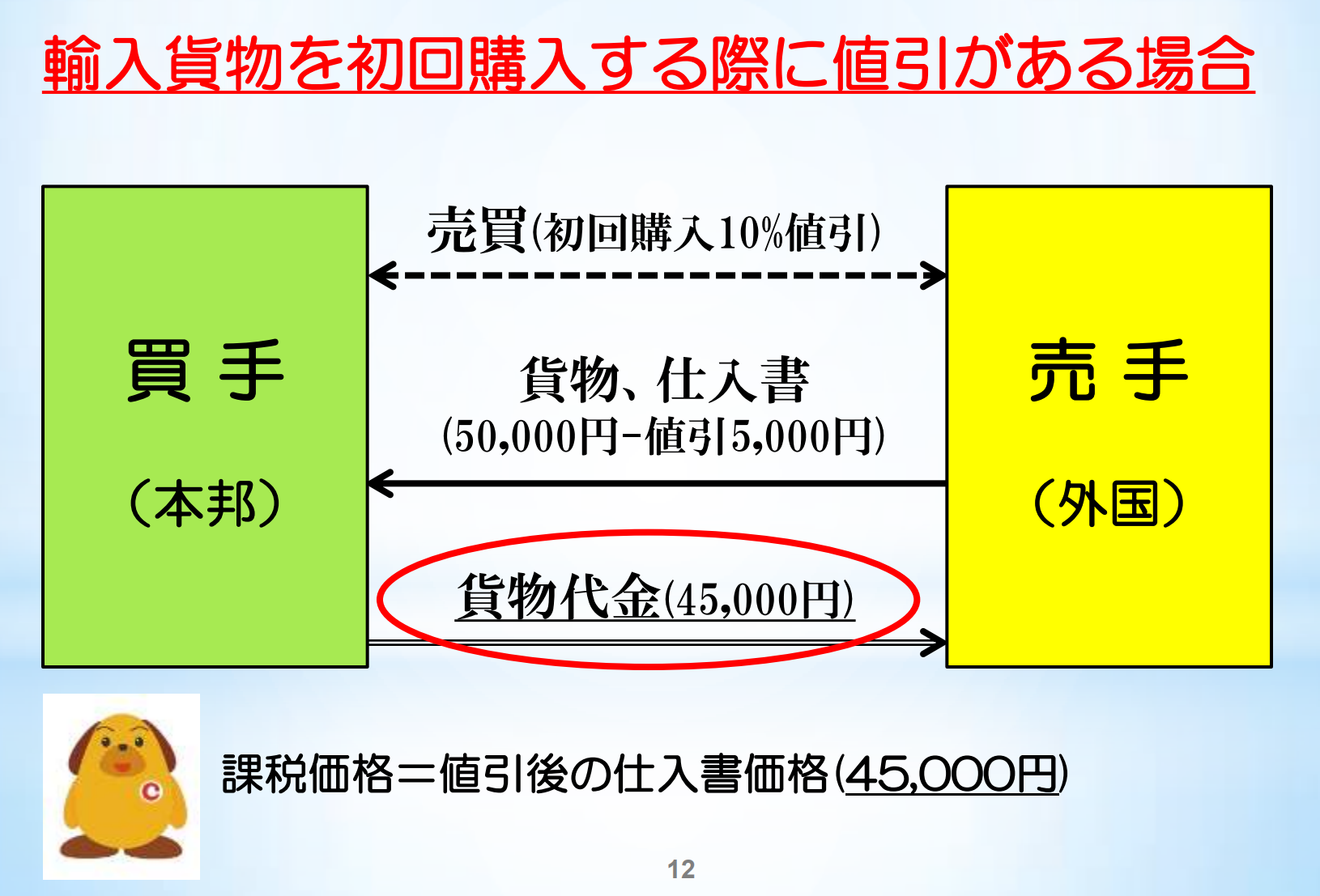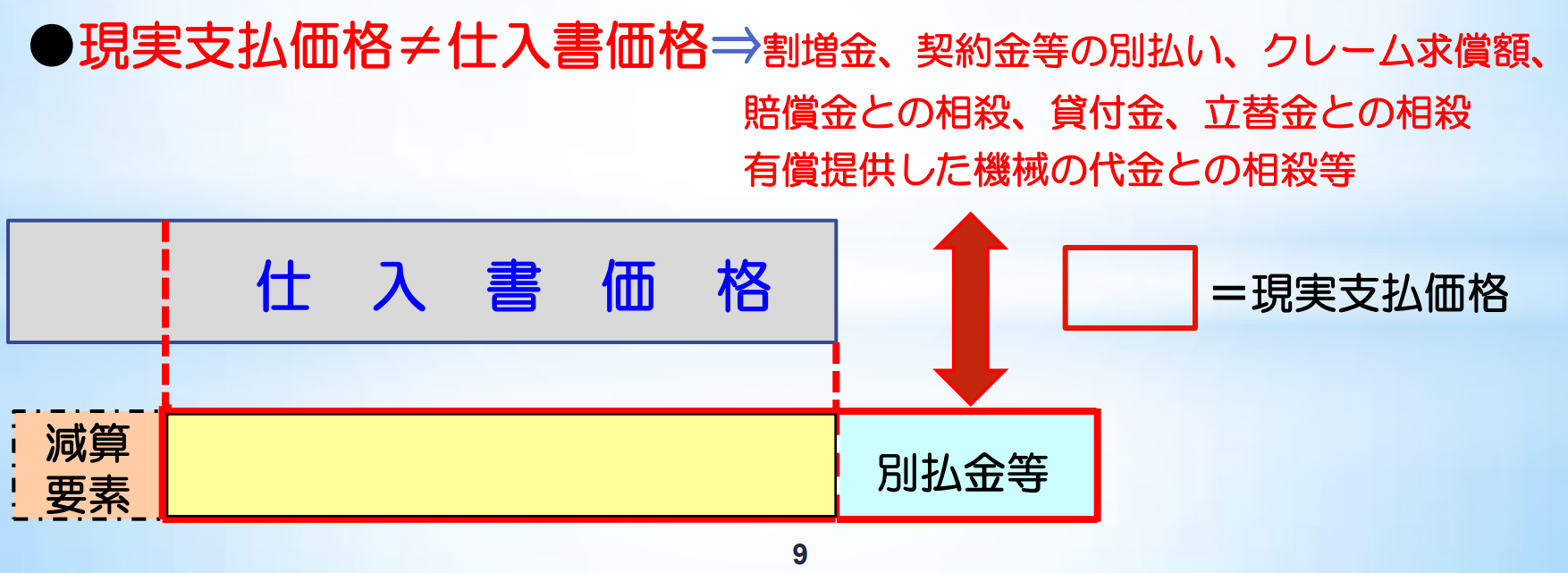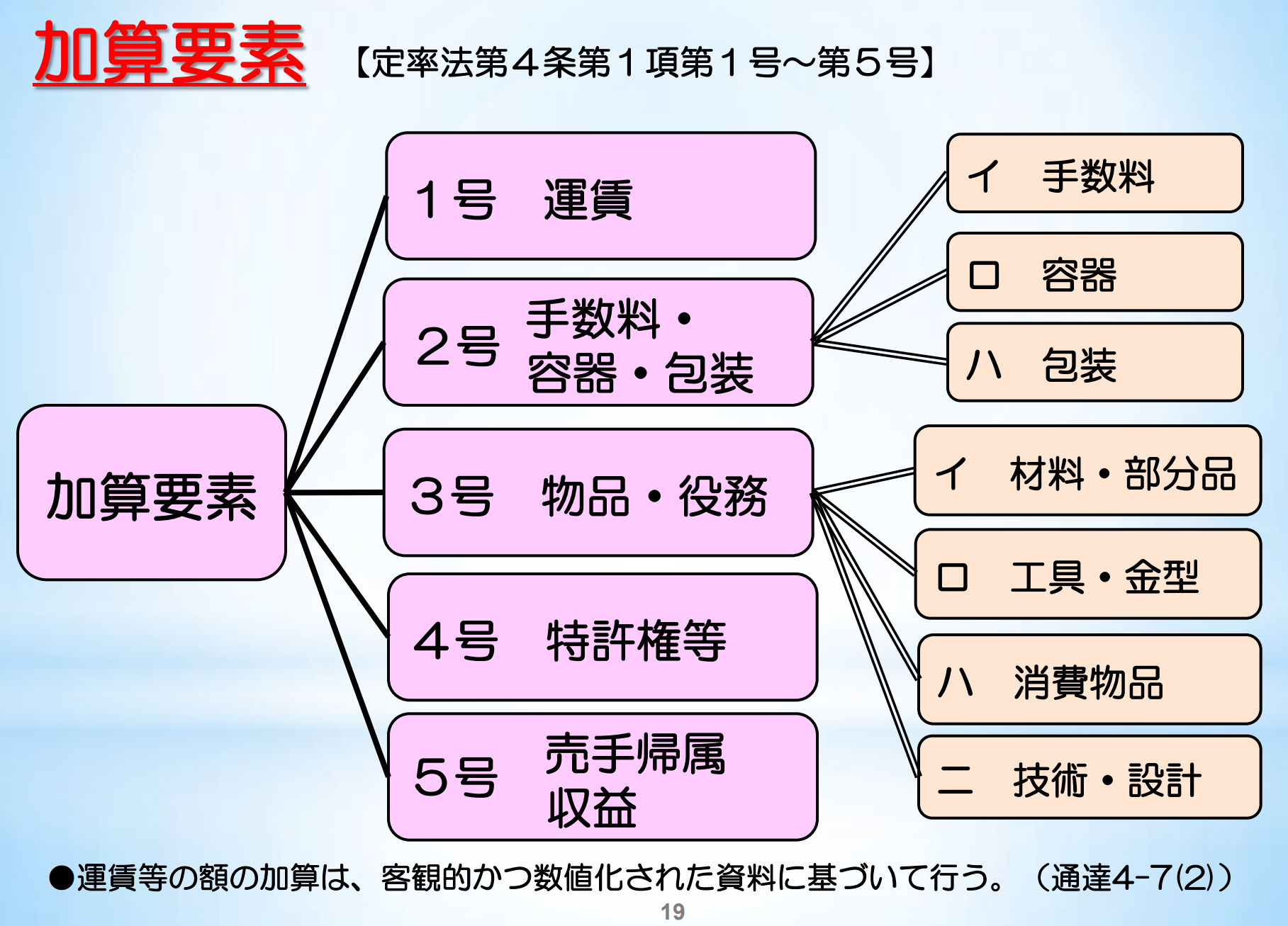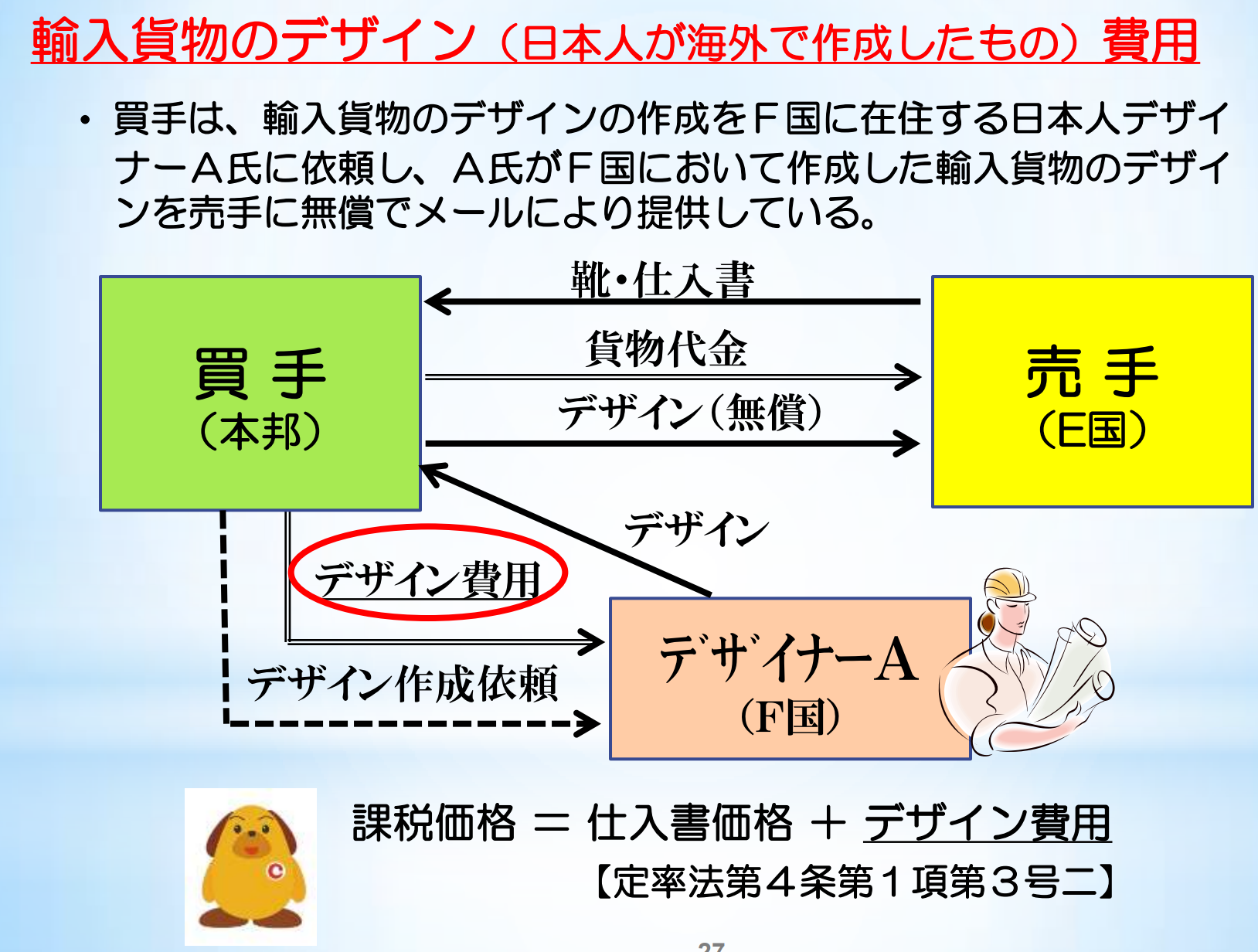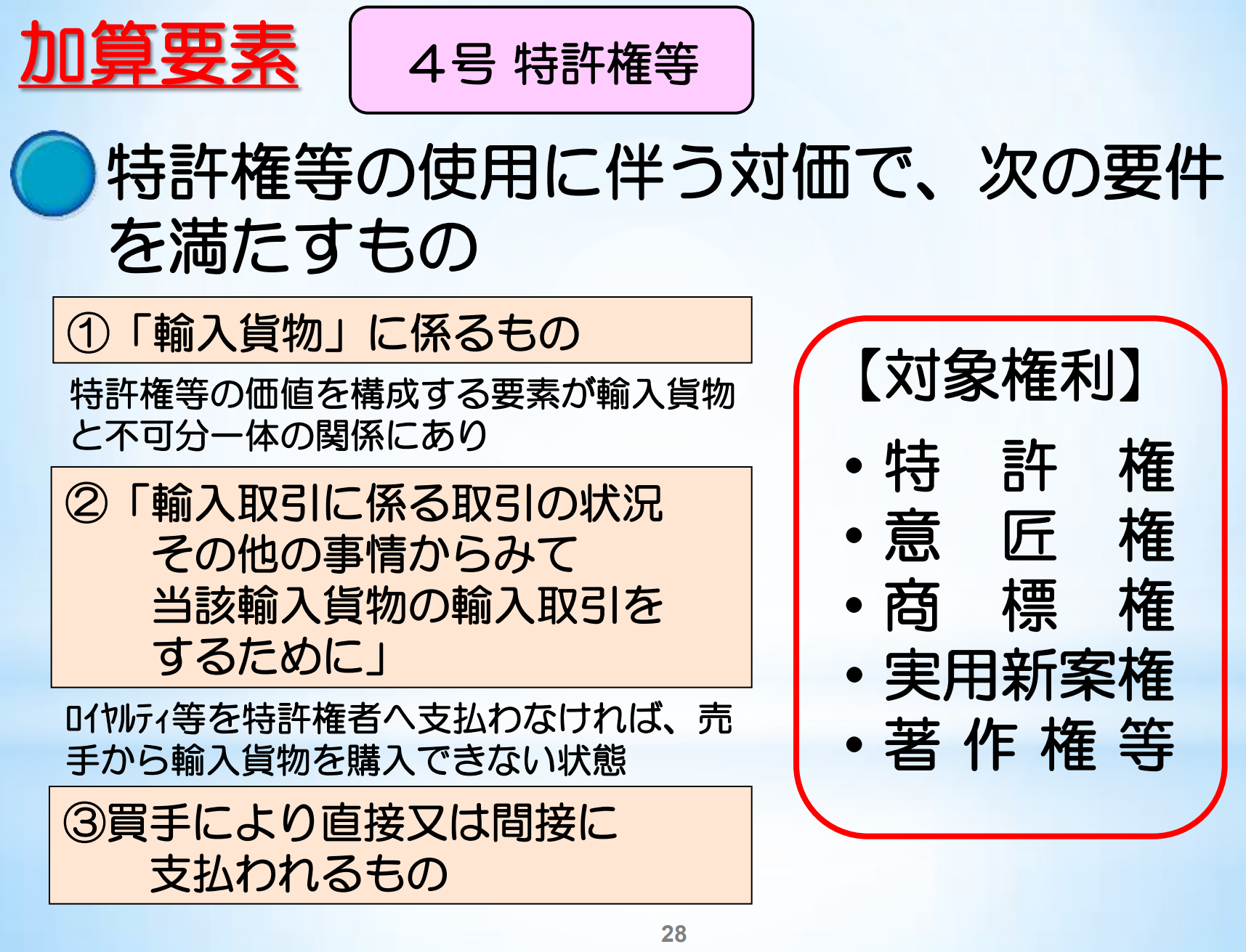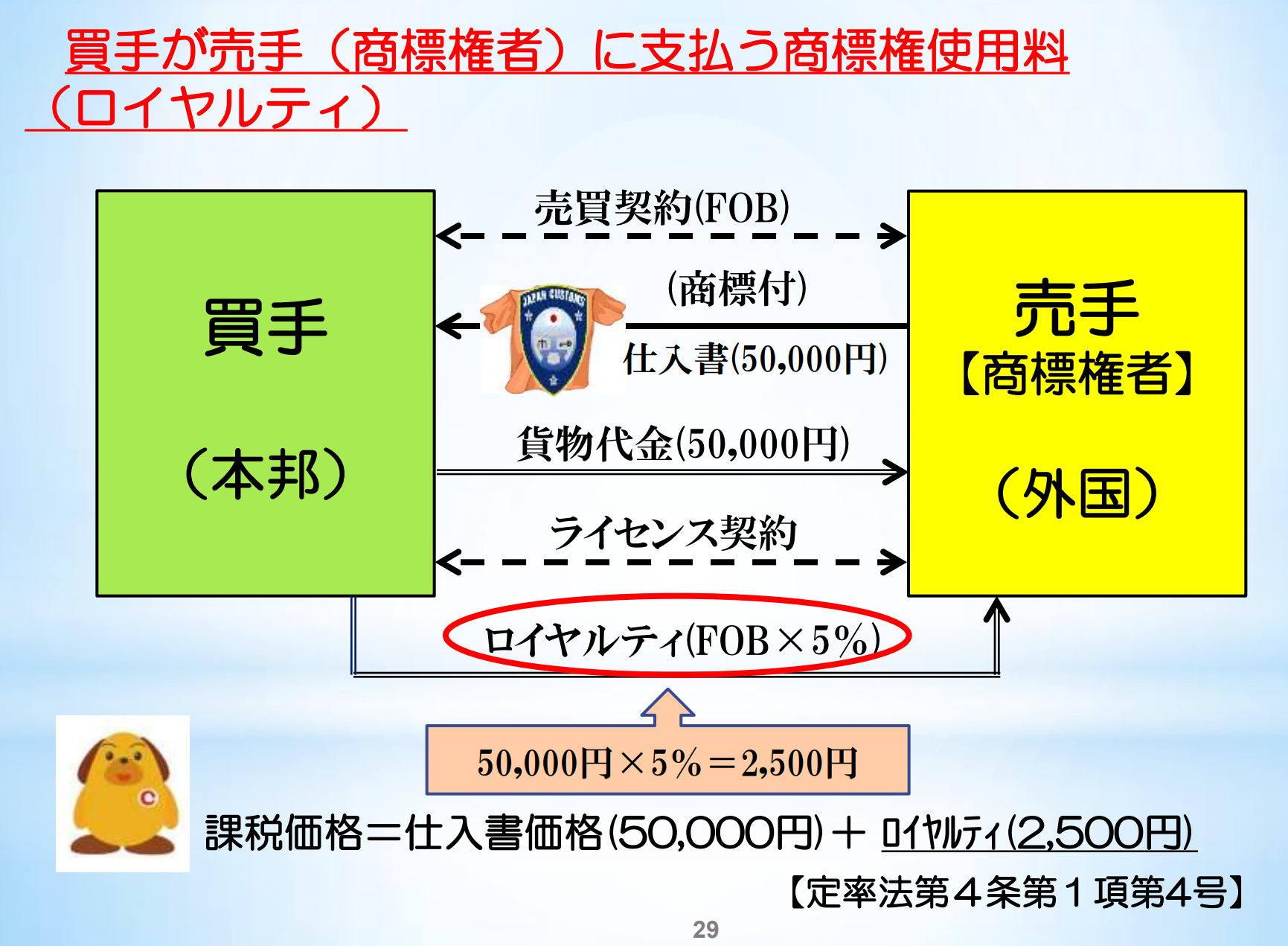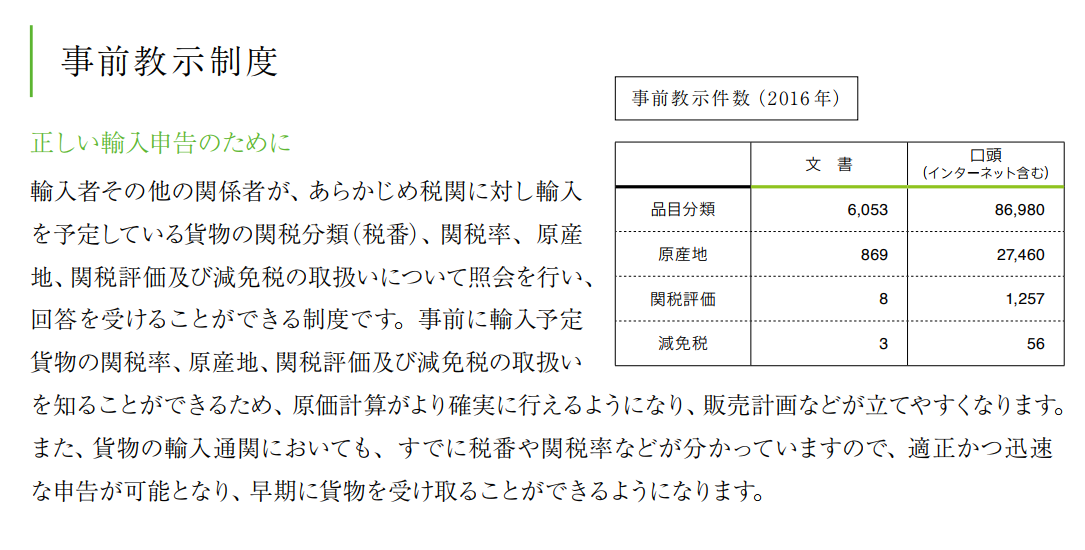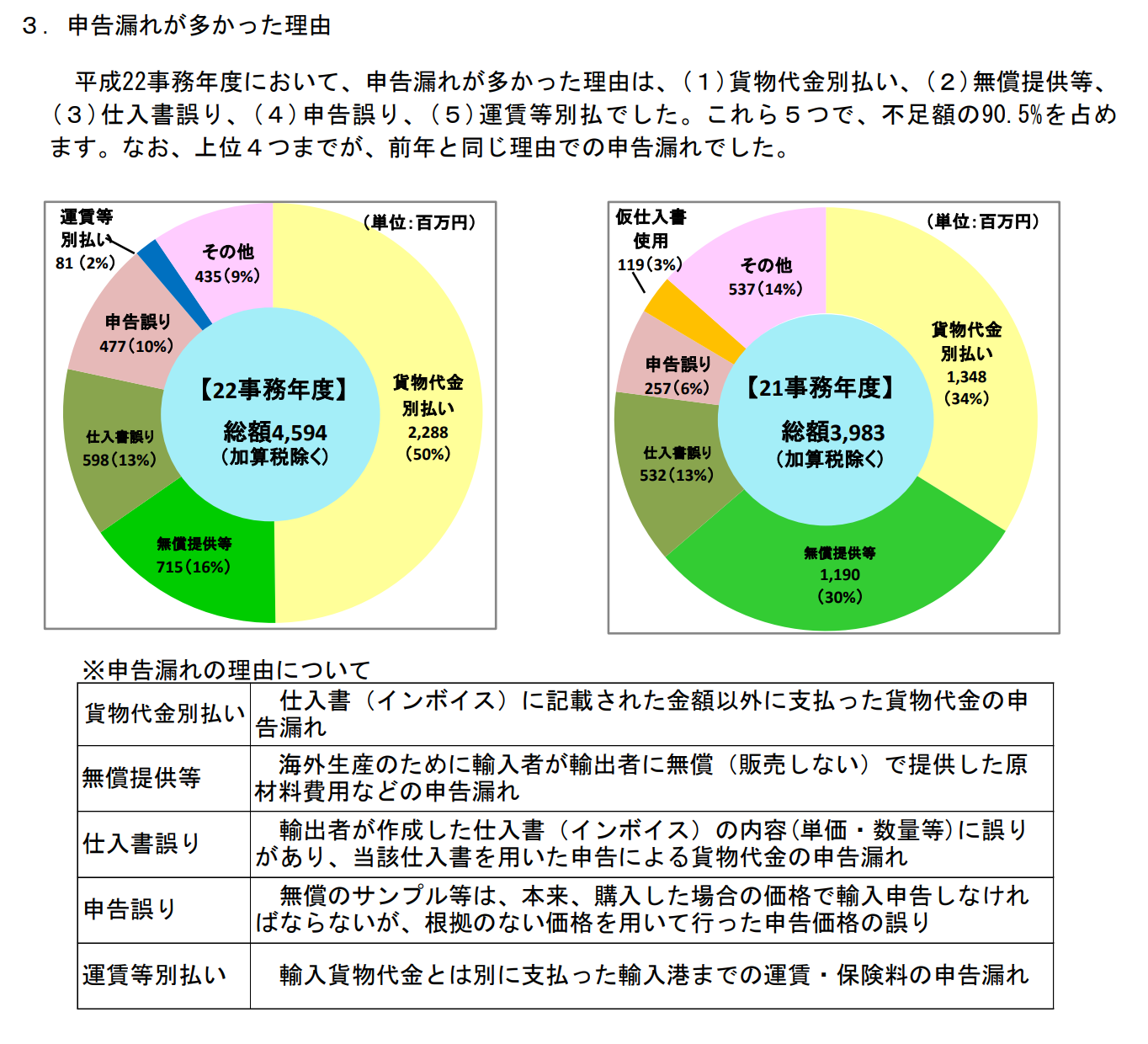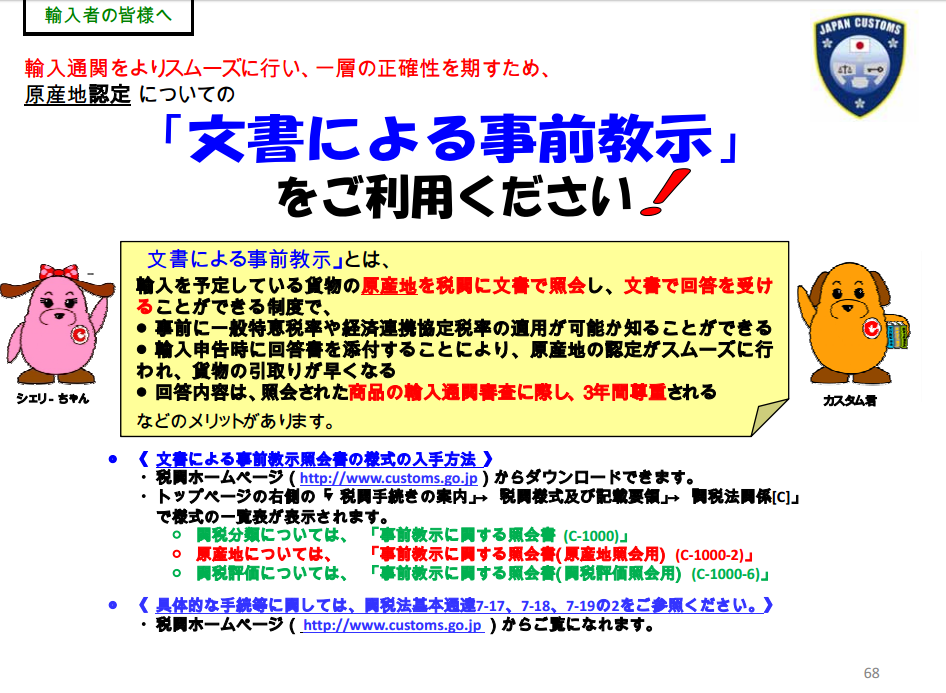EU向けの貨物に関わる関税削減において
重要な情報がEUから動画コースで紹介されております。
英語によるFTA/EPA学習コース
EUだけの専門用語等もありますが
基本的な内容は全国共通ですので、
EU向けでない貨物の輸出者様によっても非常に有益な学習動画です。
また、今後広がっていく自由貿易経済連携の知識を要する
通関士様にも為になる学習動画かと思いますので
是非ご覧になってください。
FTA/EPA学習コースは会話形式で行われます。
上級税関職員のMargotさん
税関職員のAnnaさん
商社マンのVincentさん
の3人がFTA/EPAについて質問、回答を行います。

■事前教示コース
EU内の税関において貨物がどのHSコードに該当するか
事前に書面で回答をもらうための手続き
■原産地規則コース
EU内にて経済連携協定国からの貨物を原産地証明書を用いて
減免税する為の原産地規則等の解説
■関税評価コース
関税評価の適用についての解説
■入港から保税制度
貨物がEU内に到着後の手続き、保税制度の解説
■税関手続き
EU内での税関手続きを解説
■EU内の税制
EU内での商取引における消費税(VAT)と免税について
国内取引、EU間取引、国際取引等一般税制の解説
(要Flashインストール)