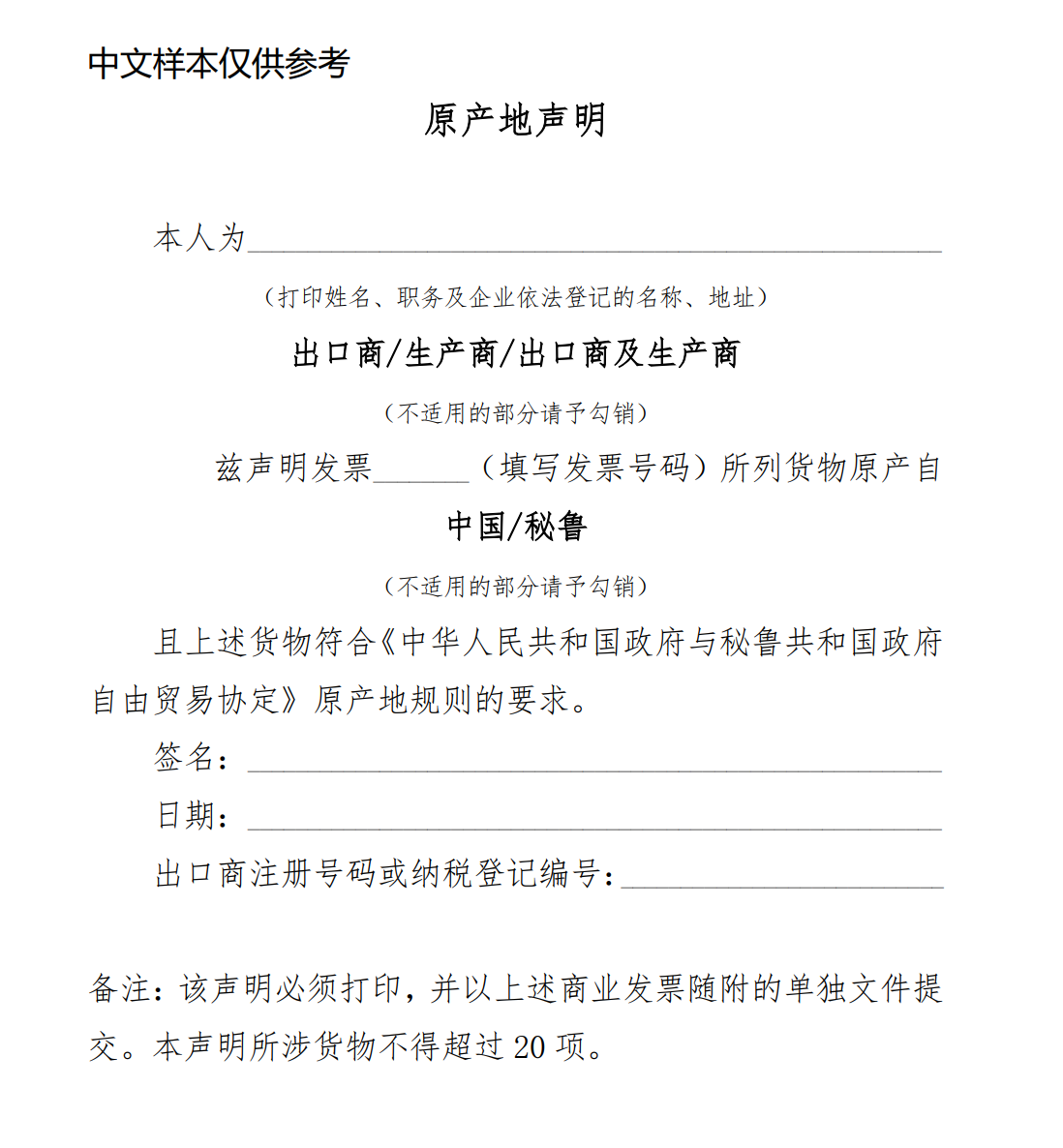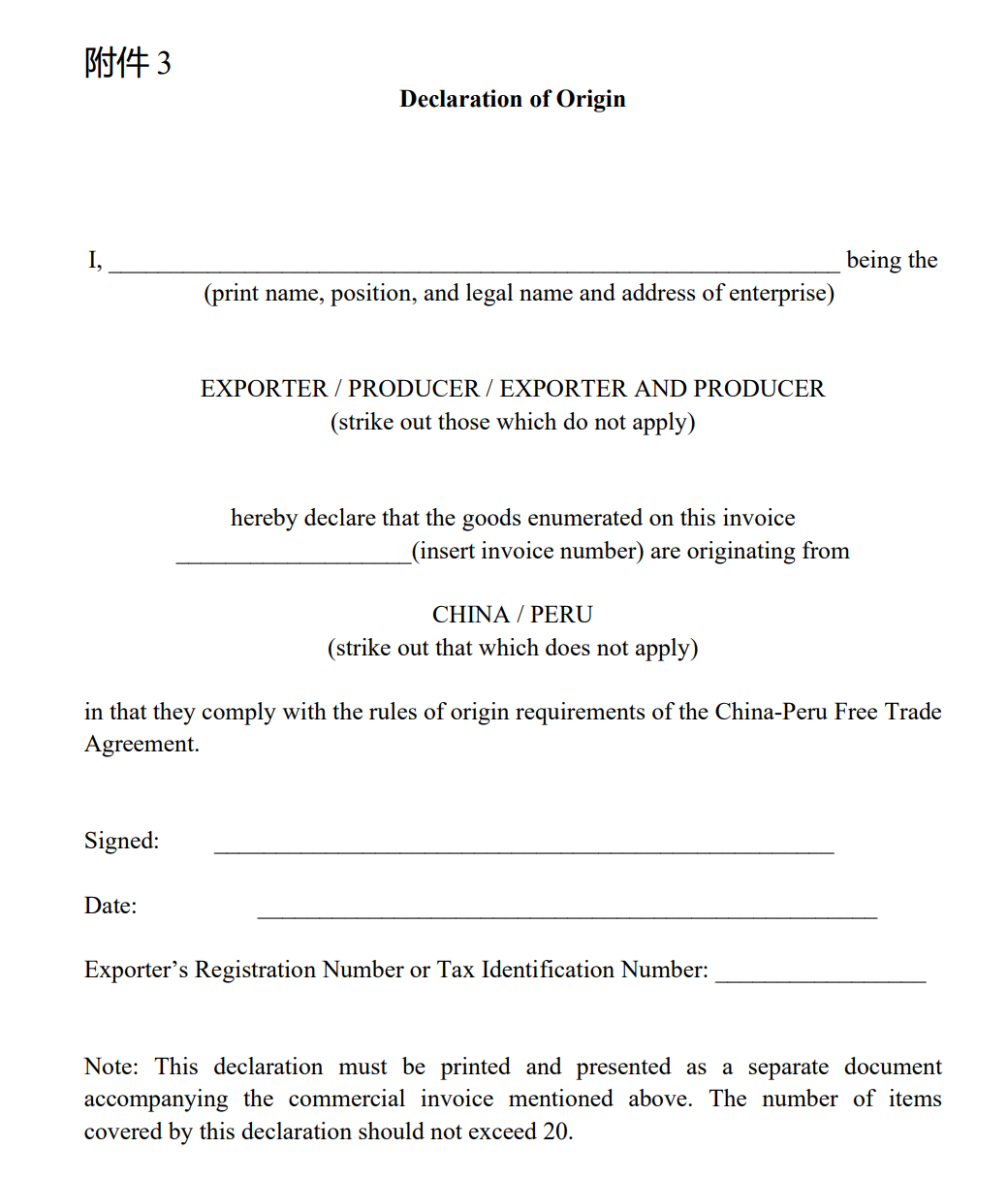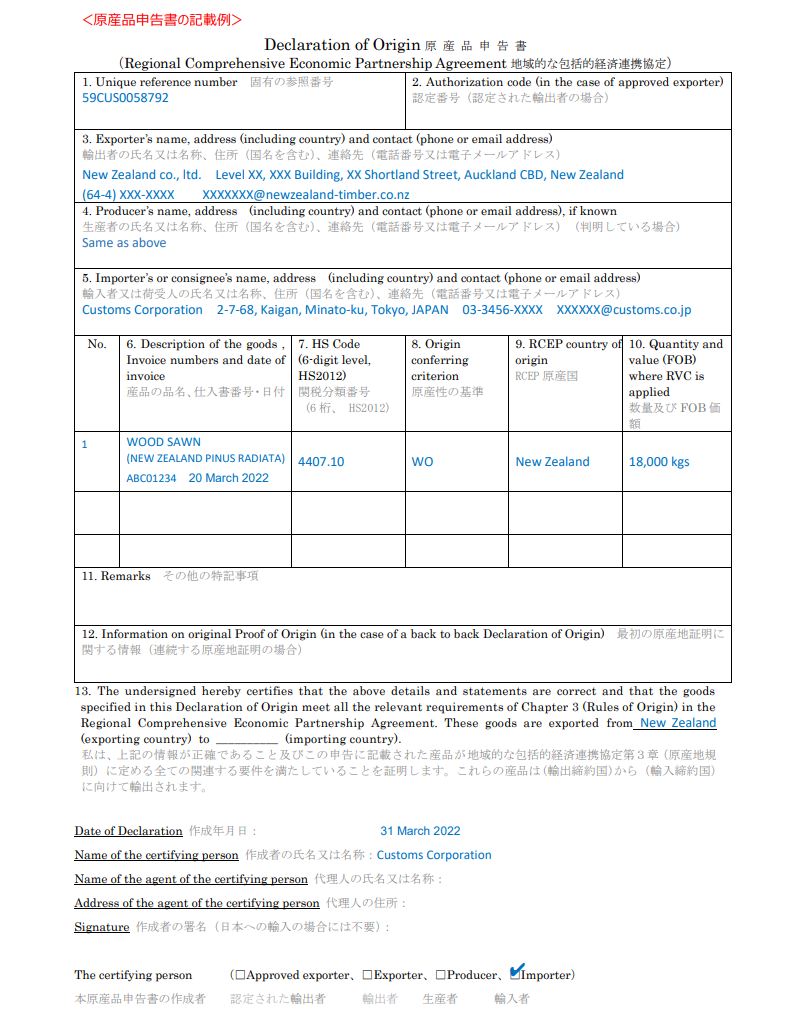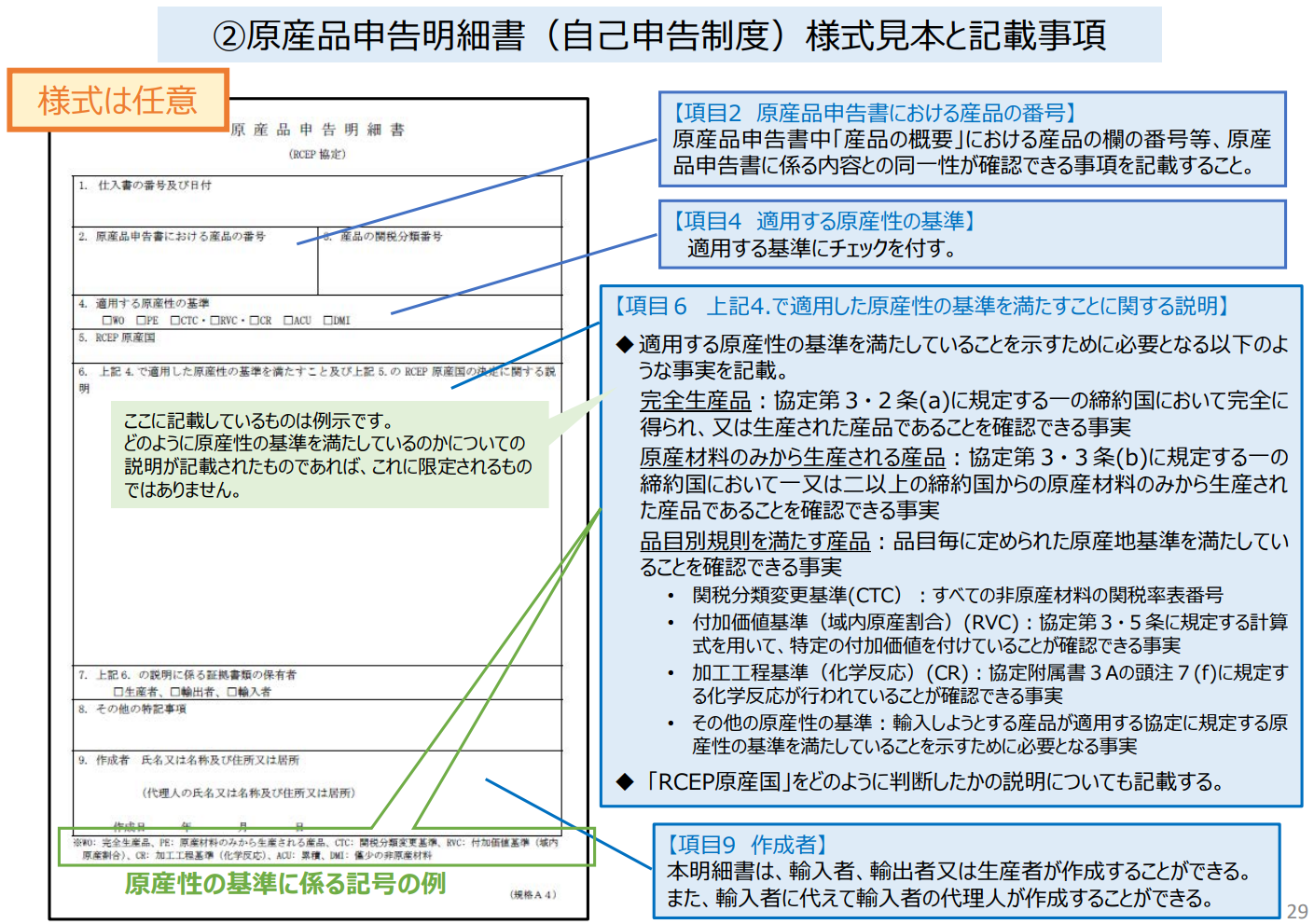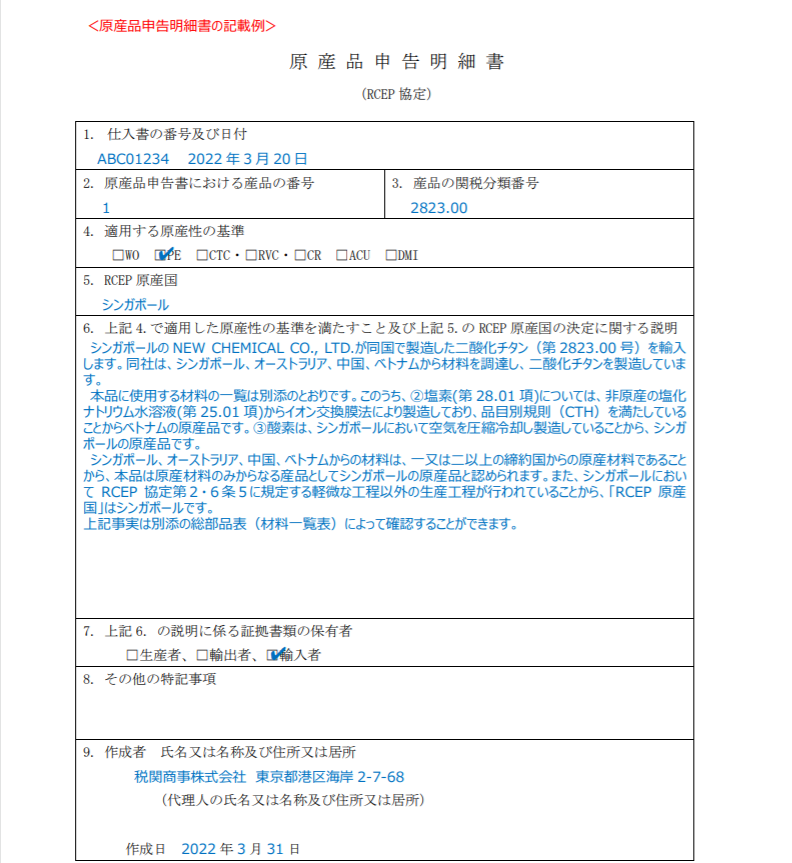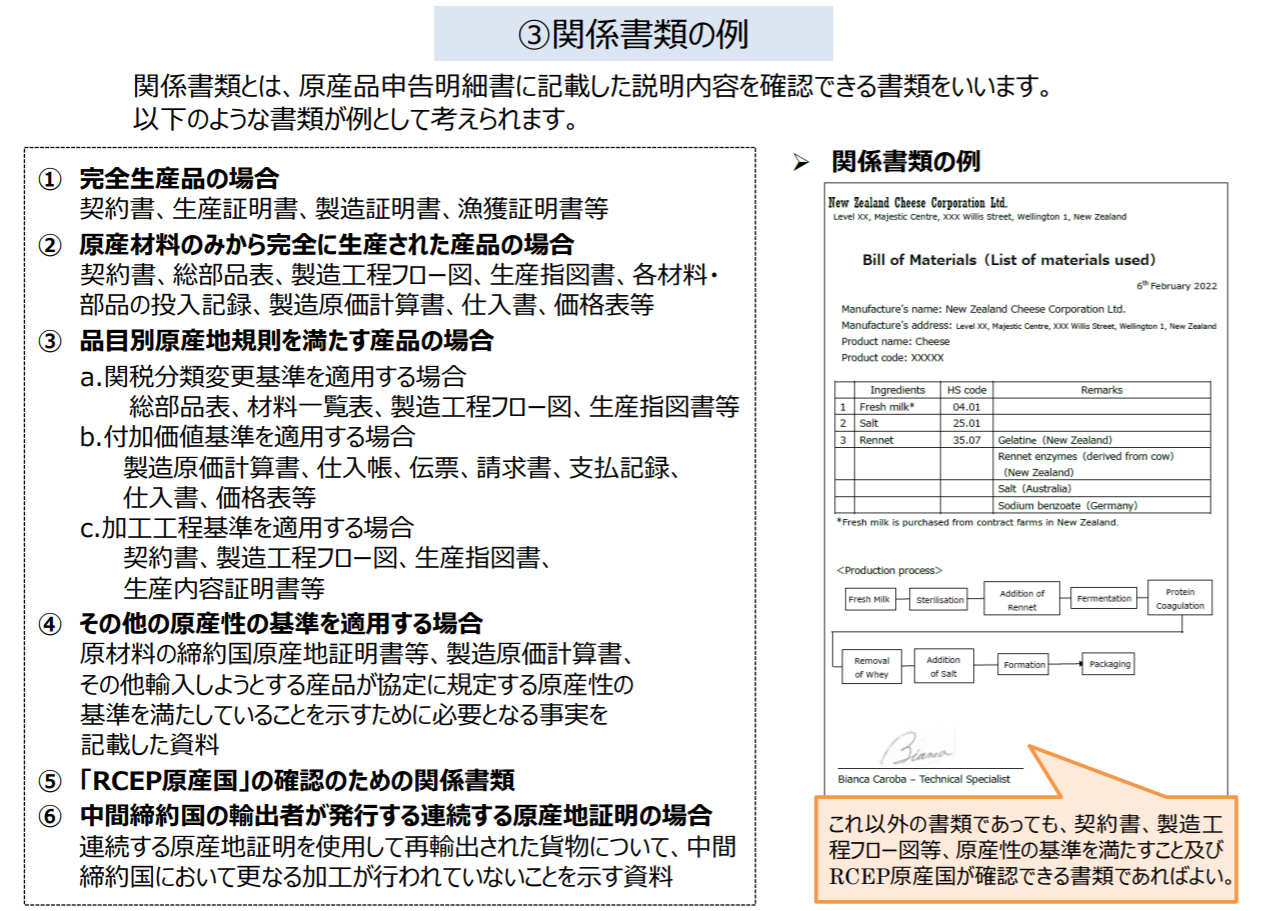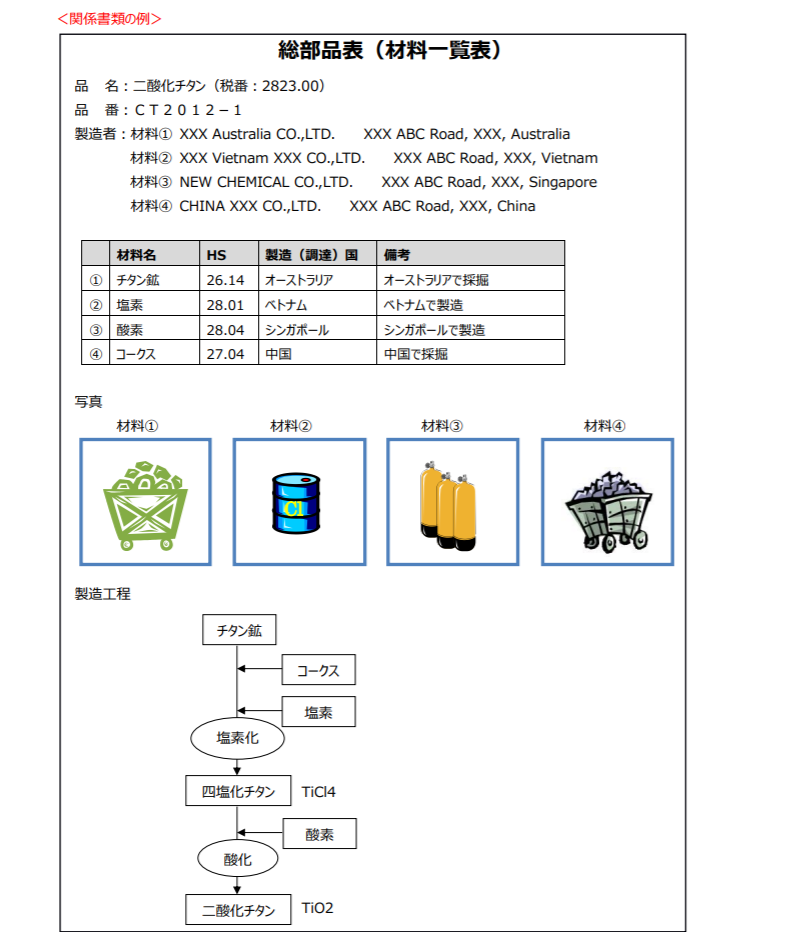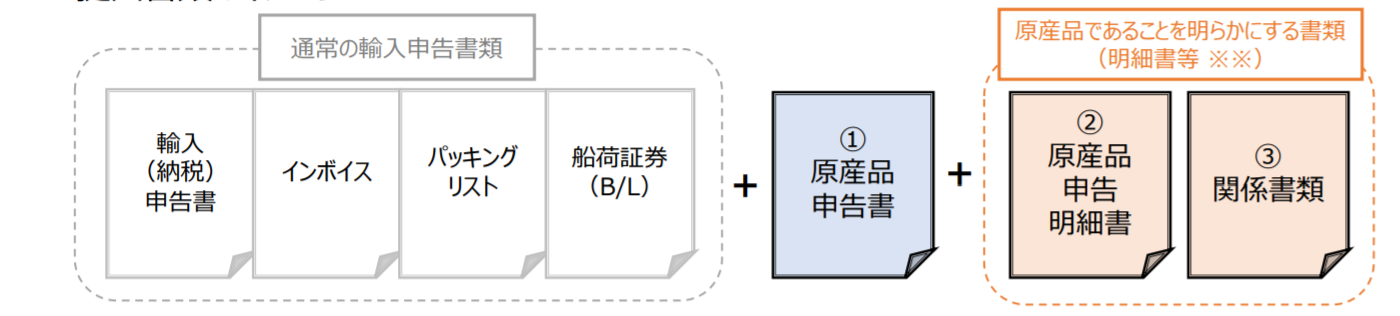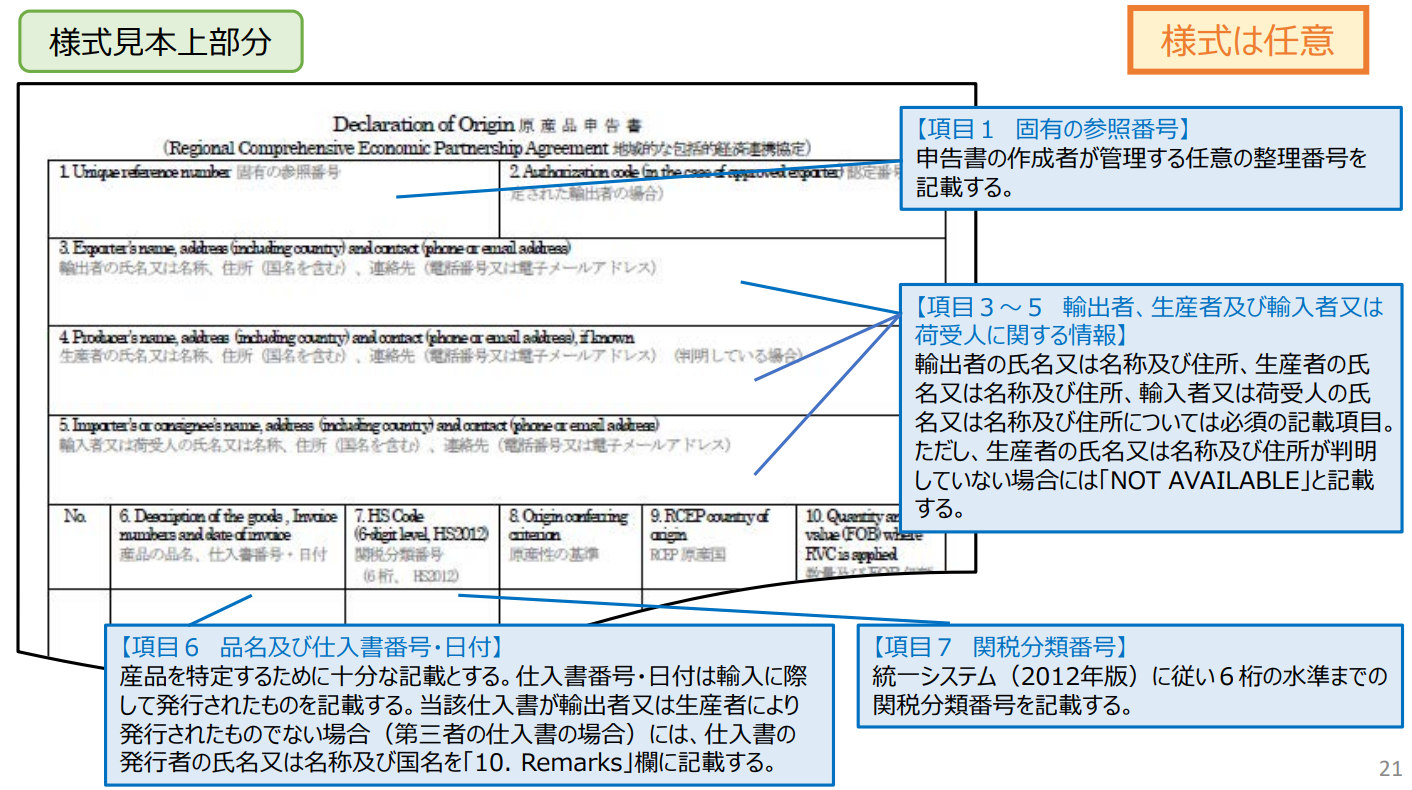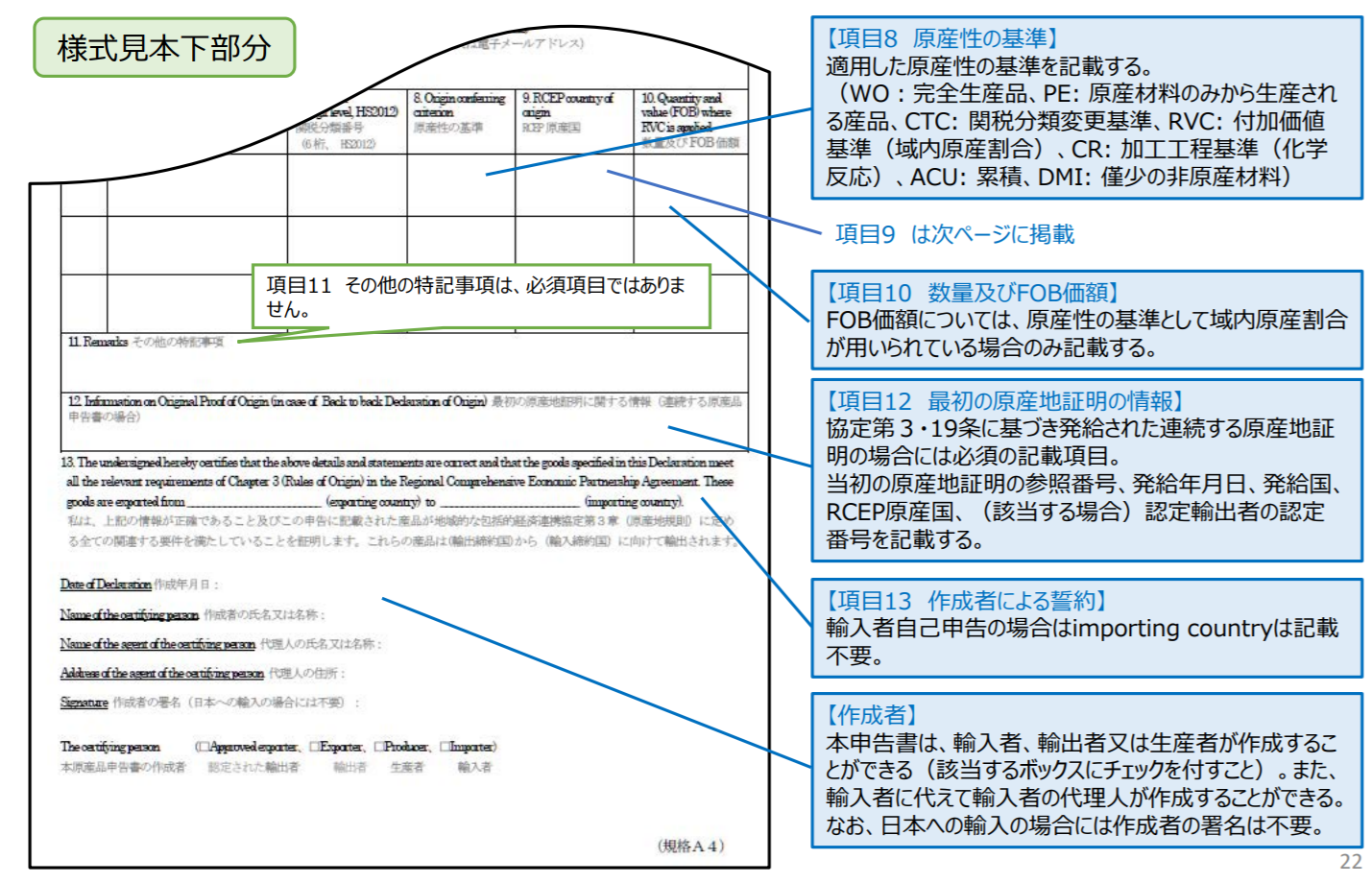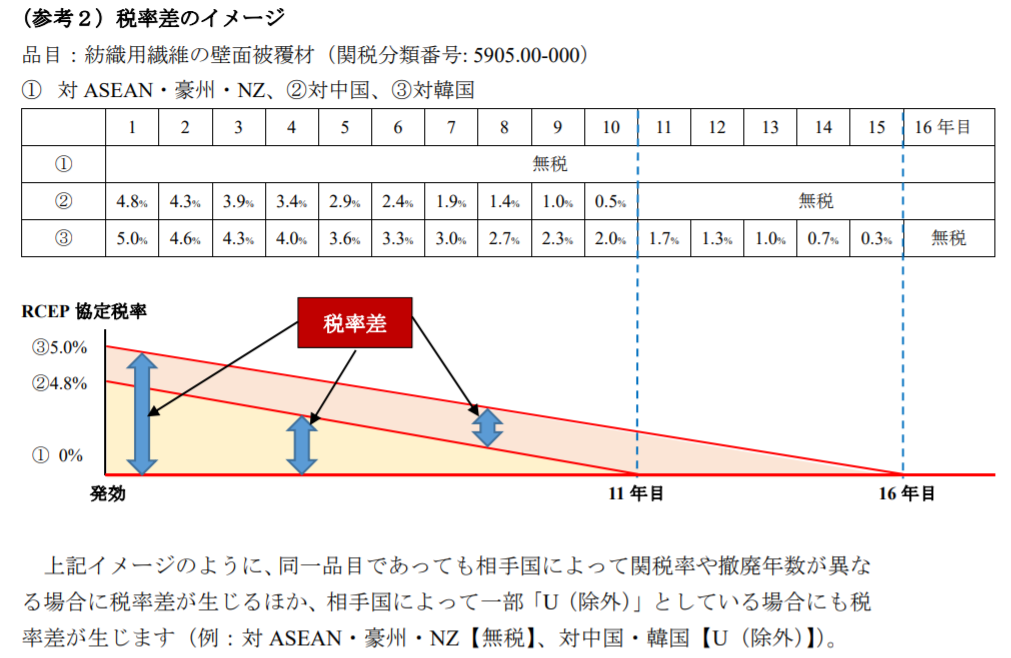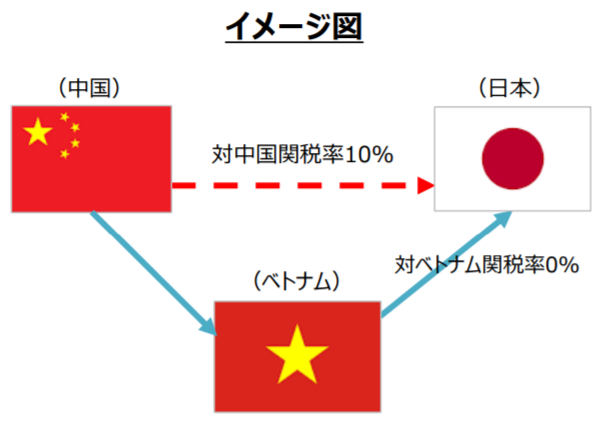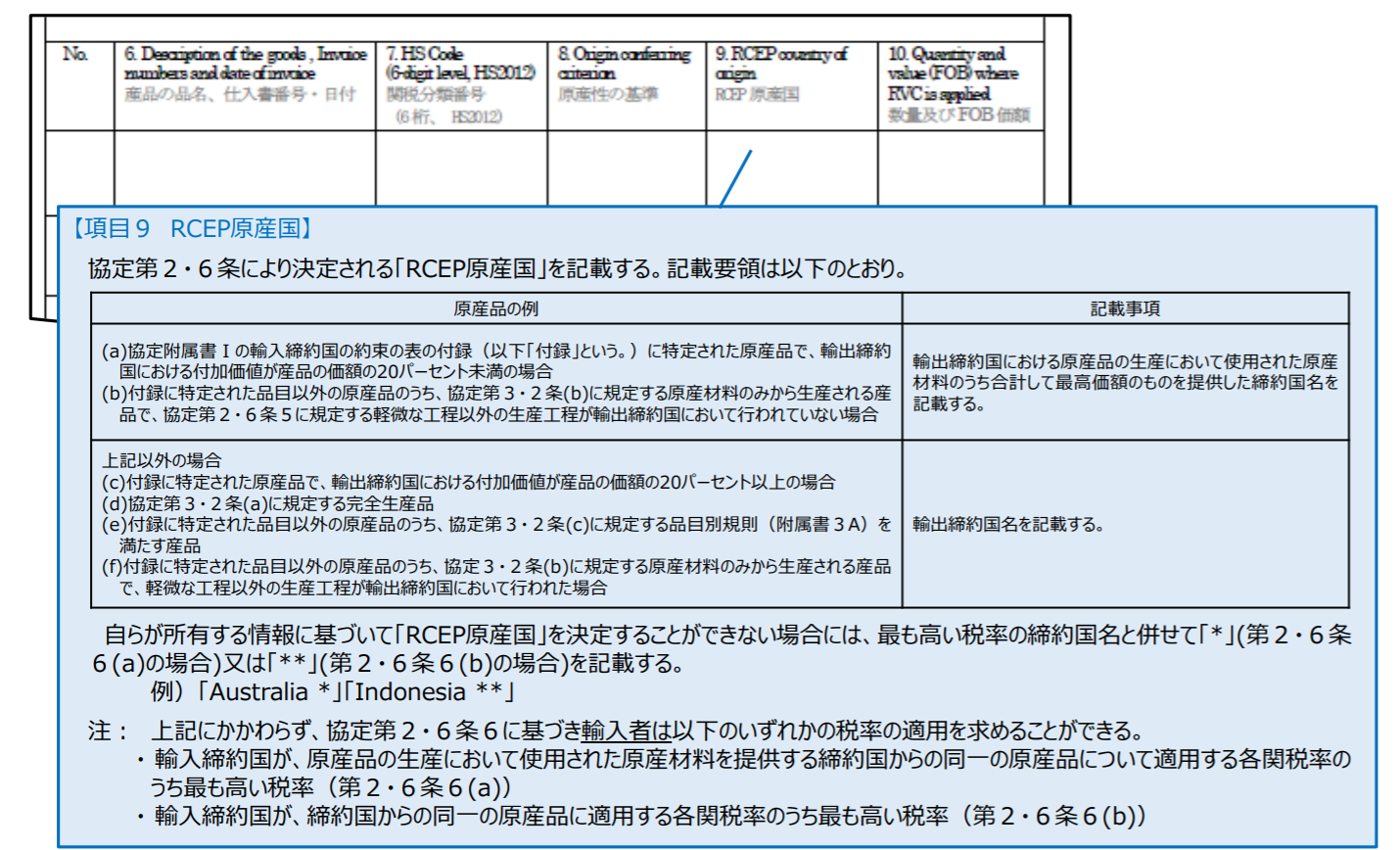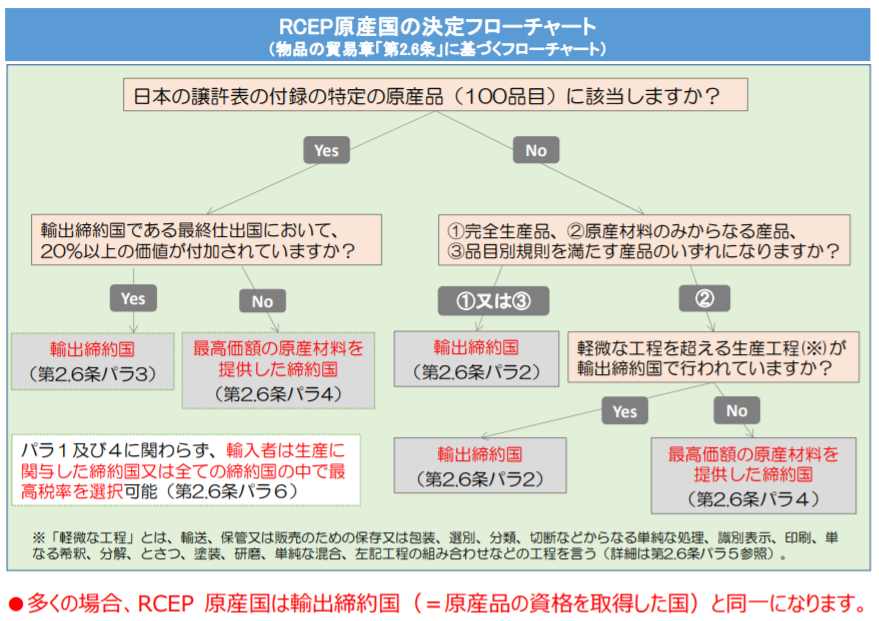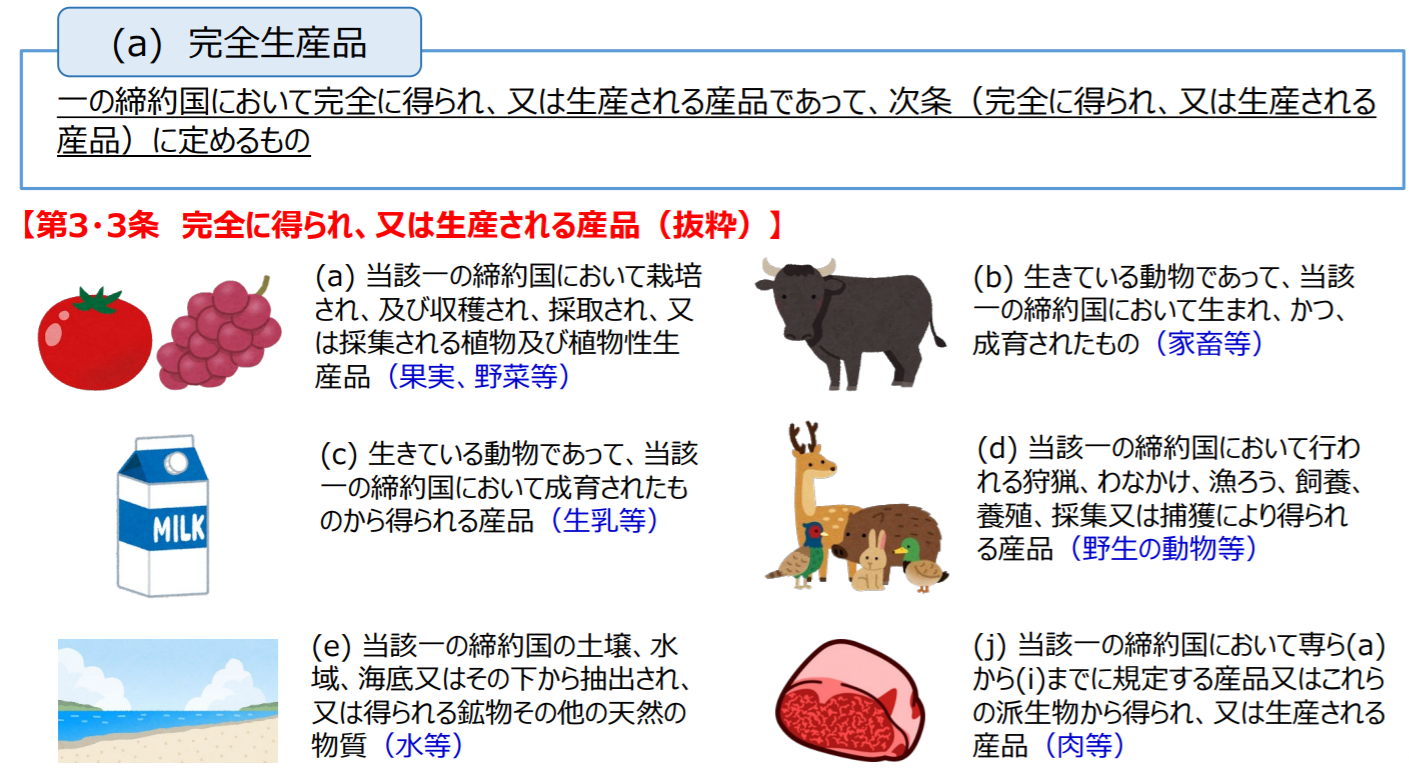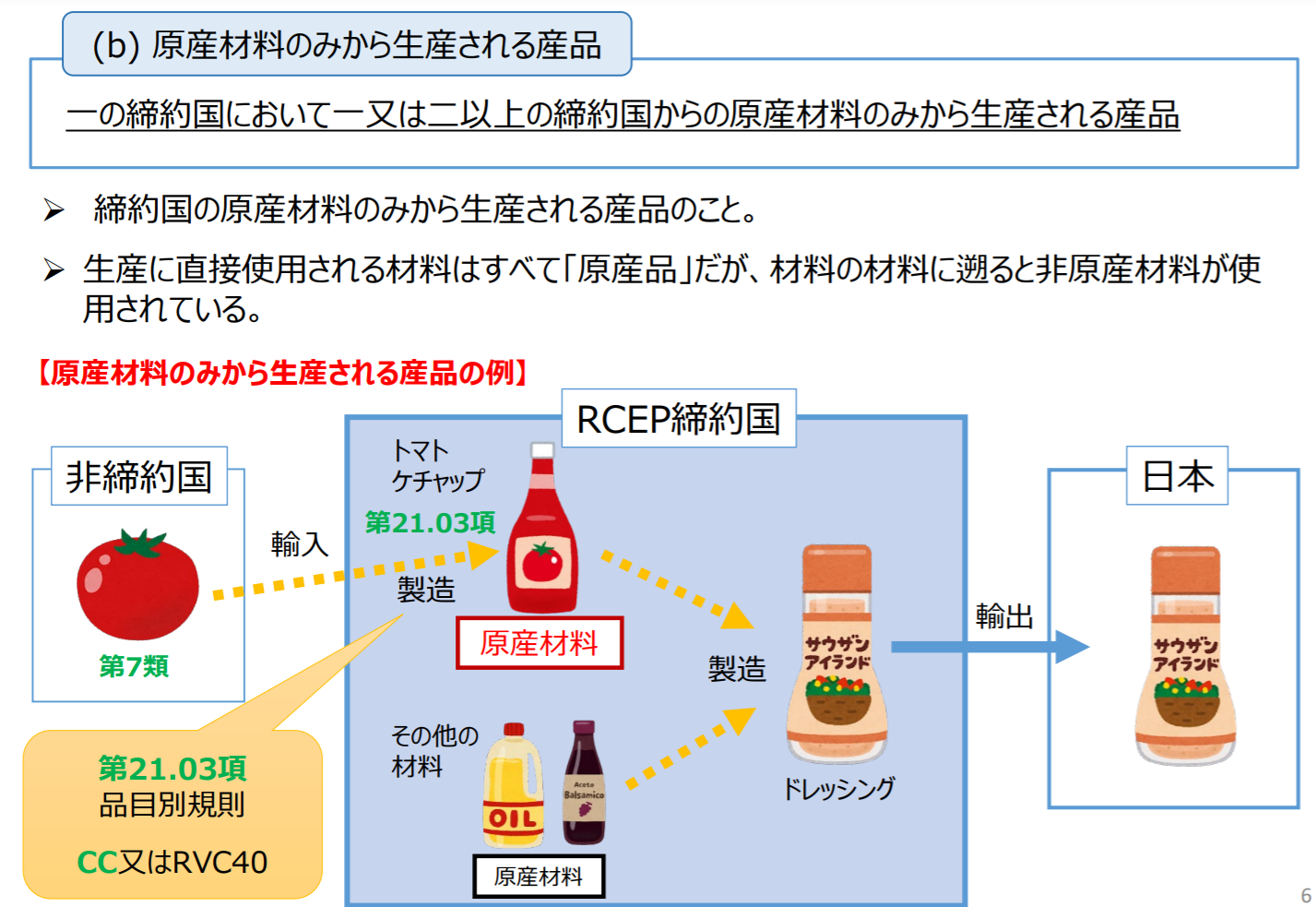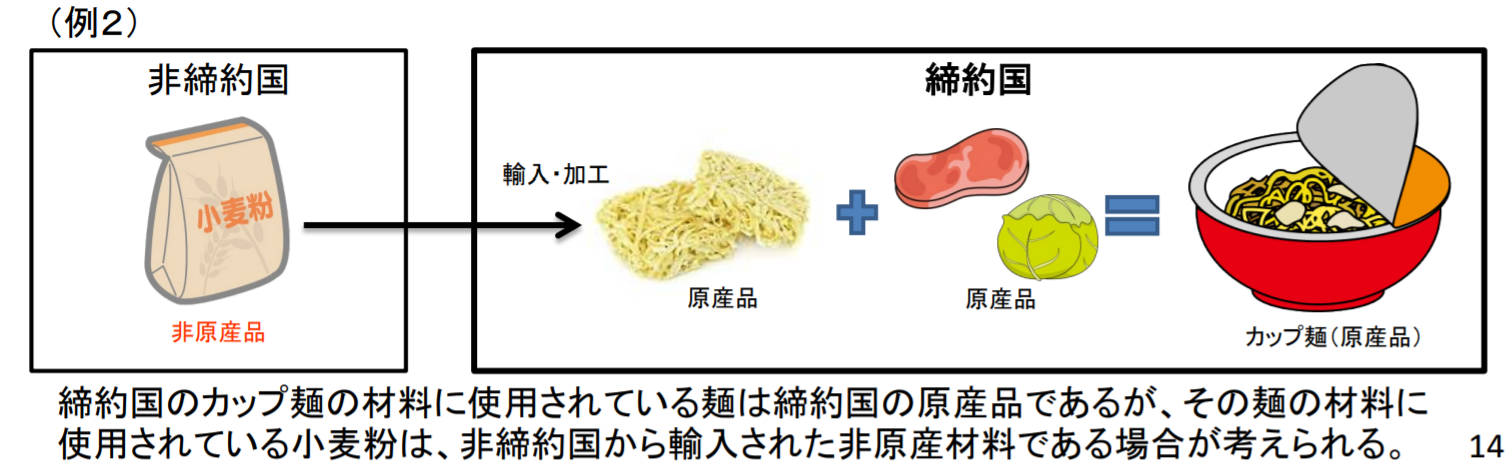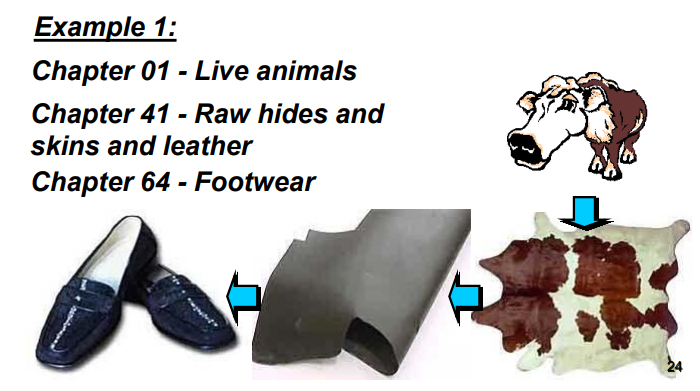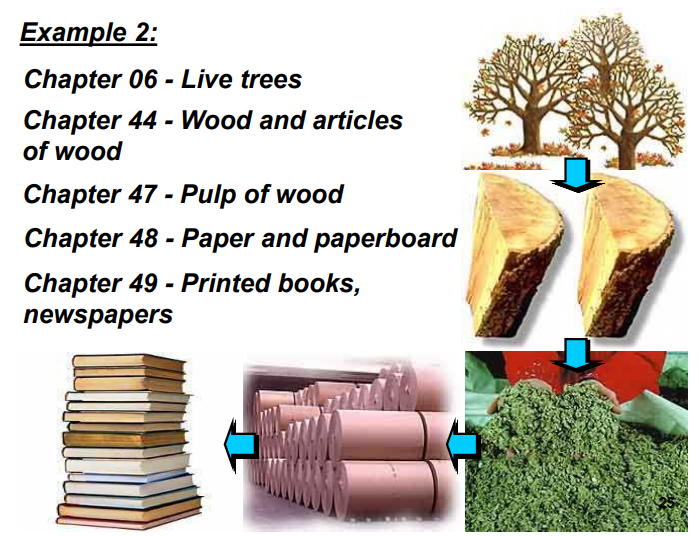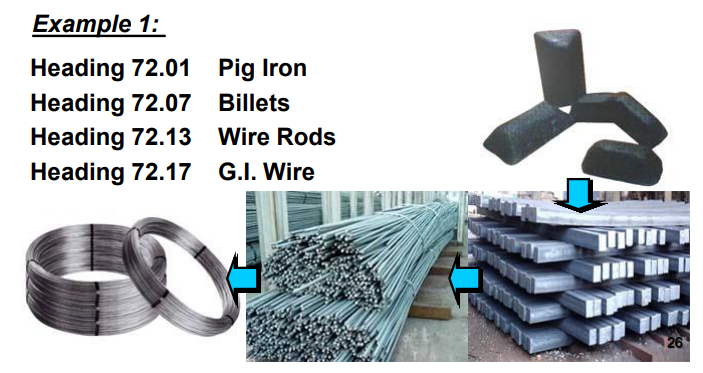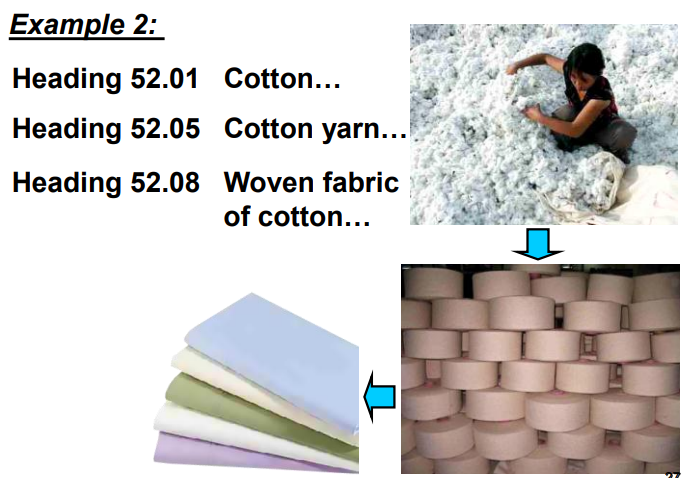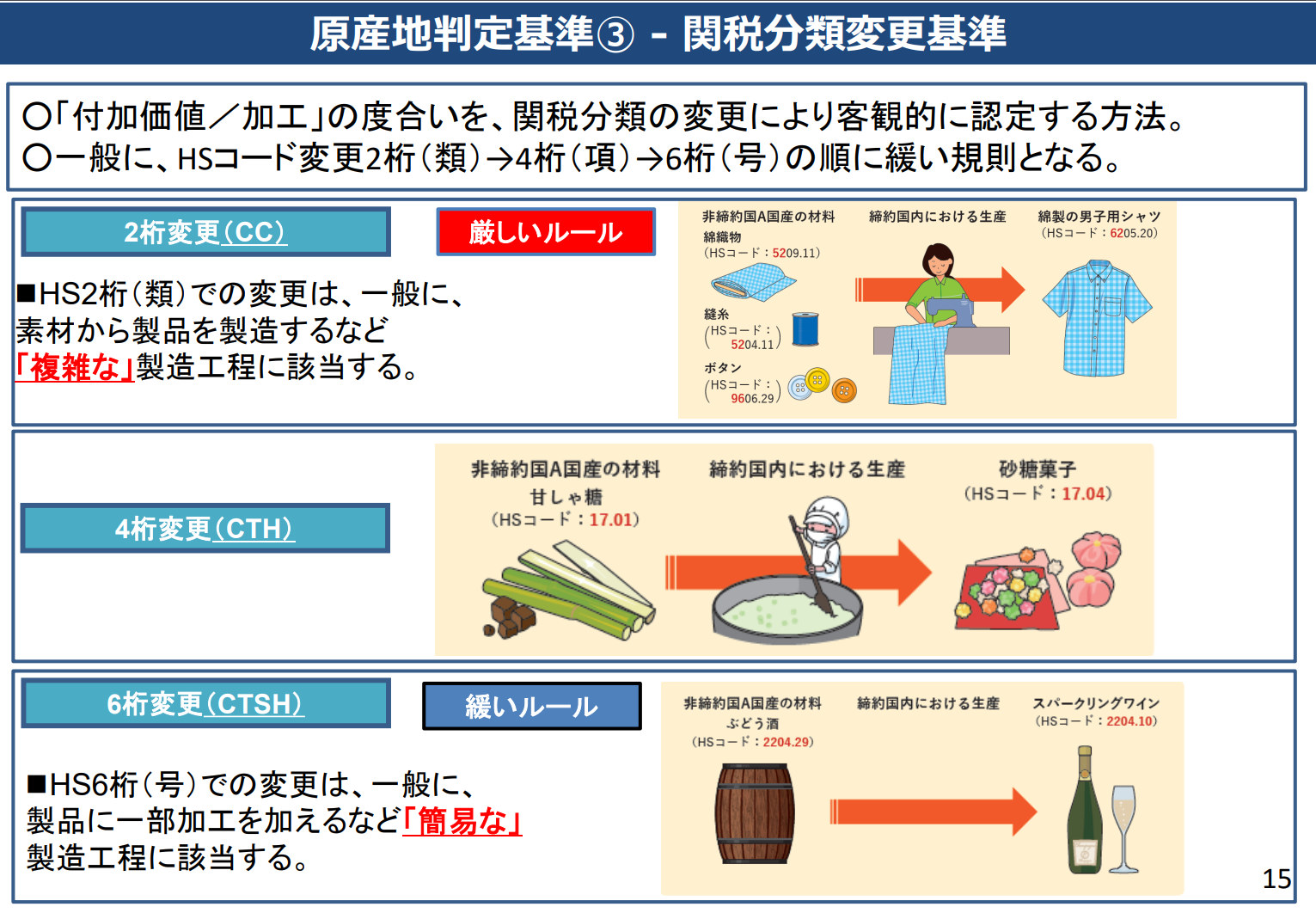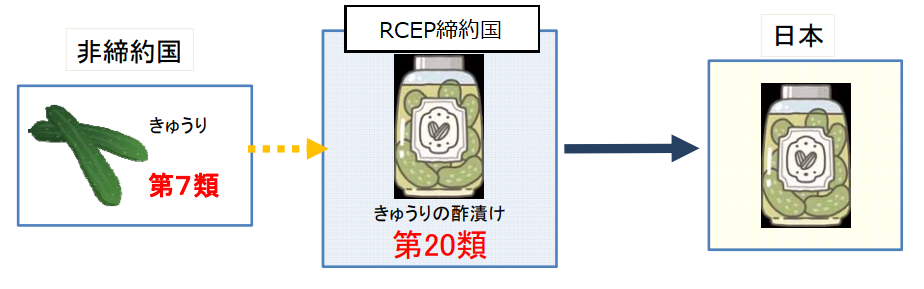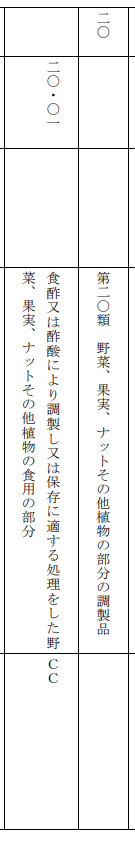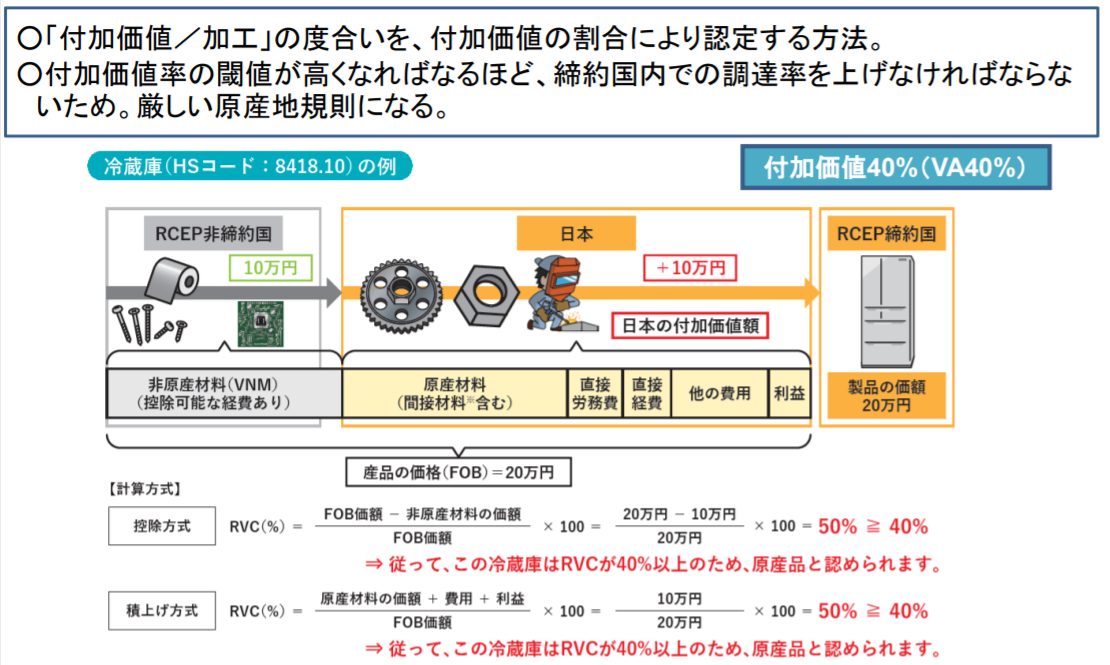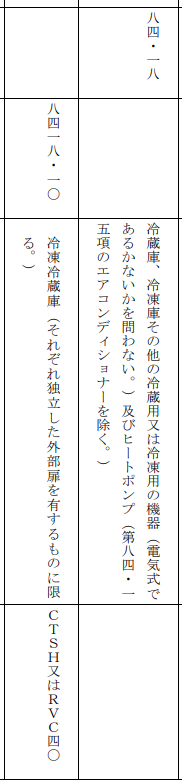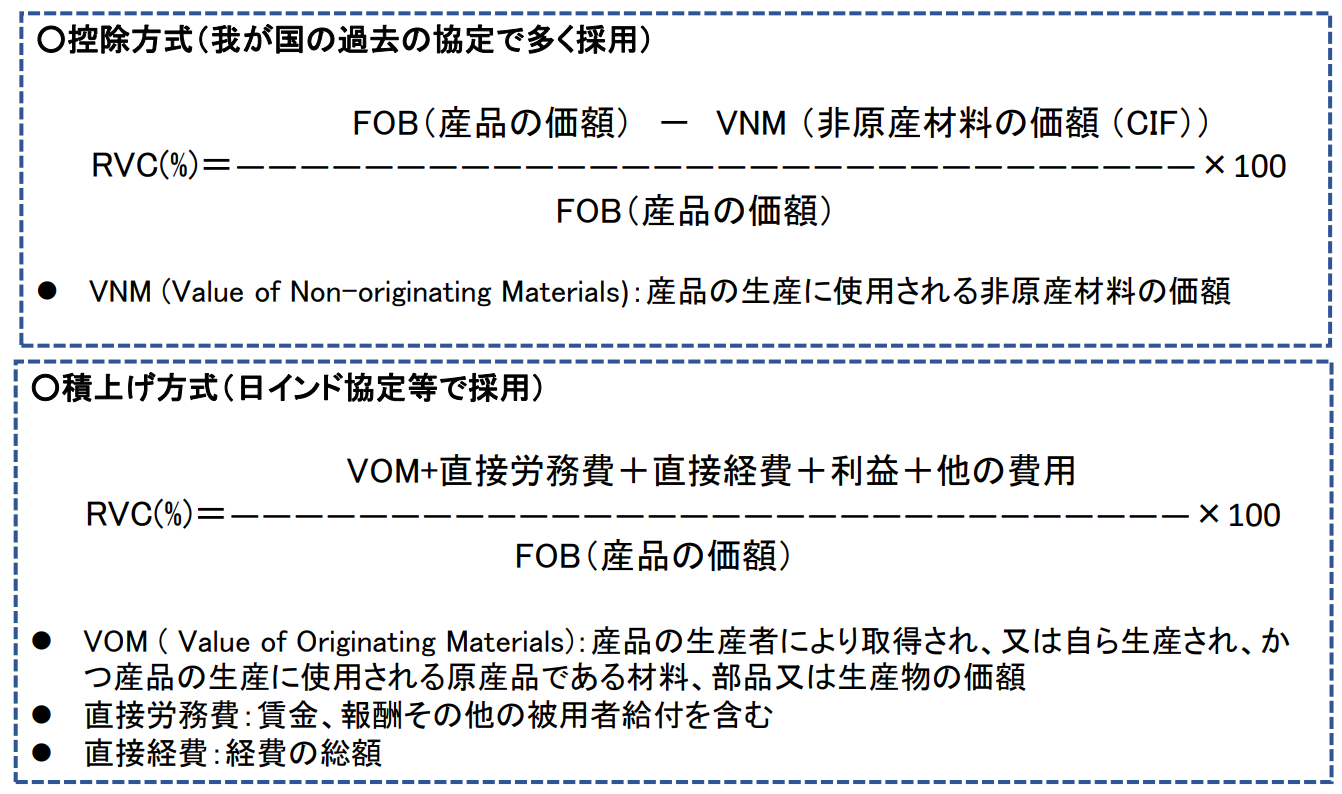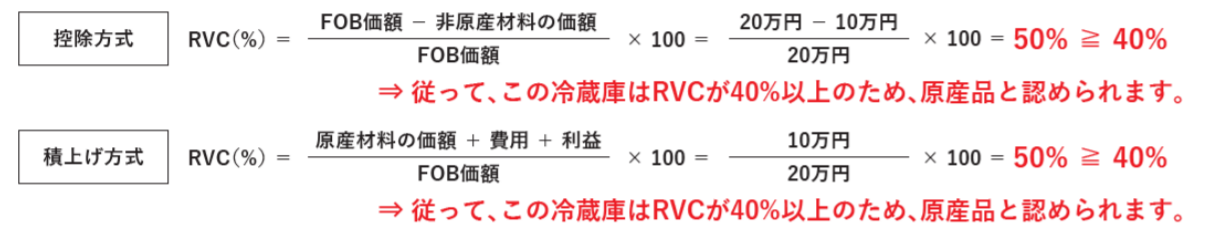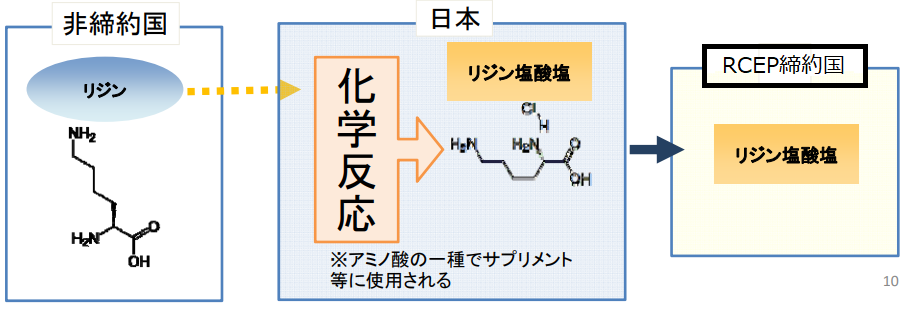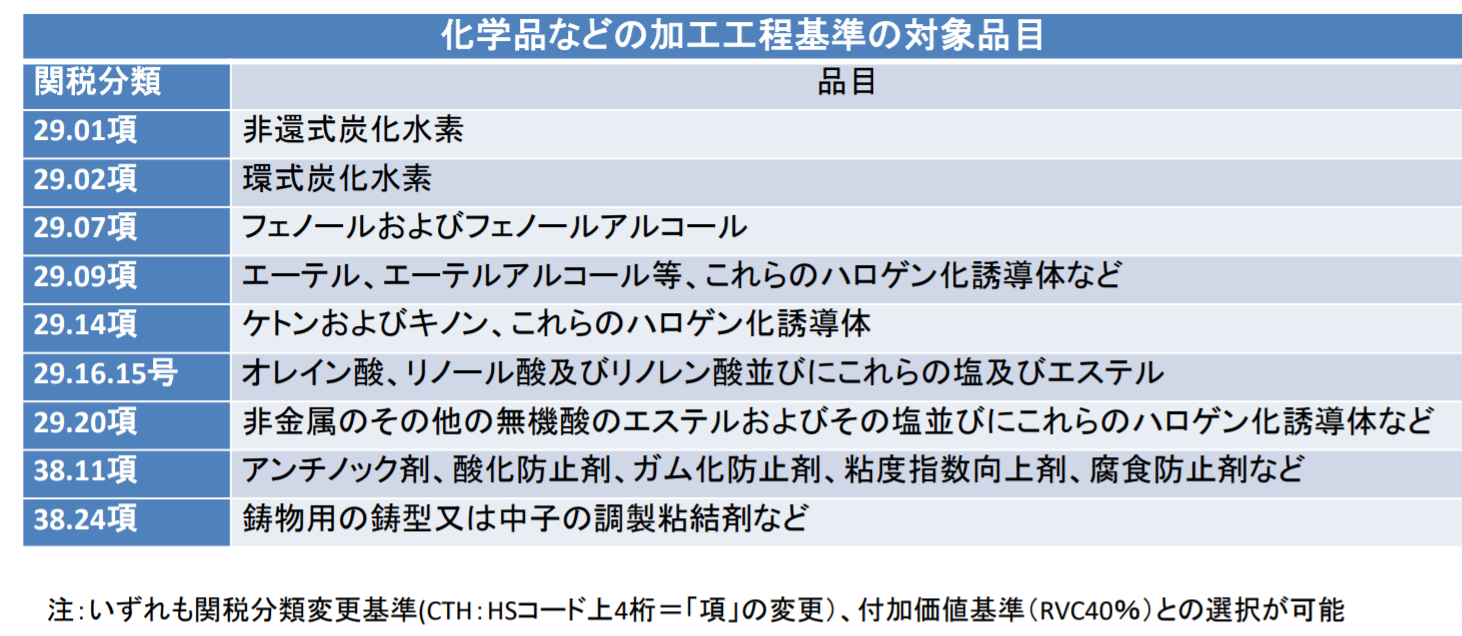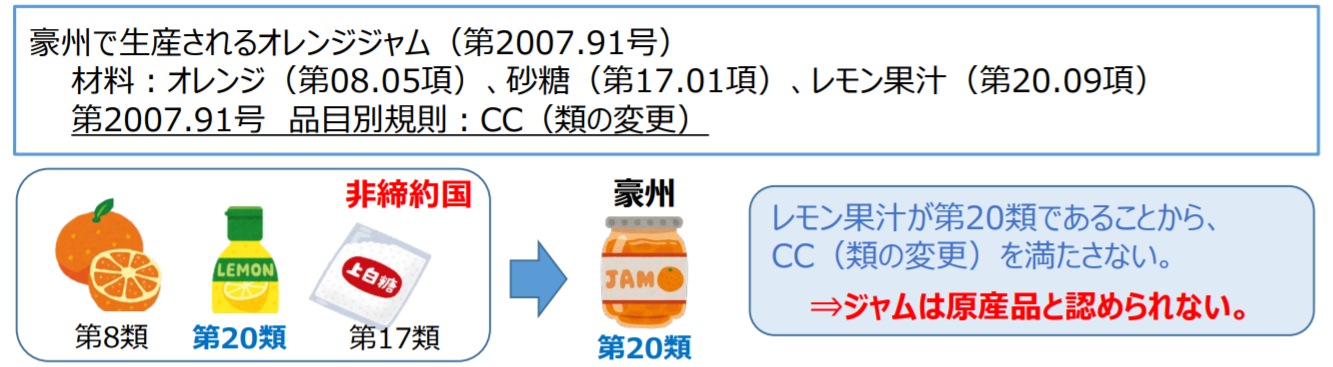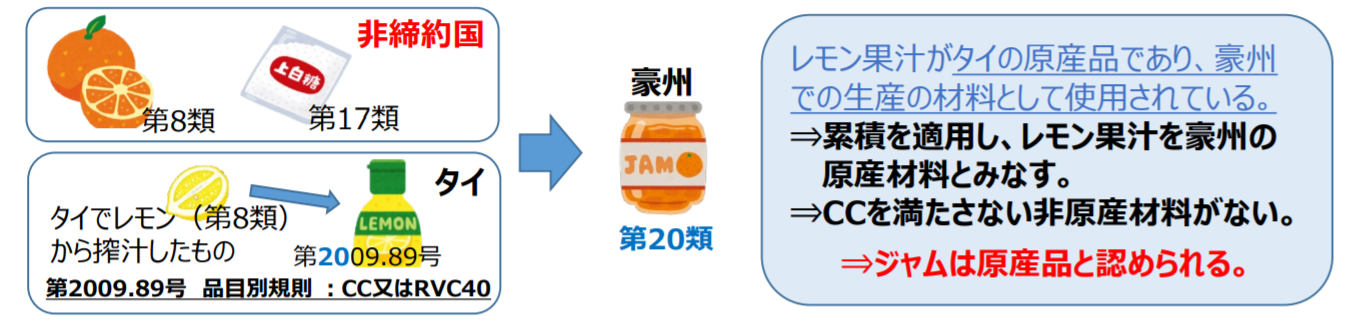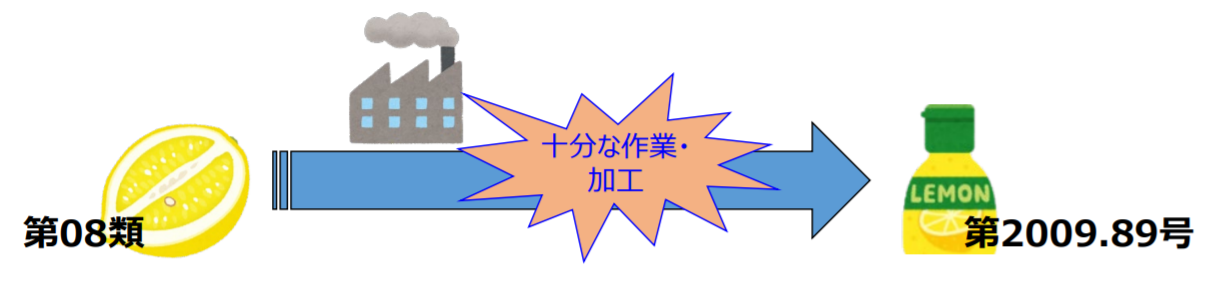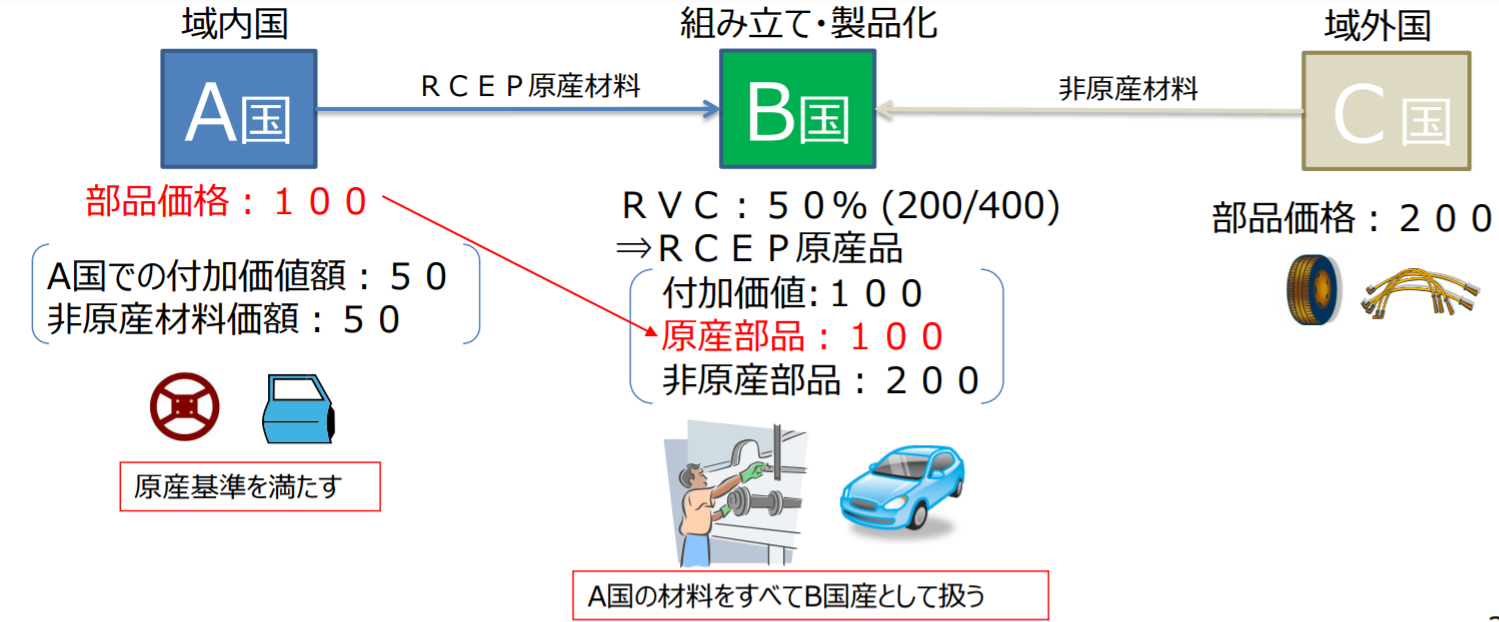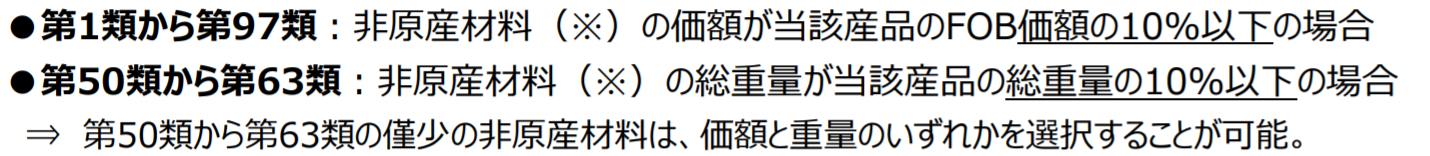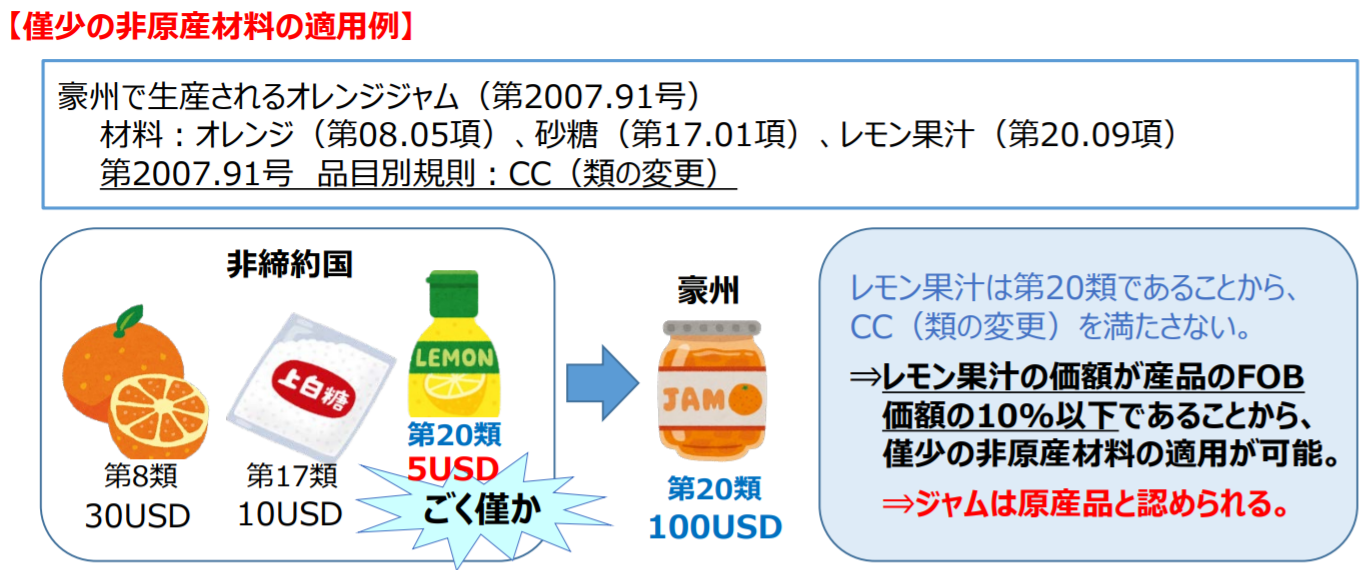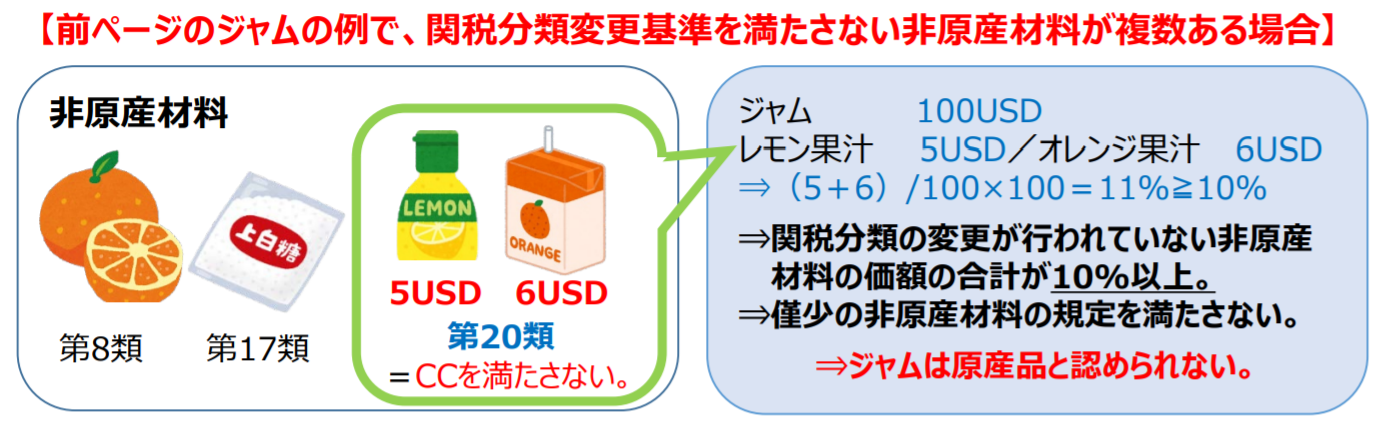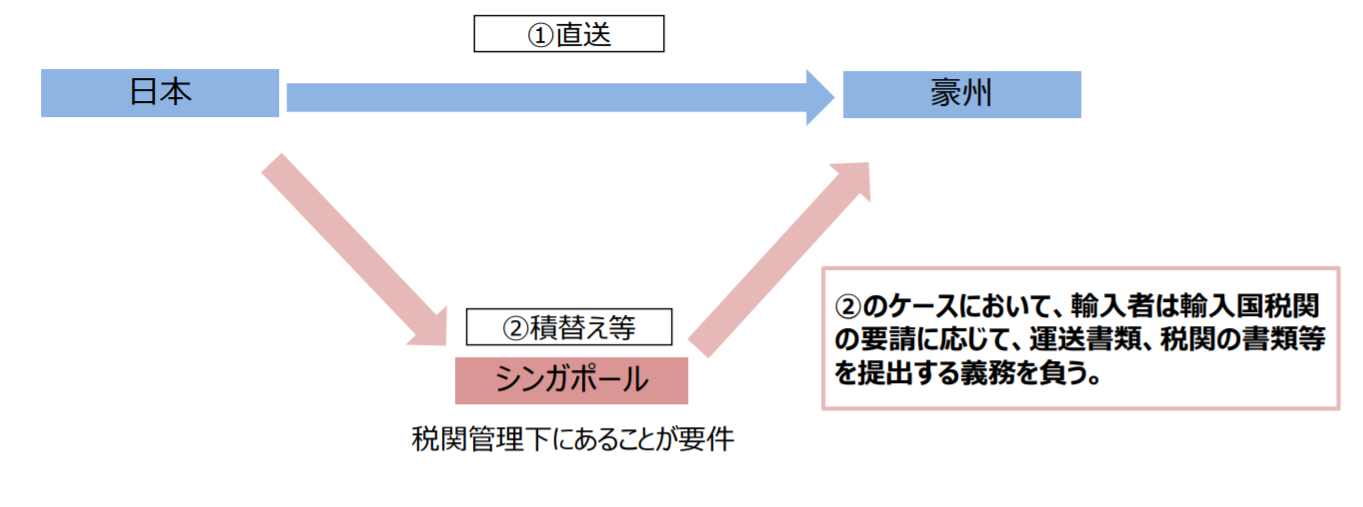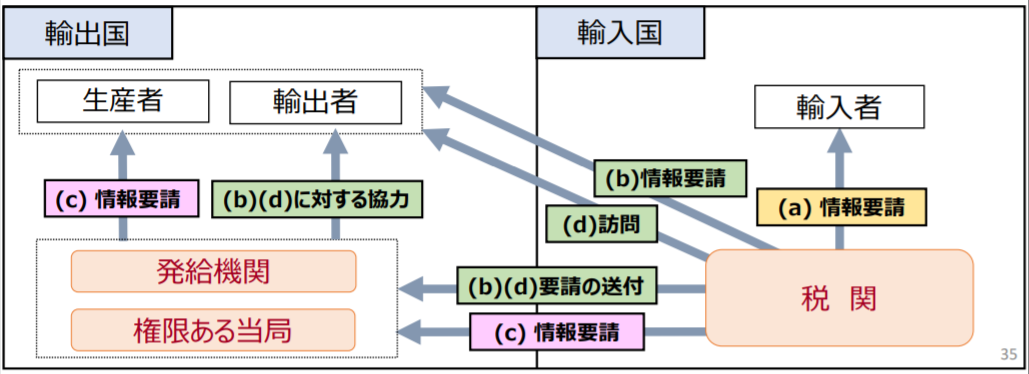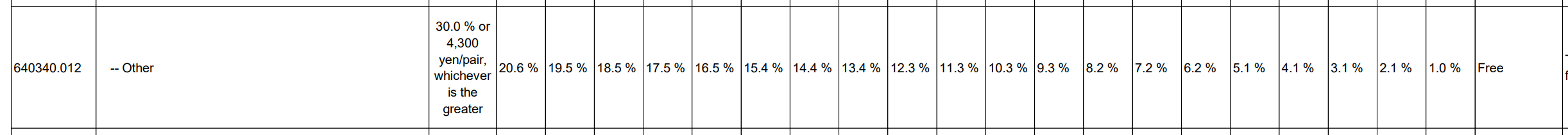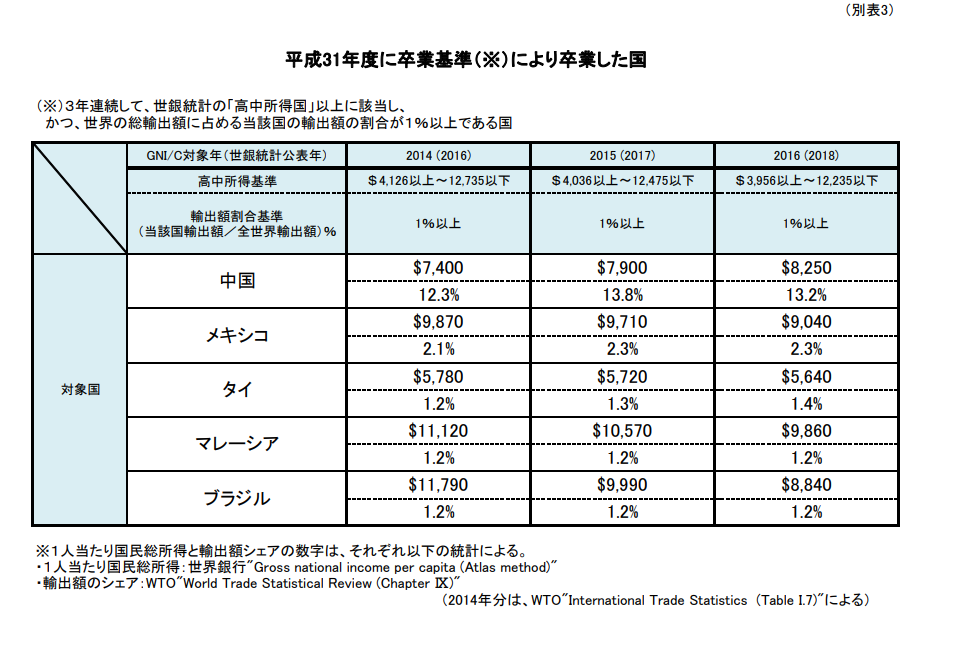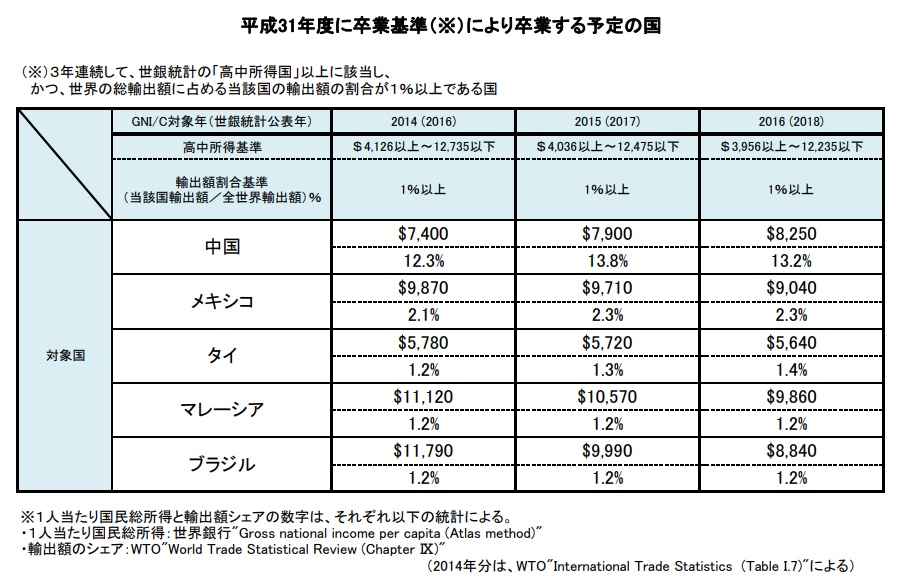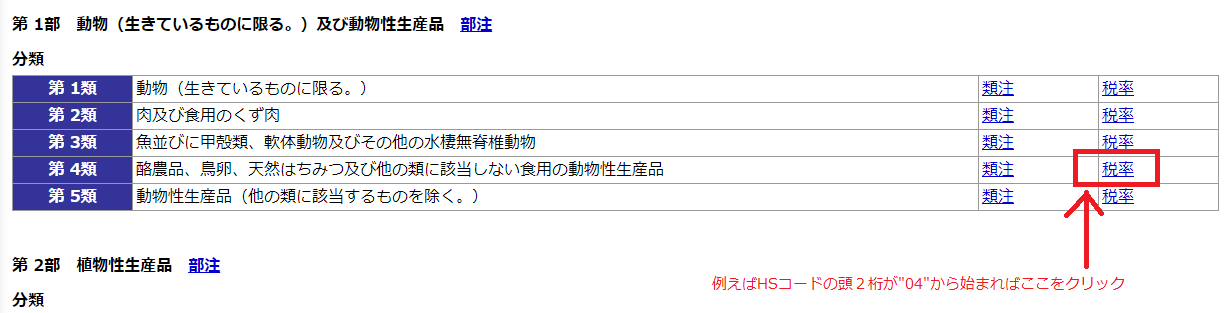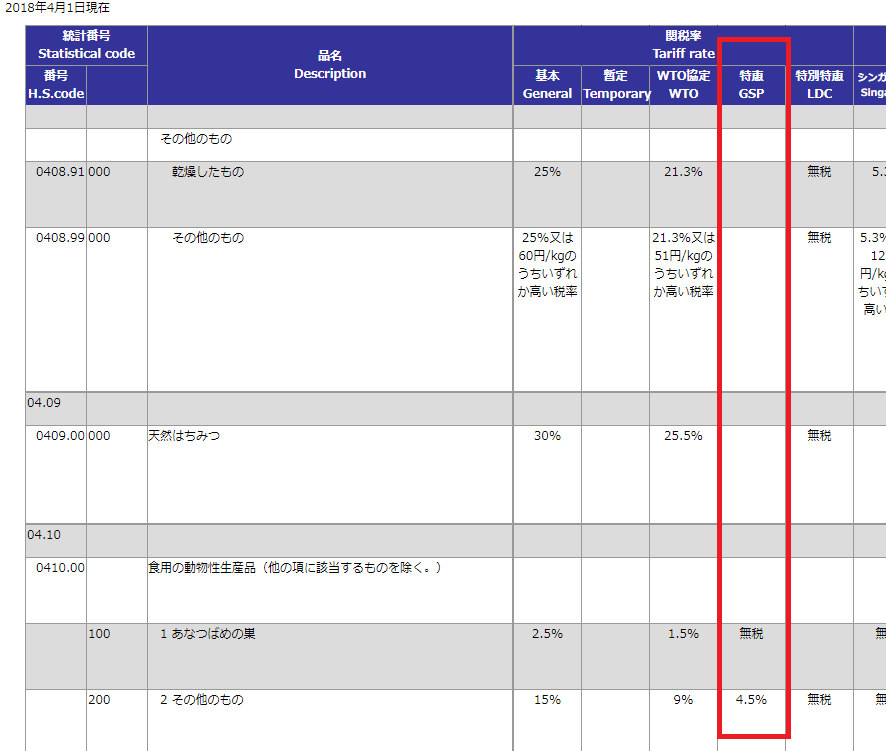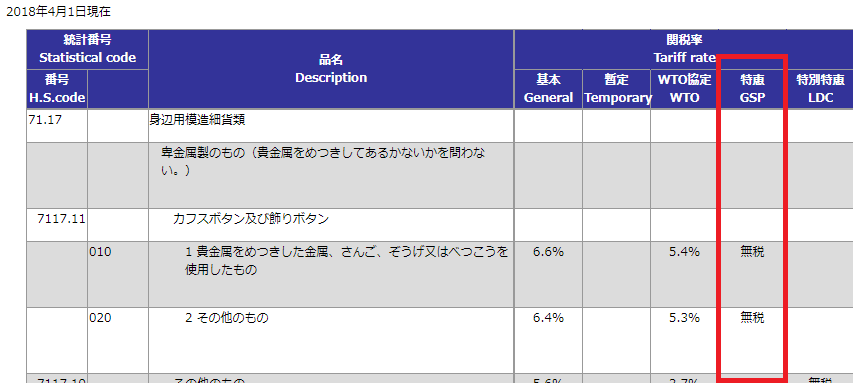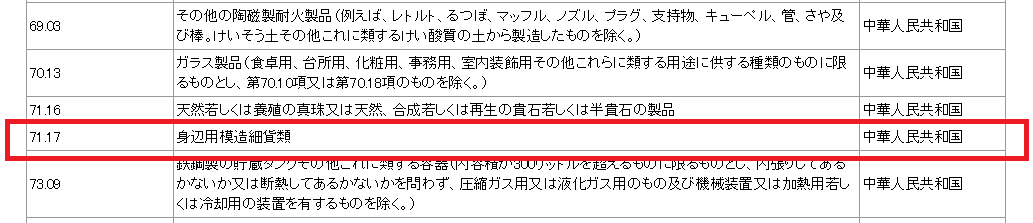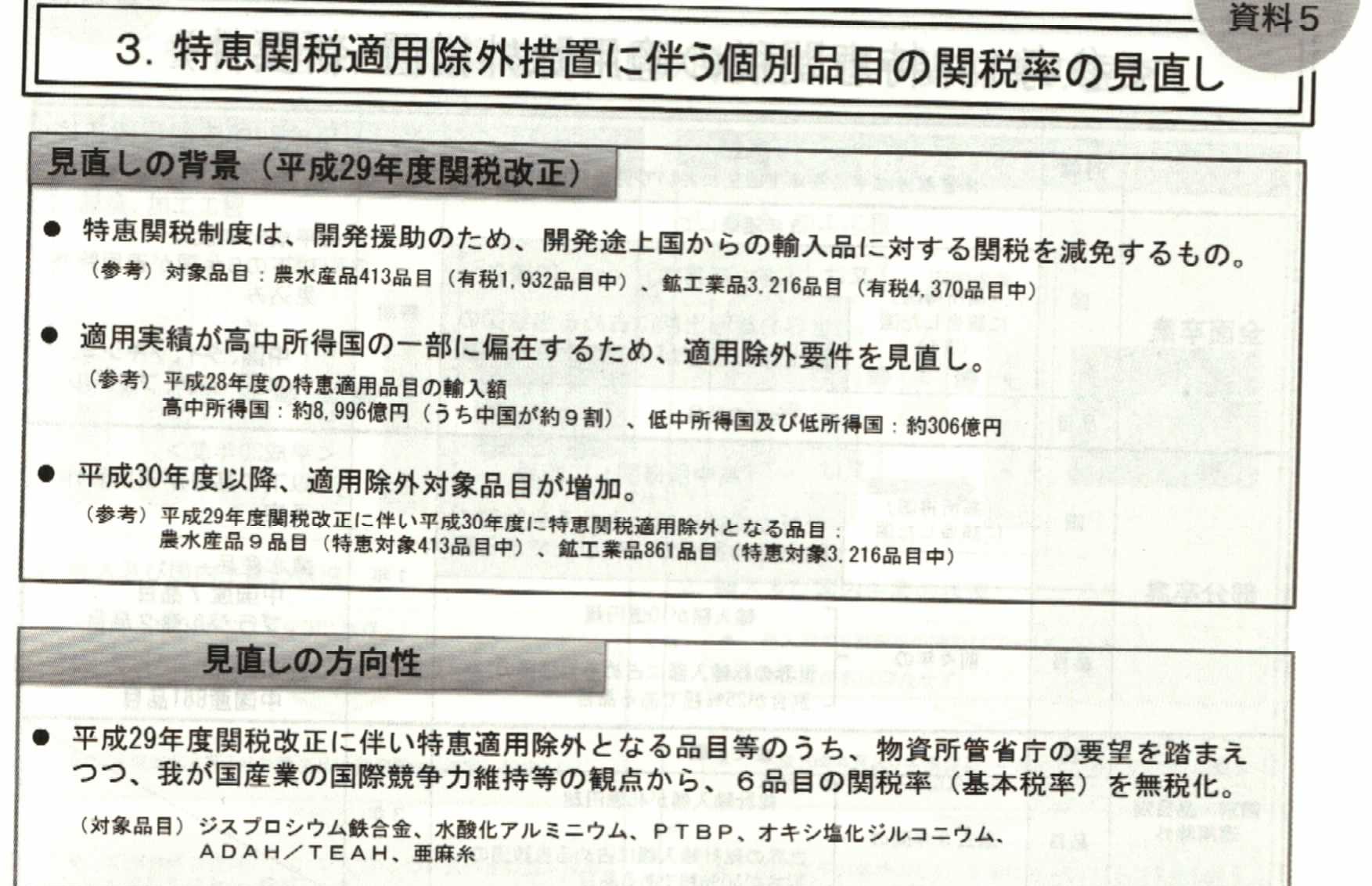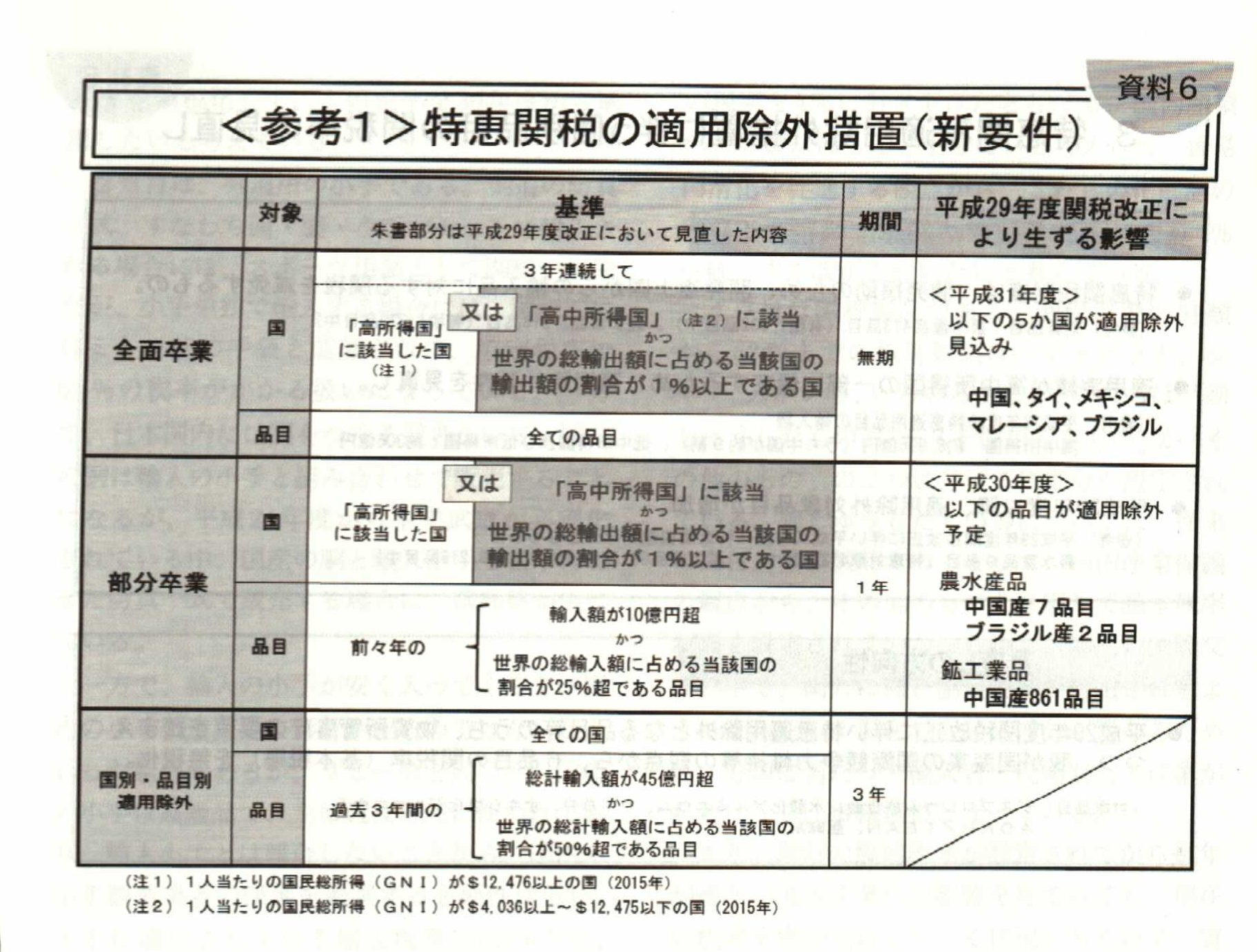■加盟国
インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、日本、オーストラリア、
ニュージーランド、ブルネイ
RCEP協定文一覧
原産地規則
原産地規則の検索
品目別規則
日本側ステージング表
他国側ステージング表一覧
「自己申告制度」利用の手引き(明細書、関係書類の事例が豊富)
地域的な包括的経済連携協定 概要 令和3年12月財務省関税局経済連携室
出典:RCEP物品貿易について~原産地規則中心に~
RCEP協定原産地規則について
RCEP協定に係る業務説明会Q&A