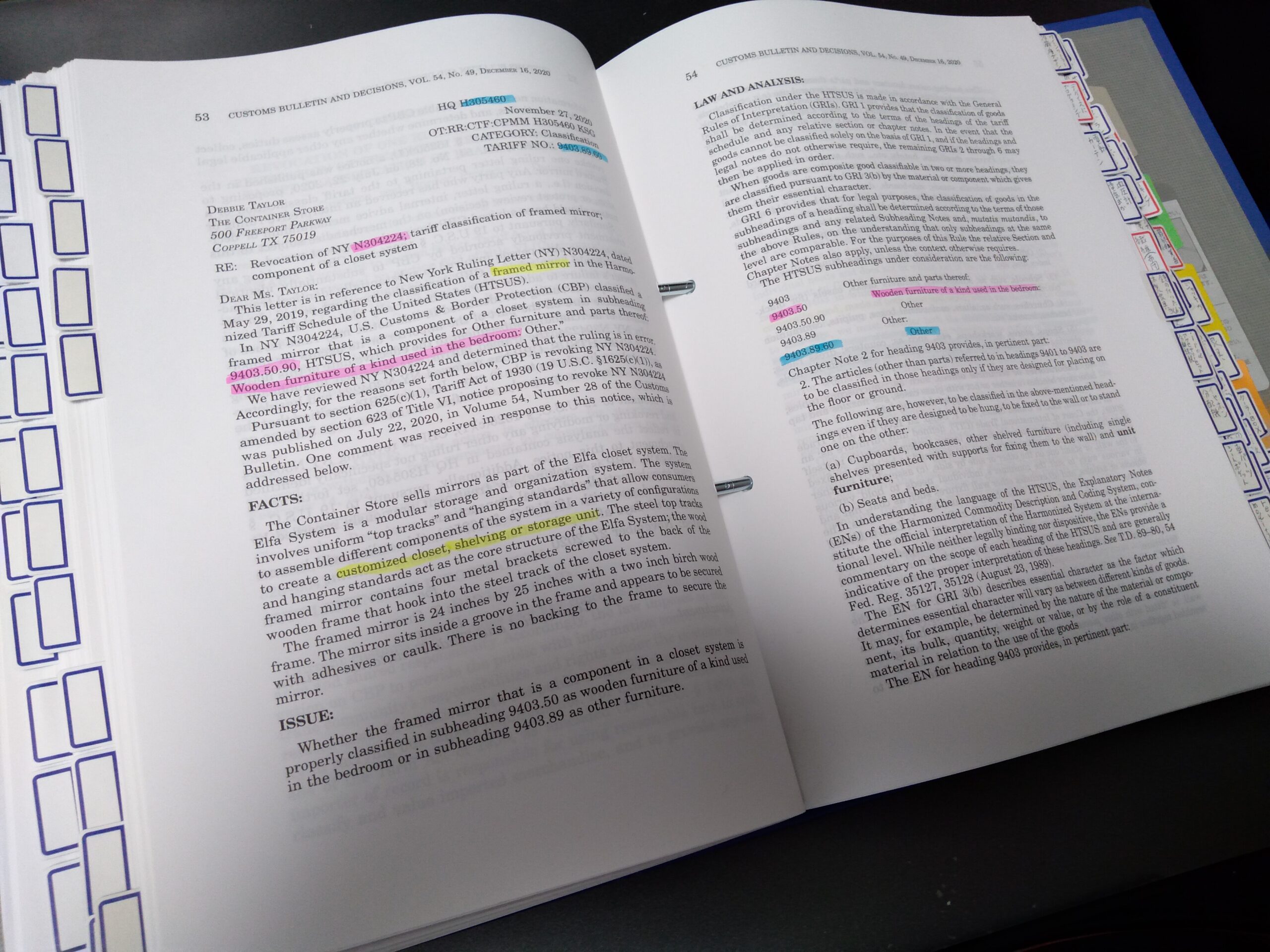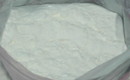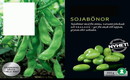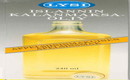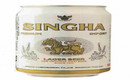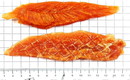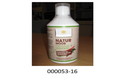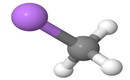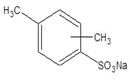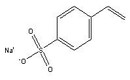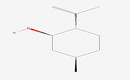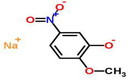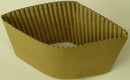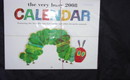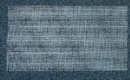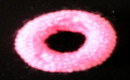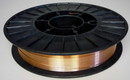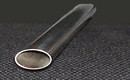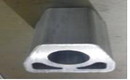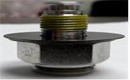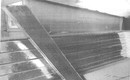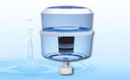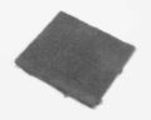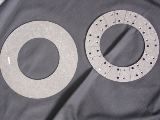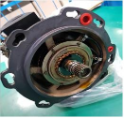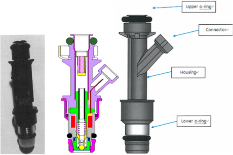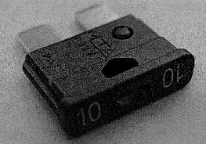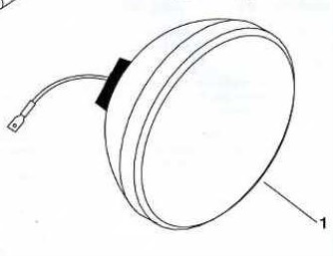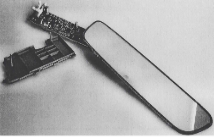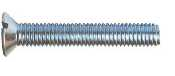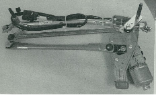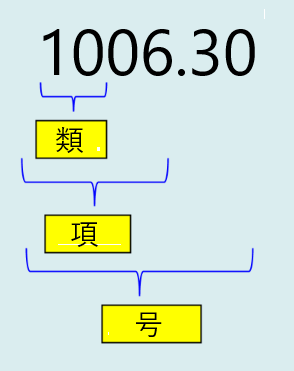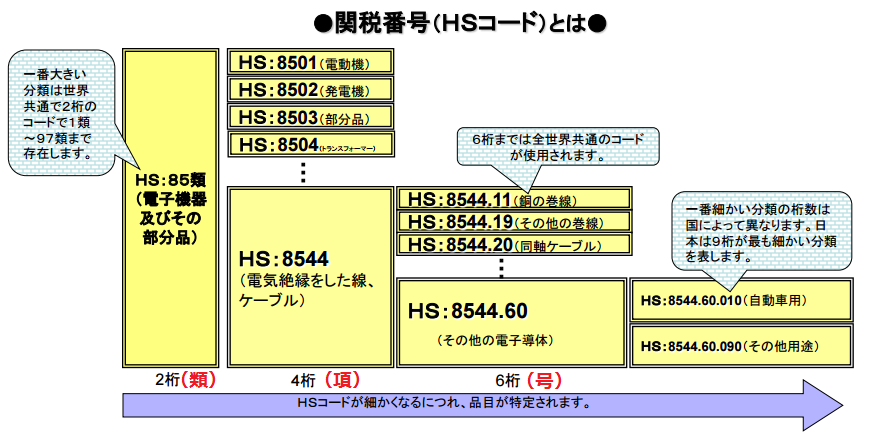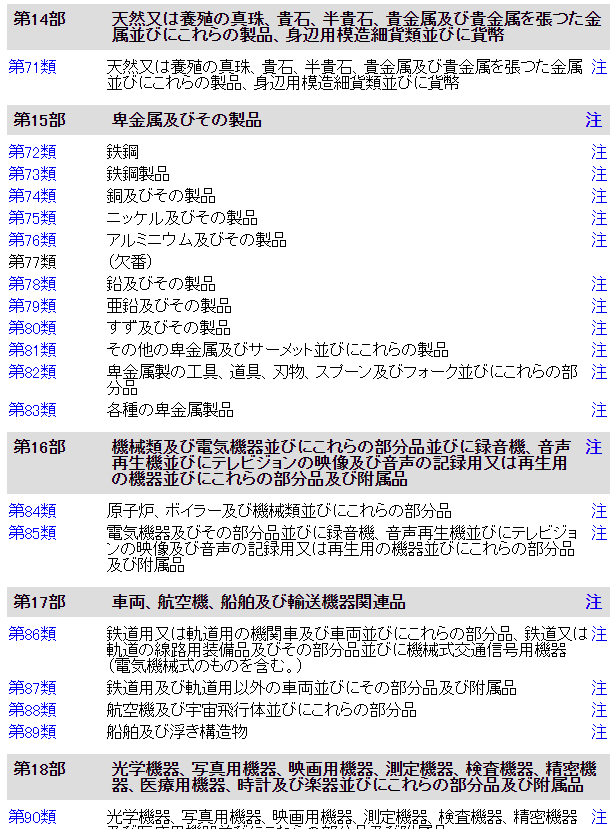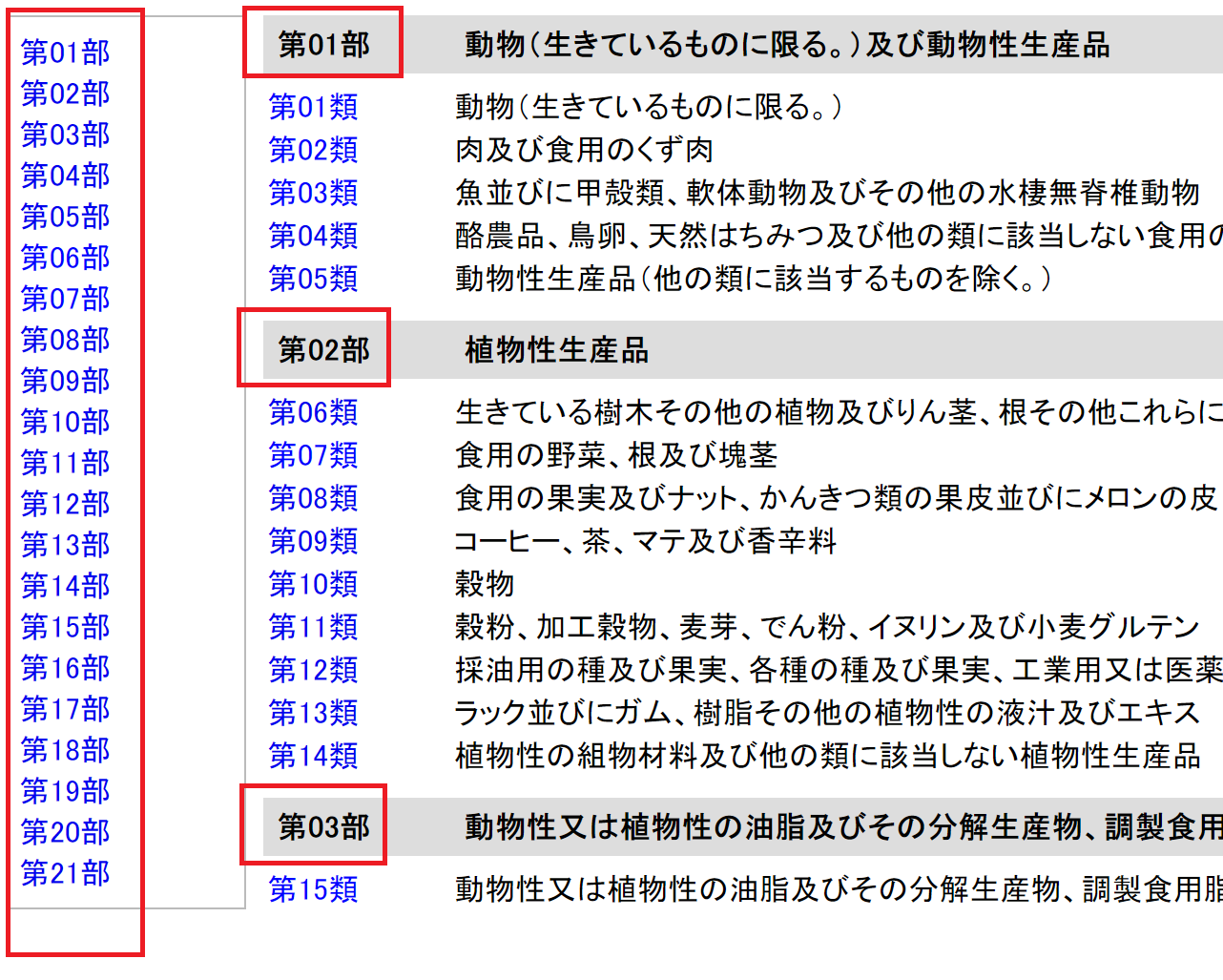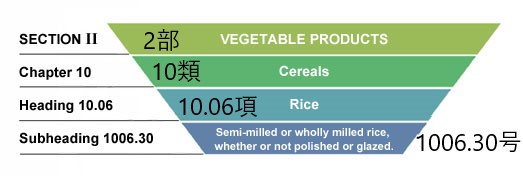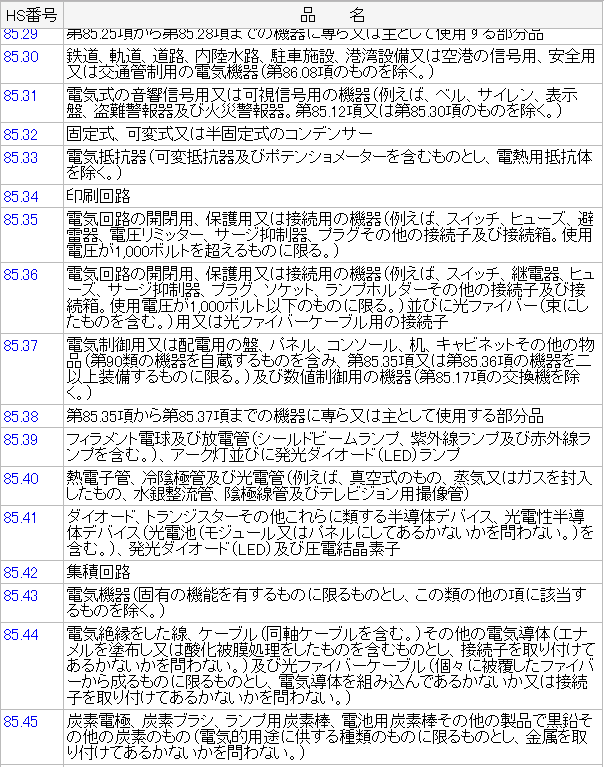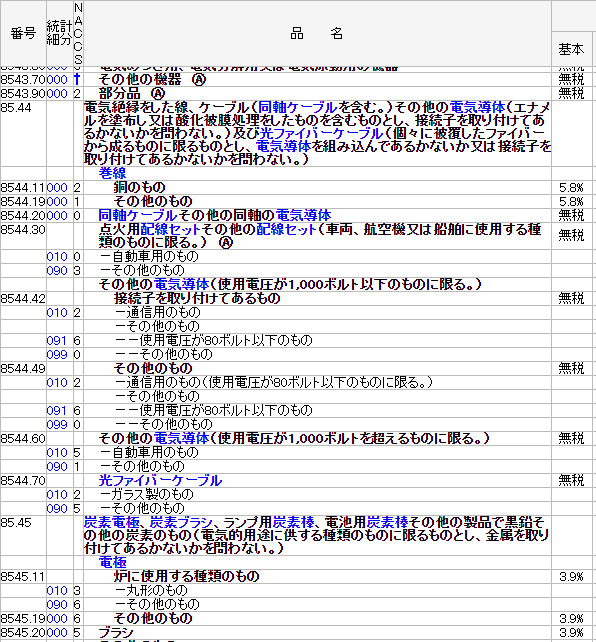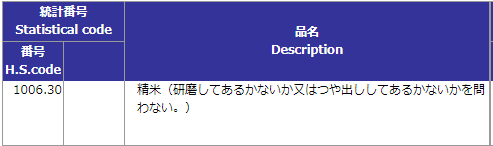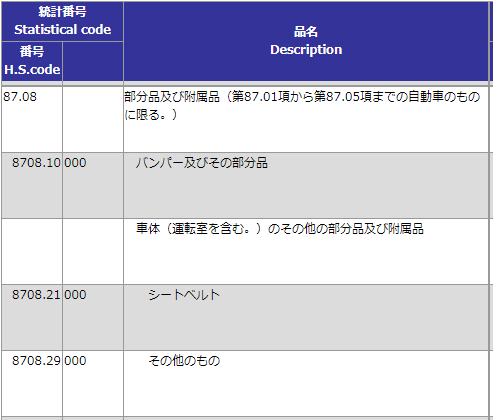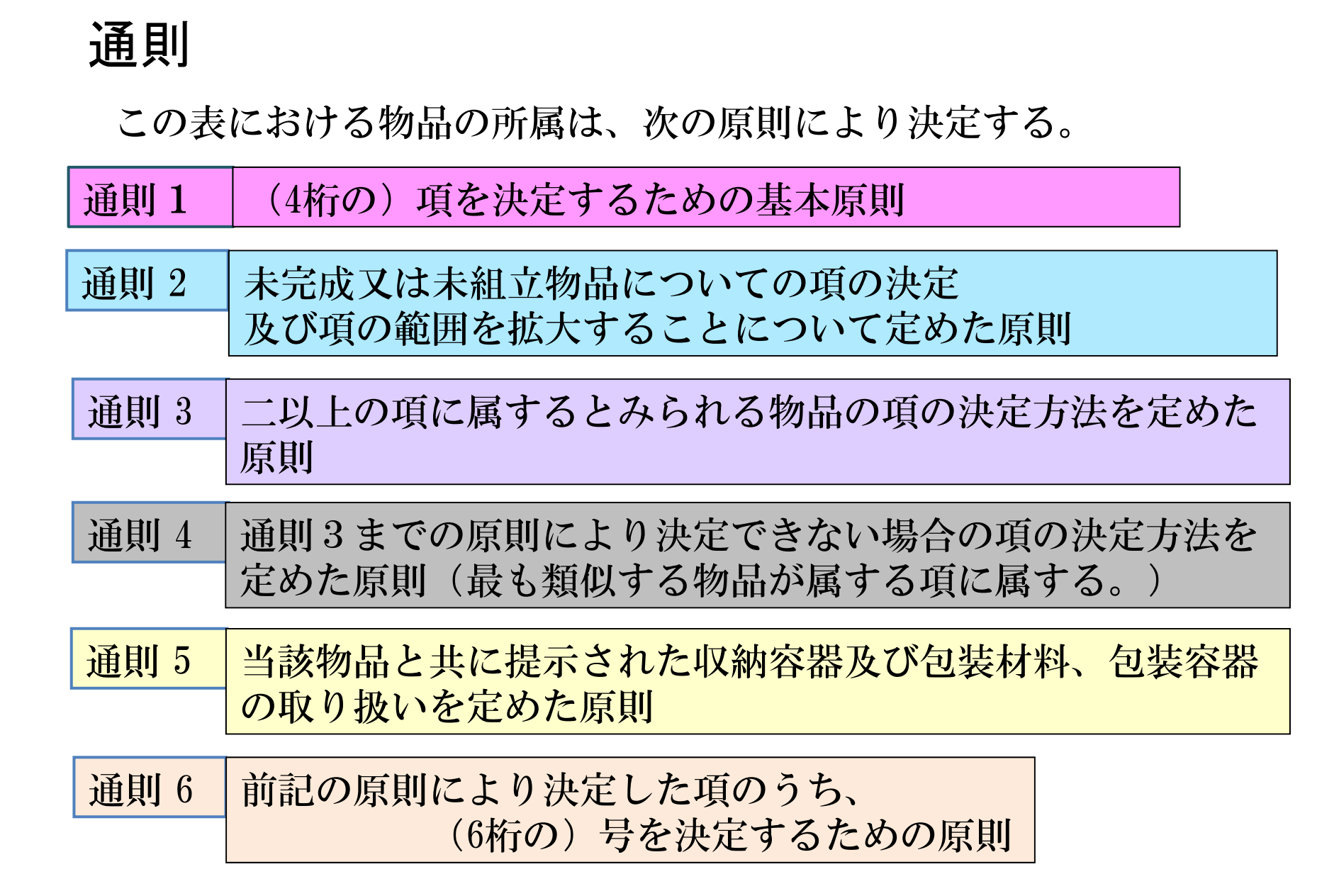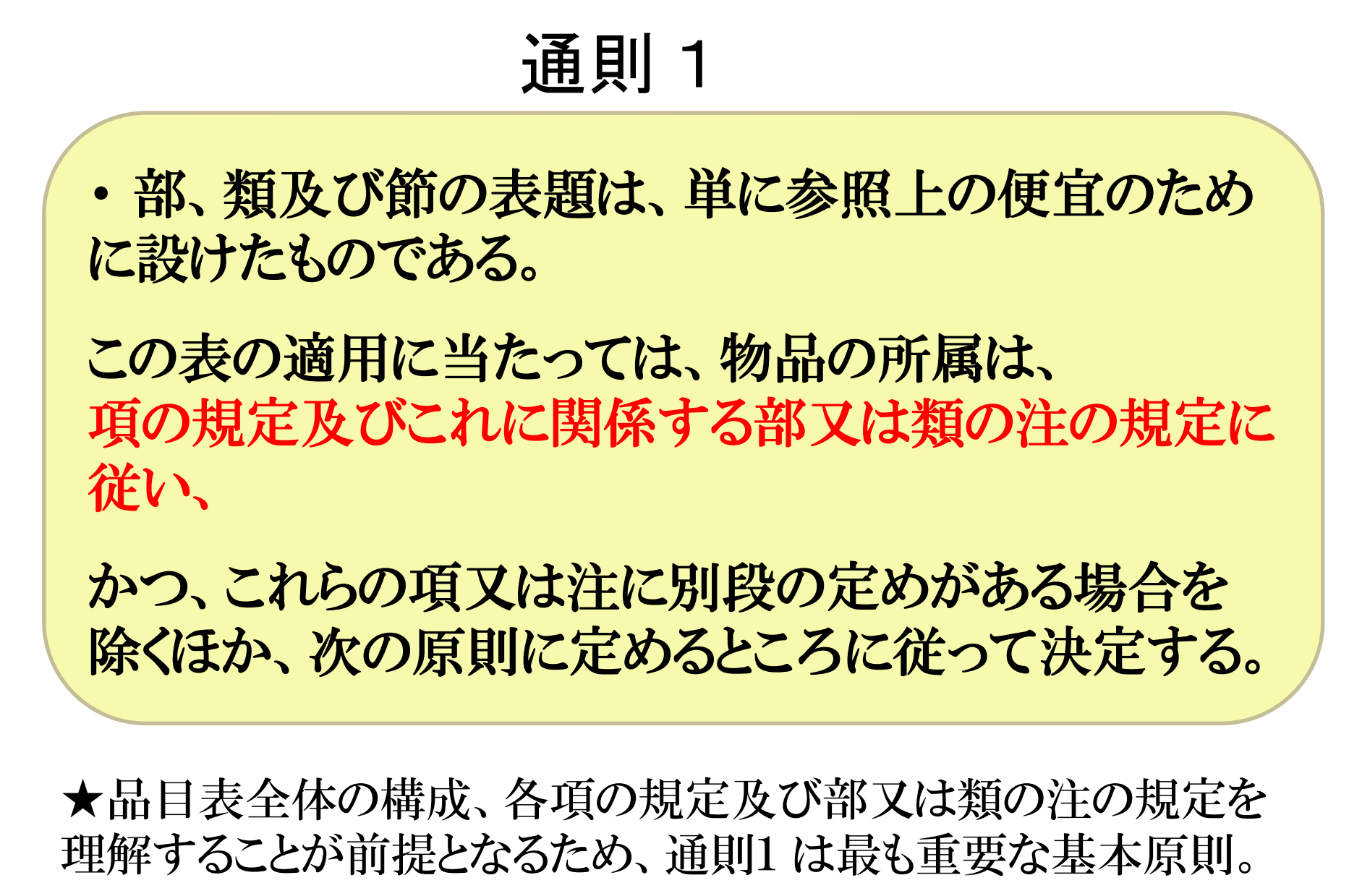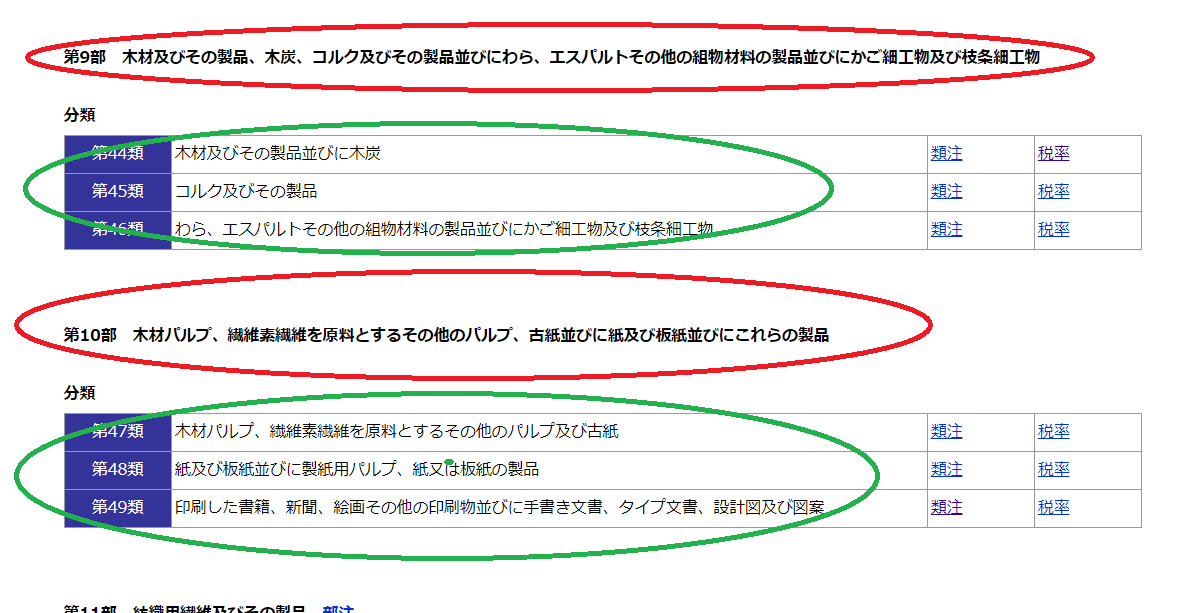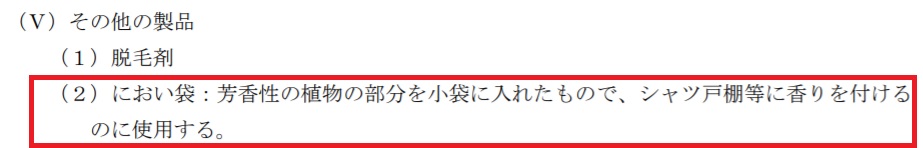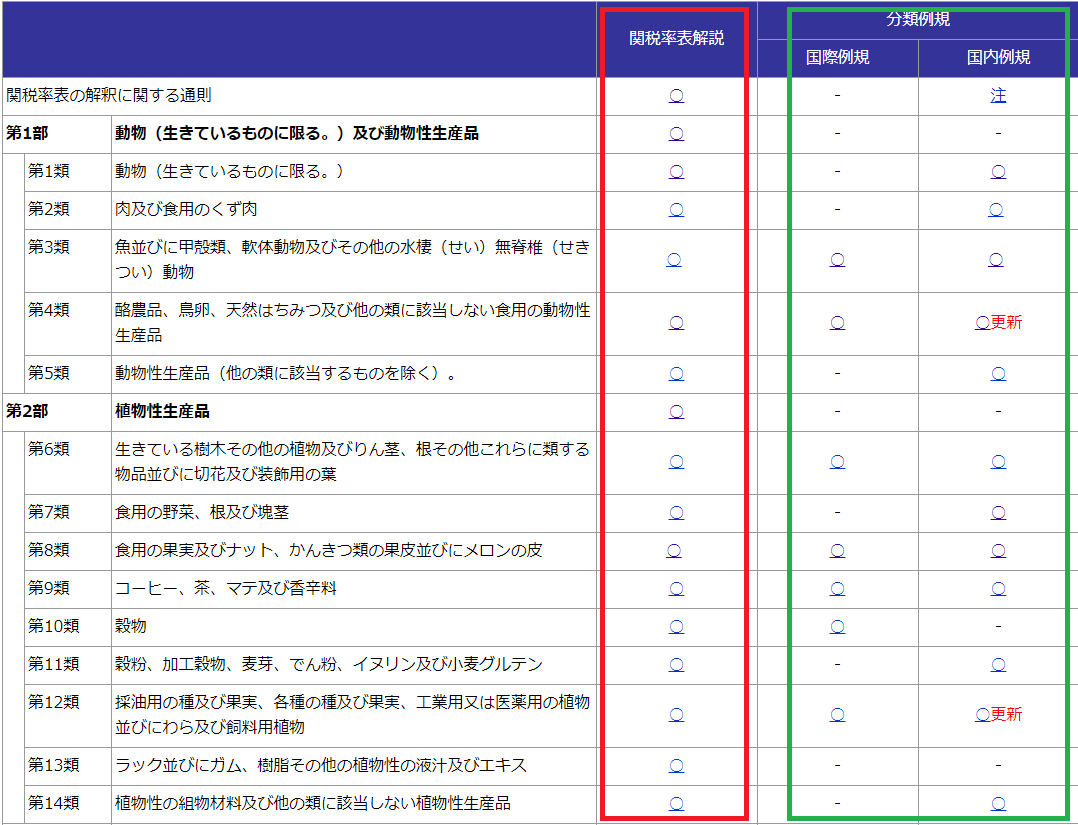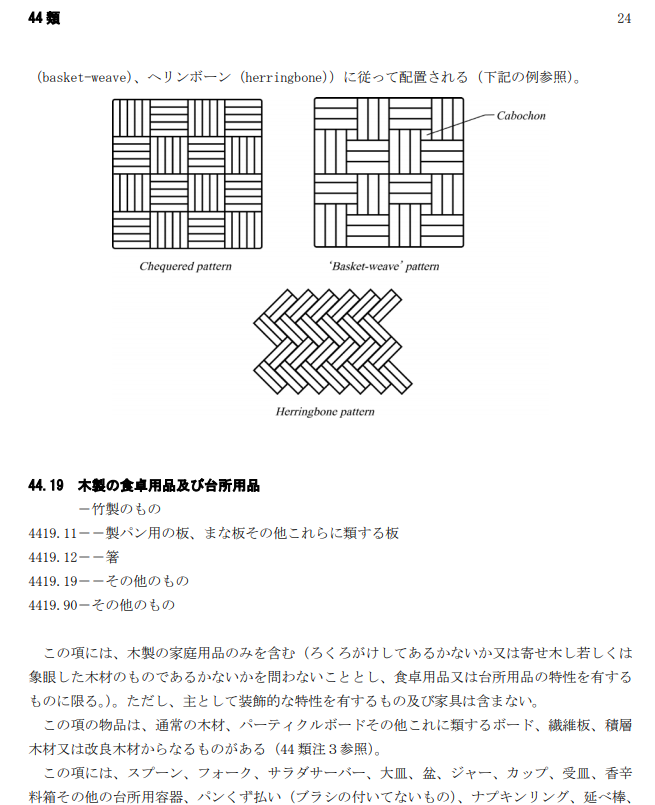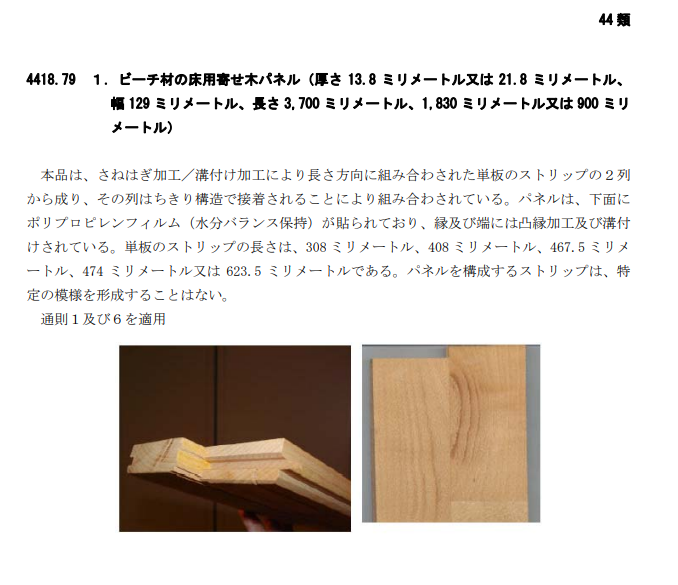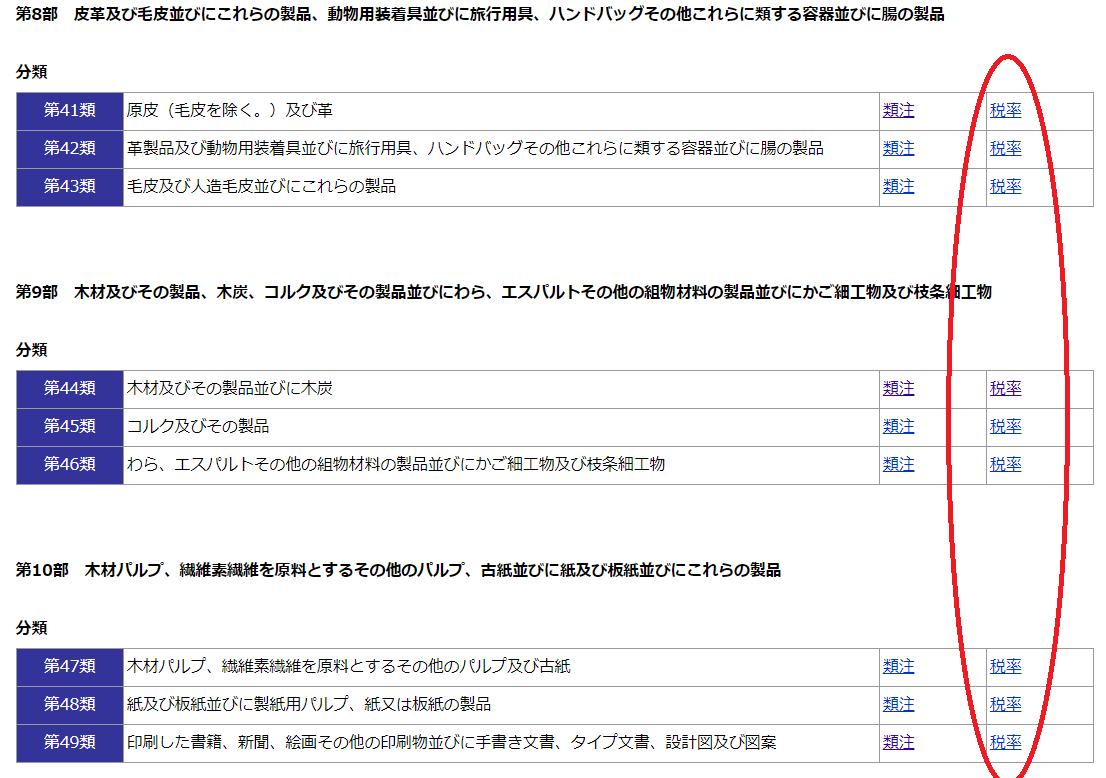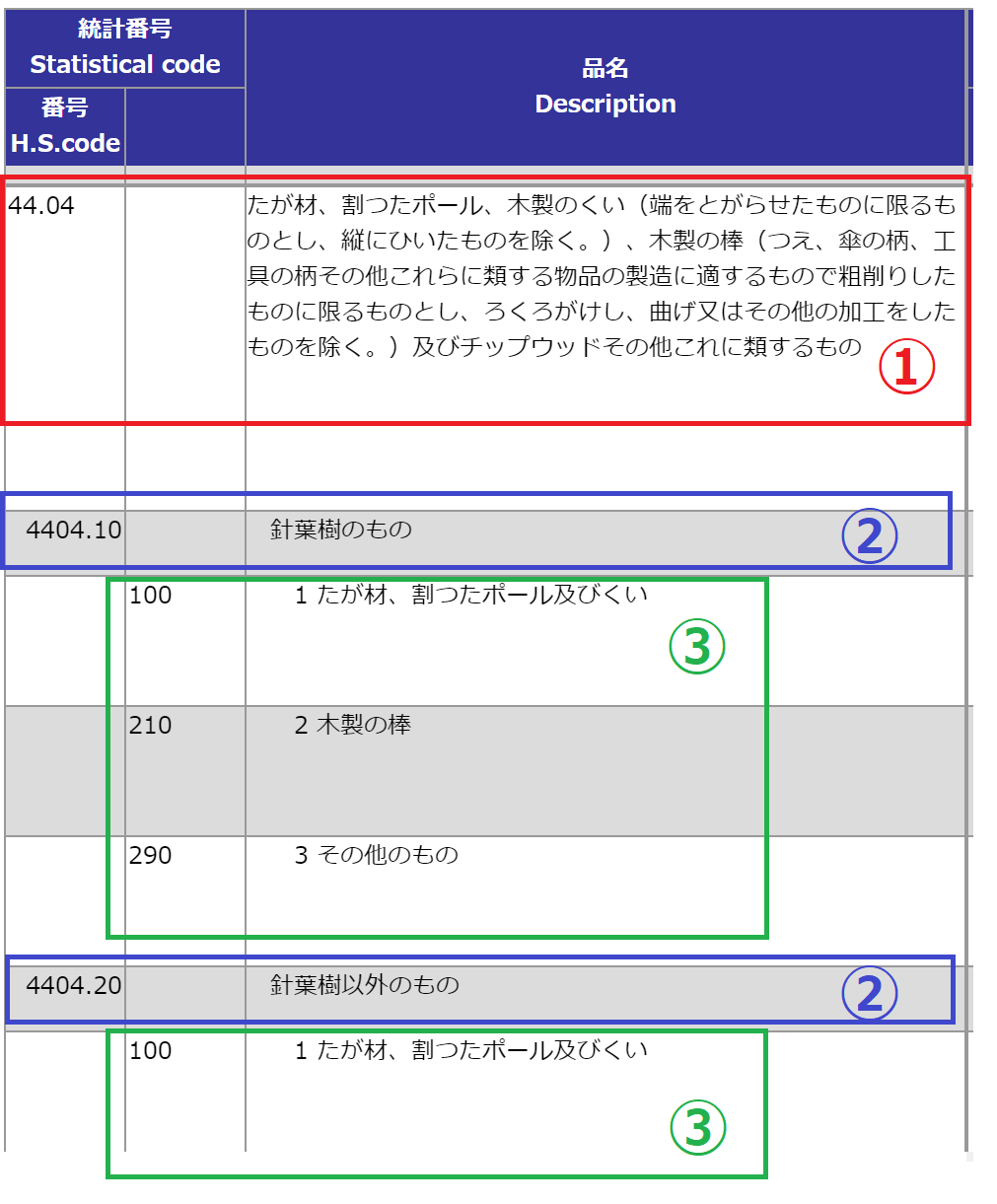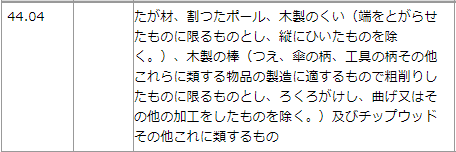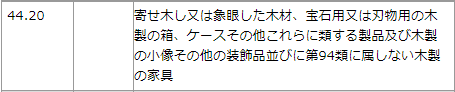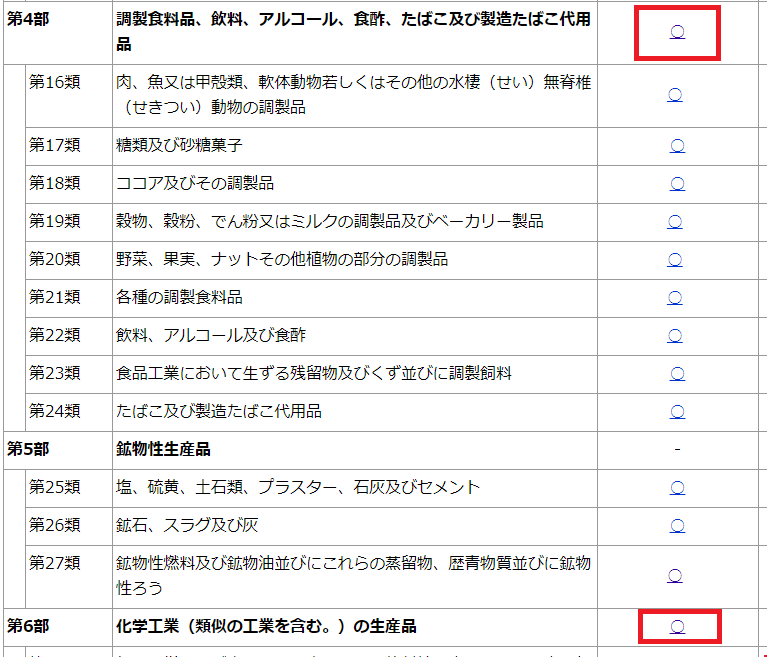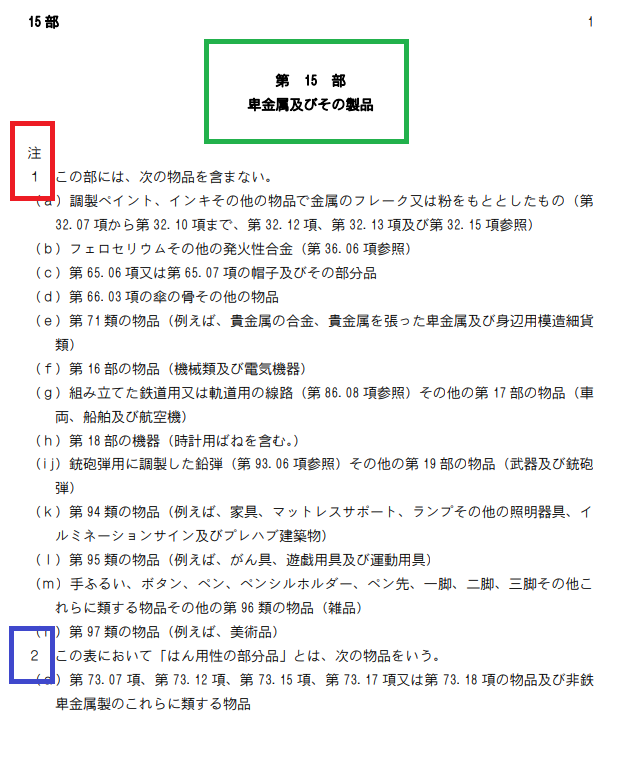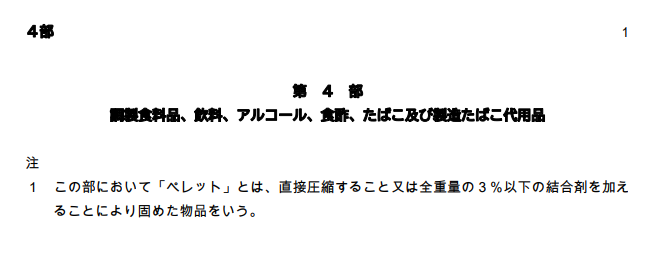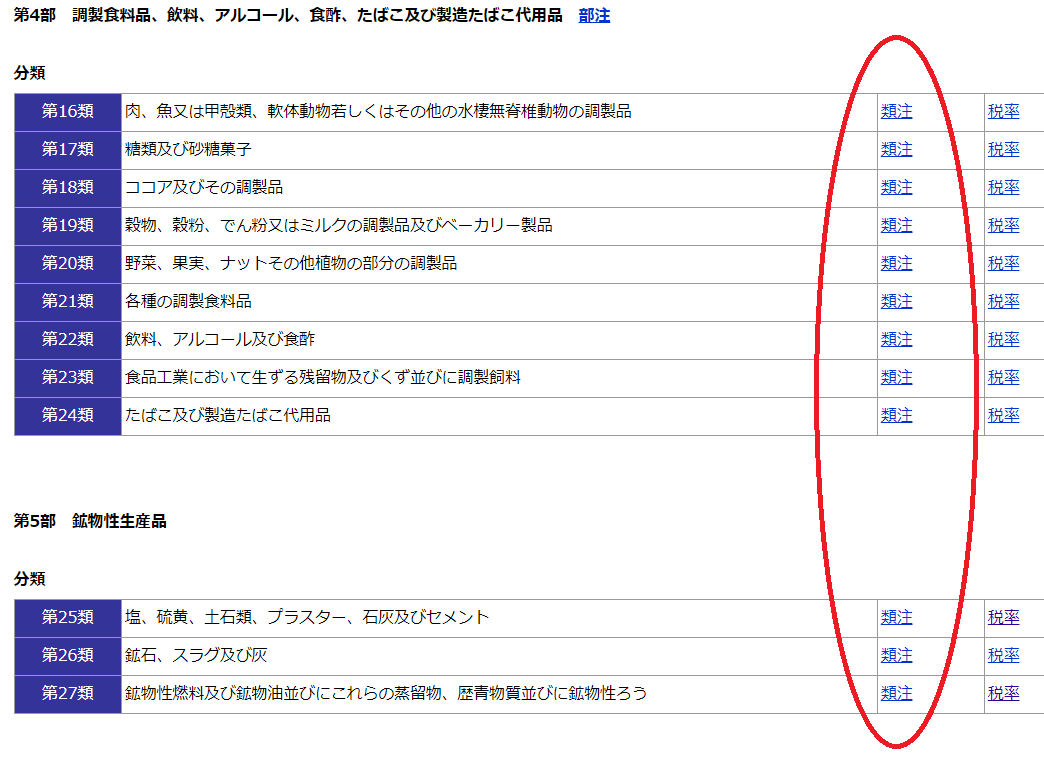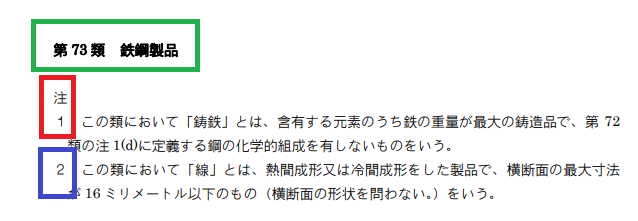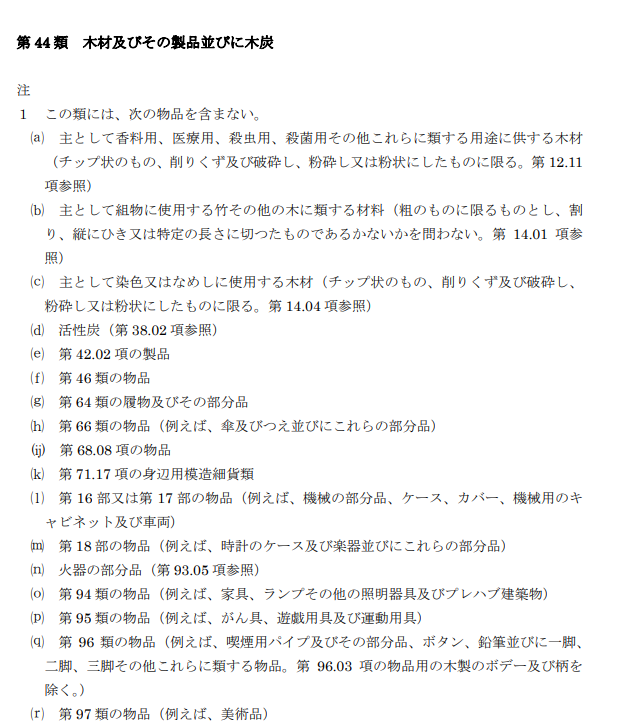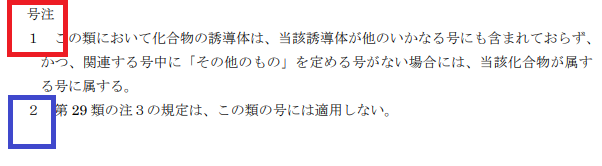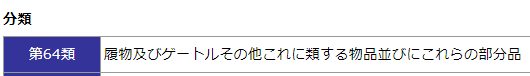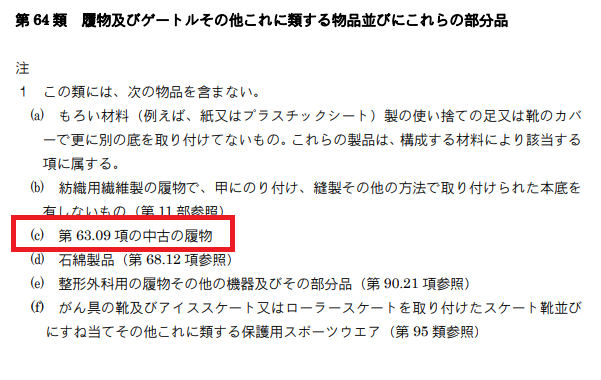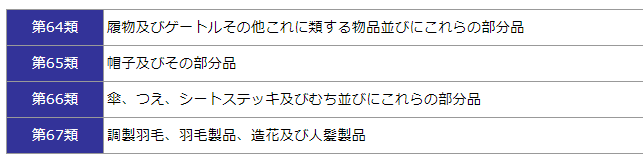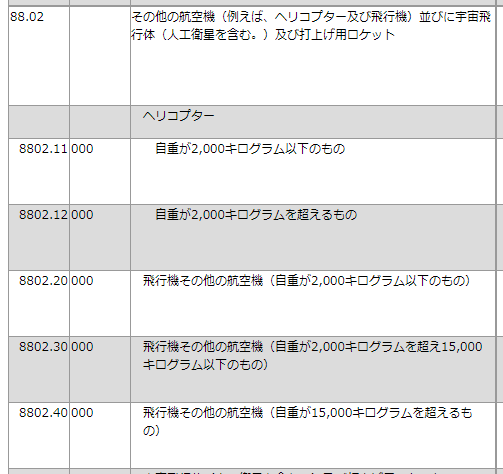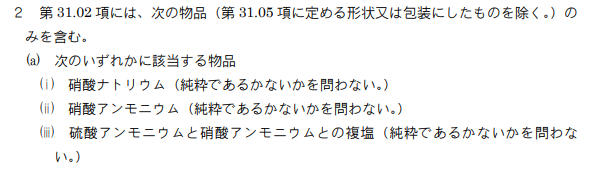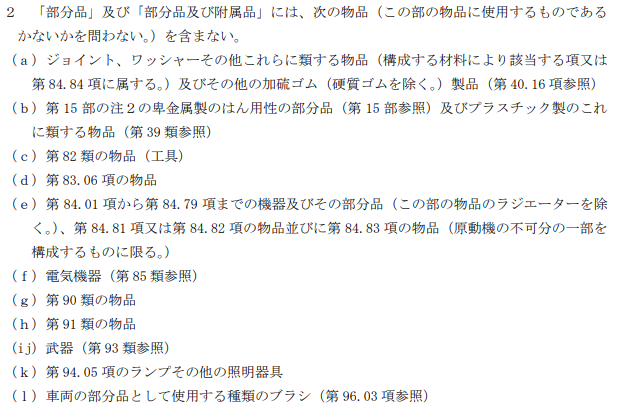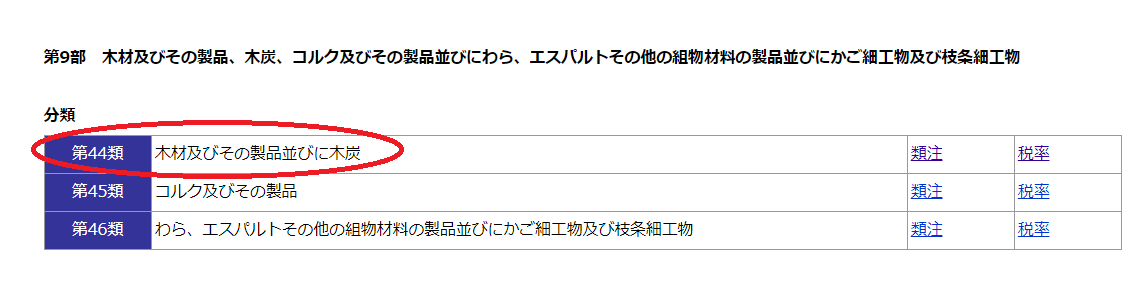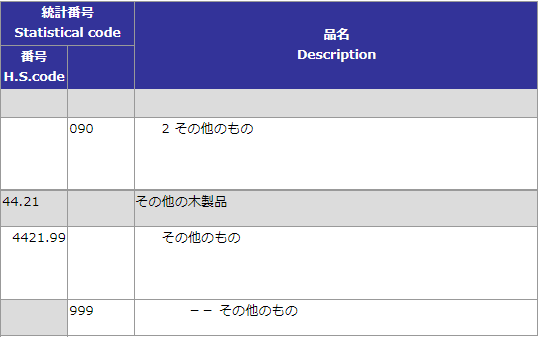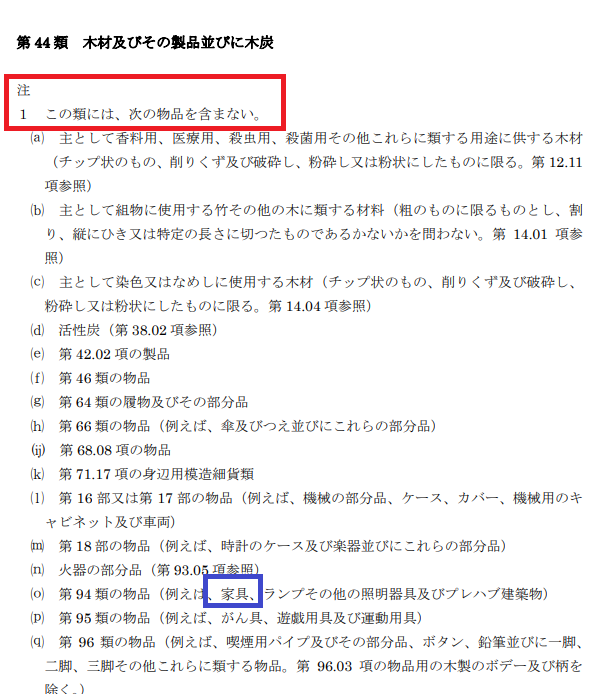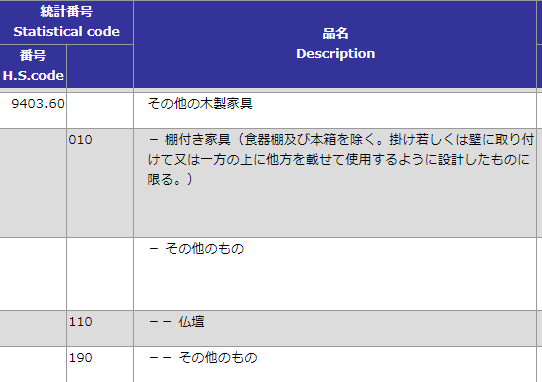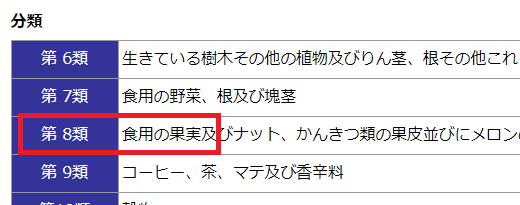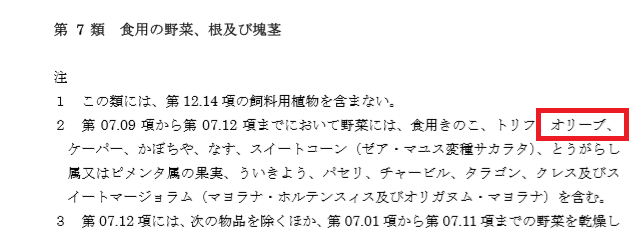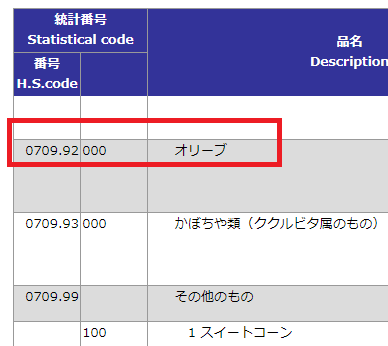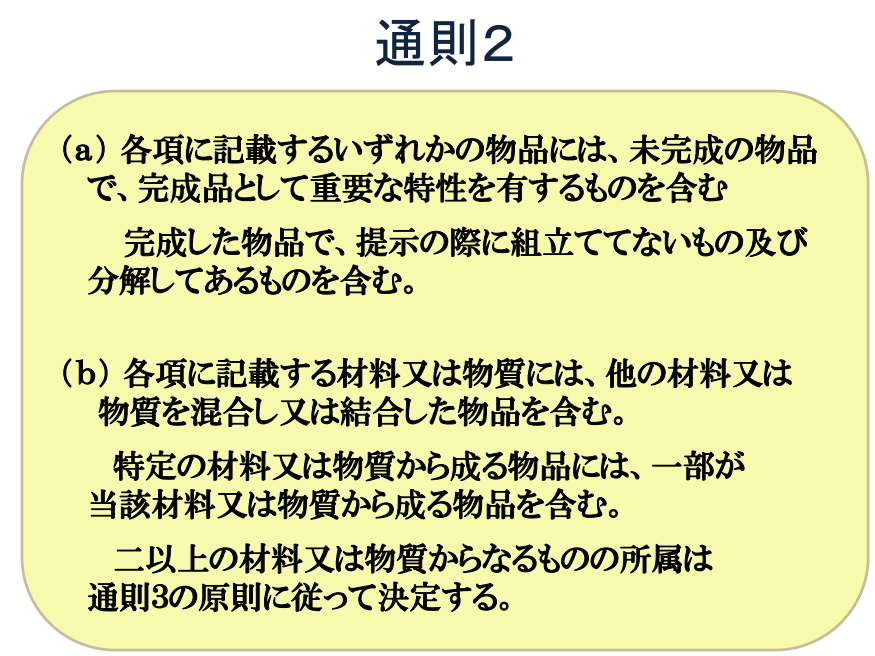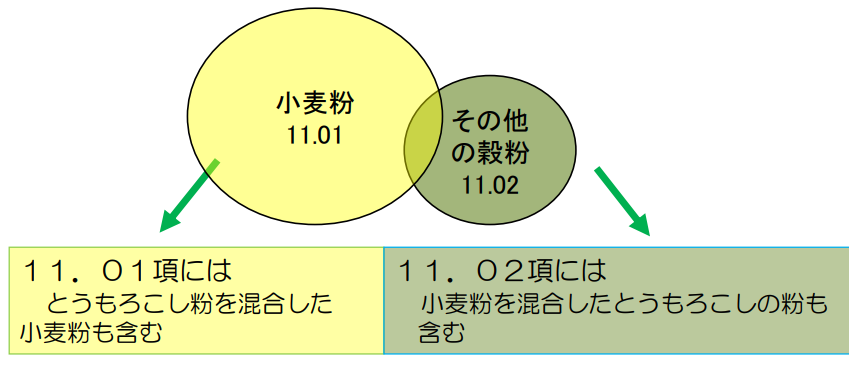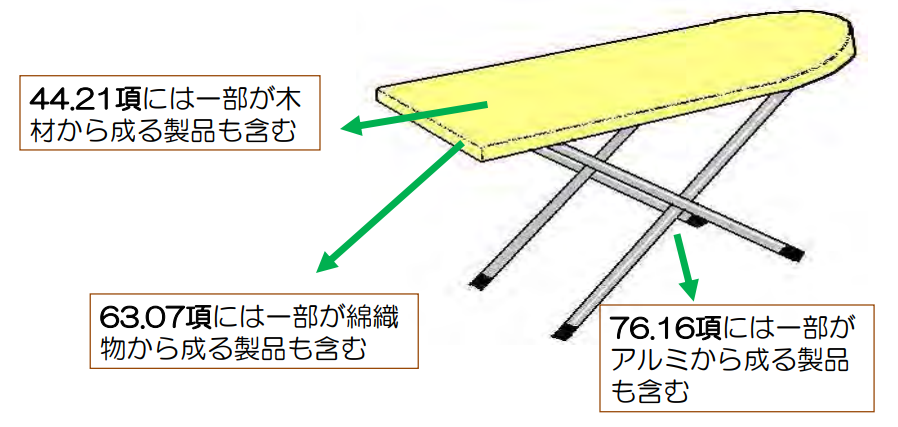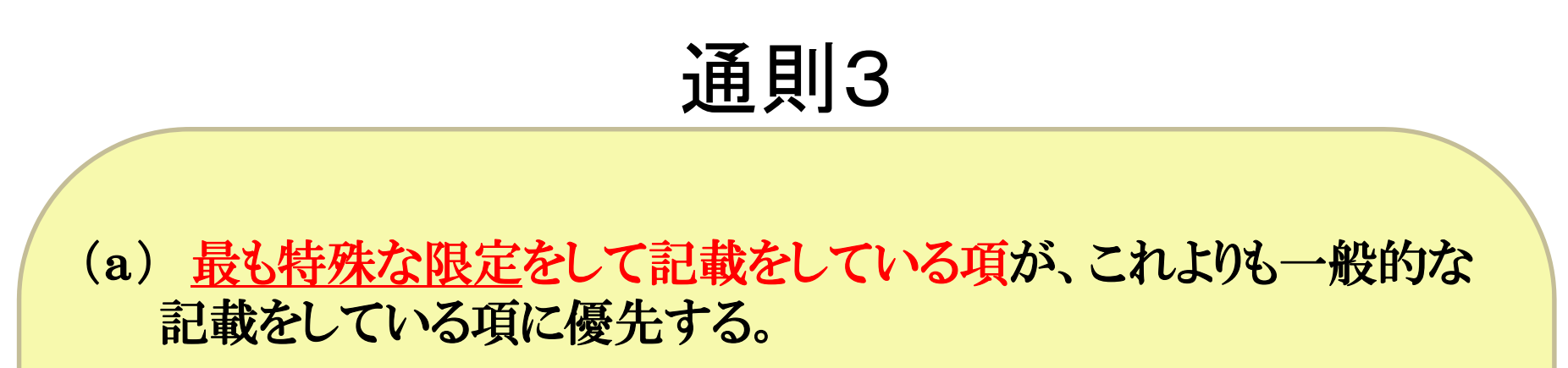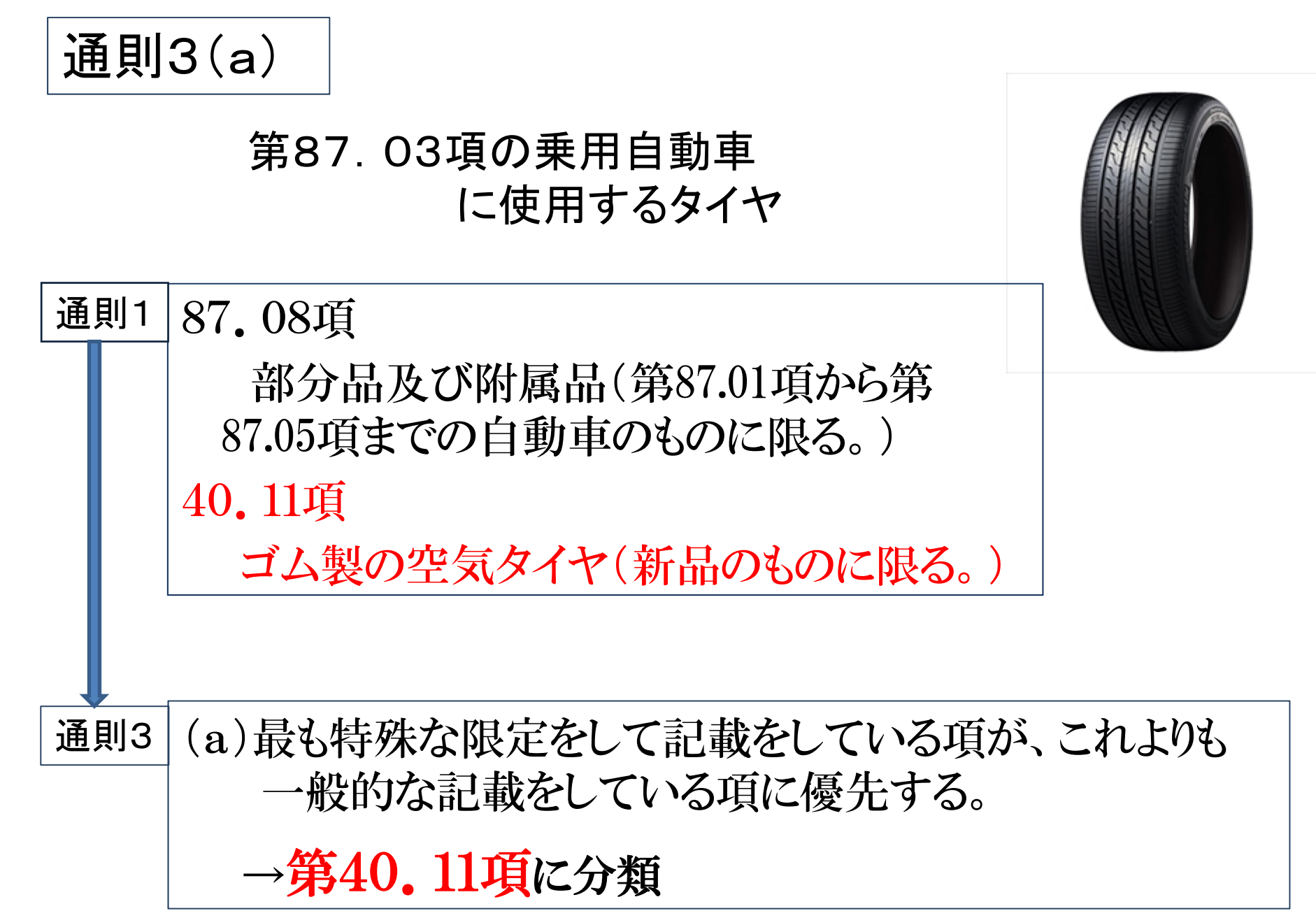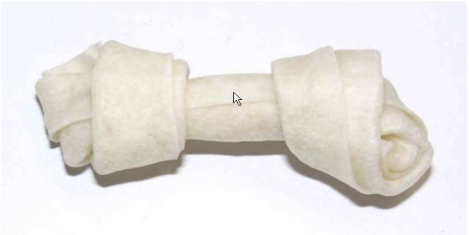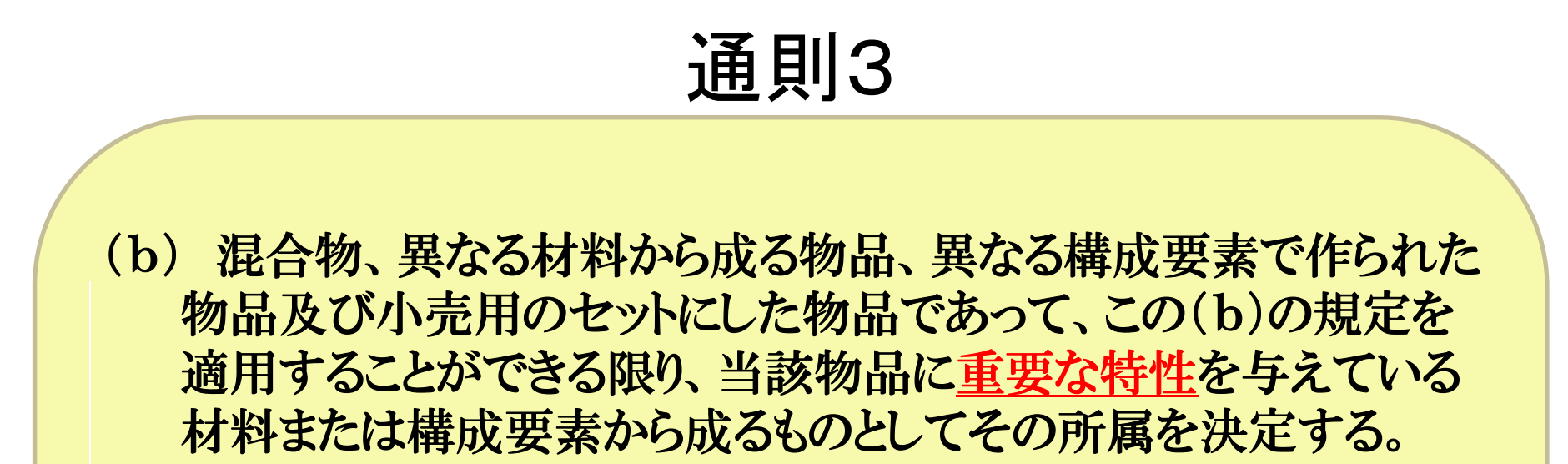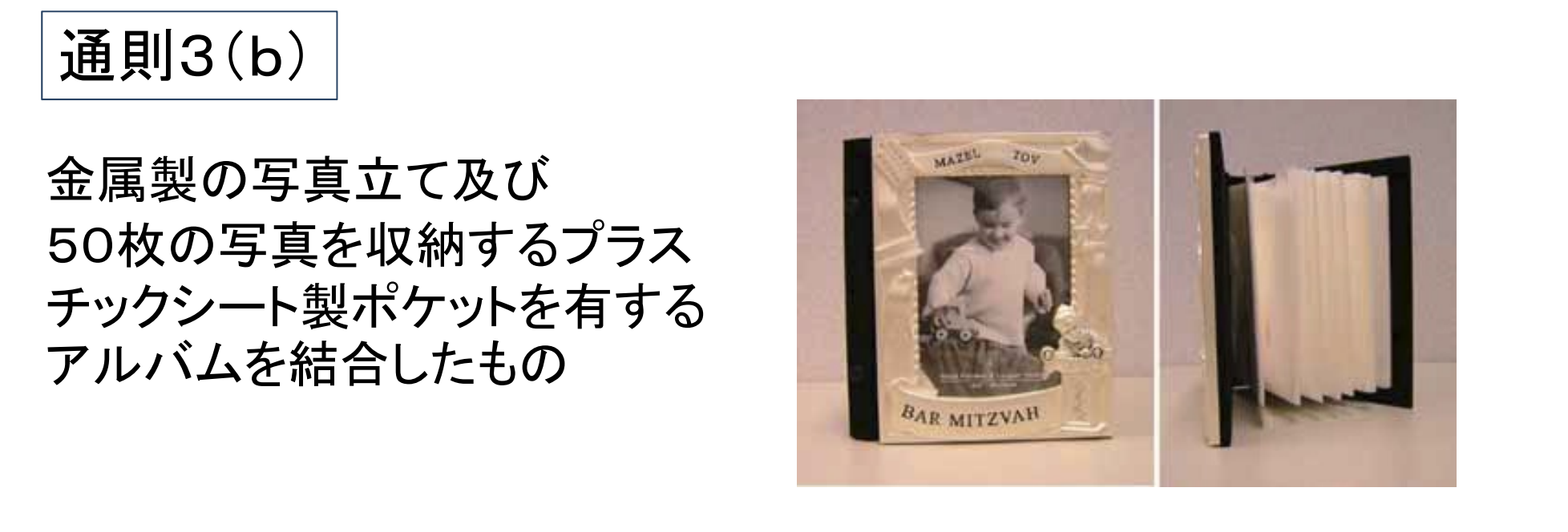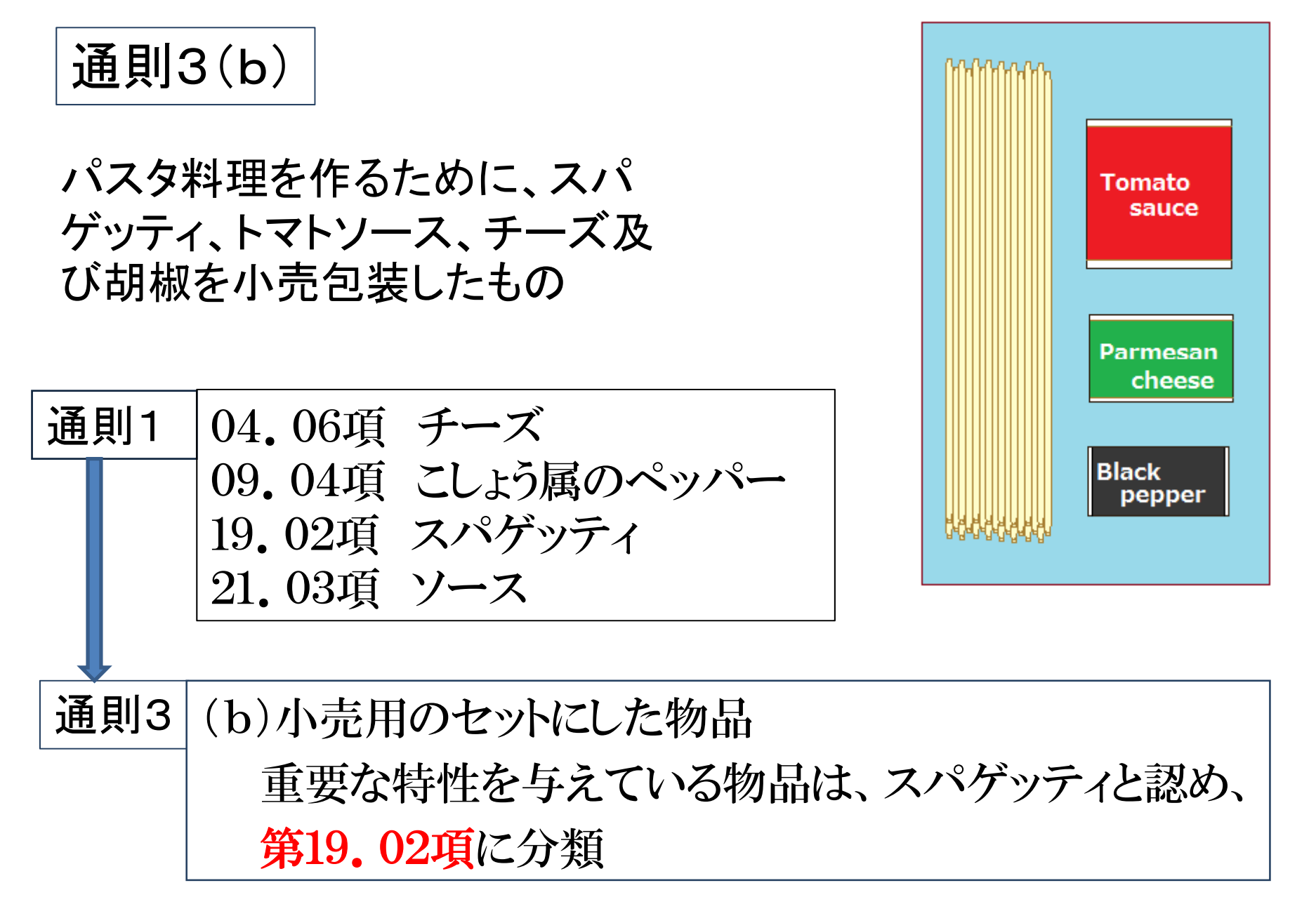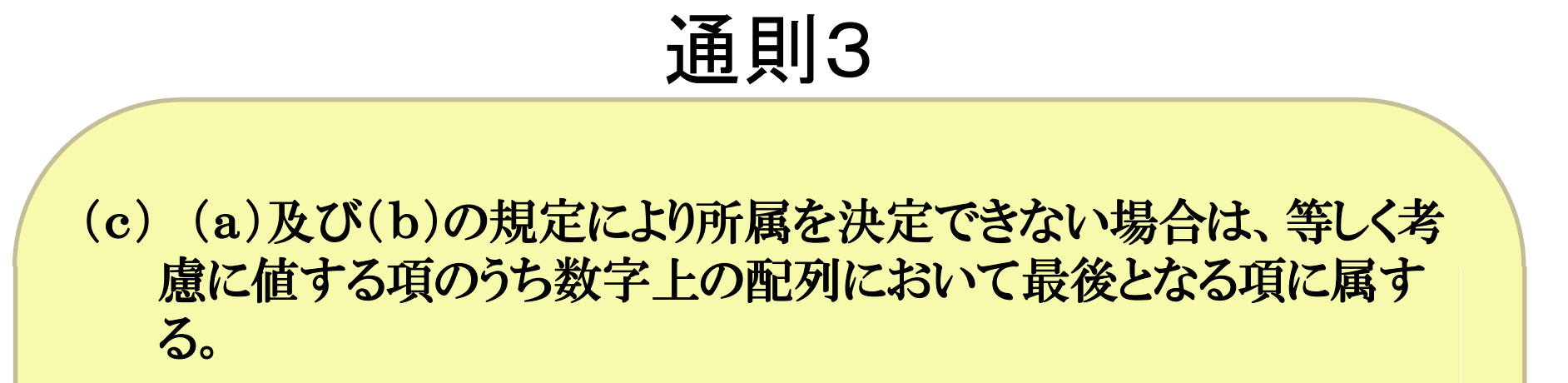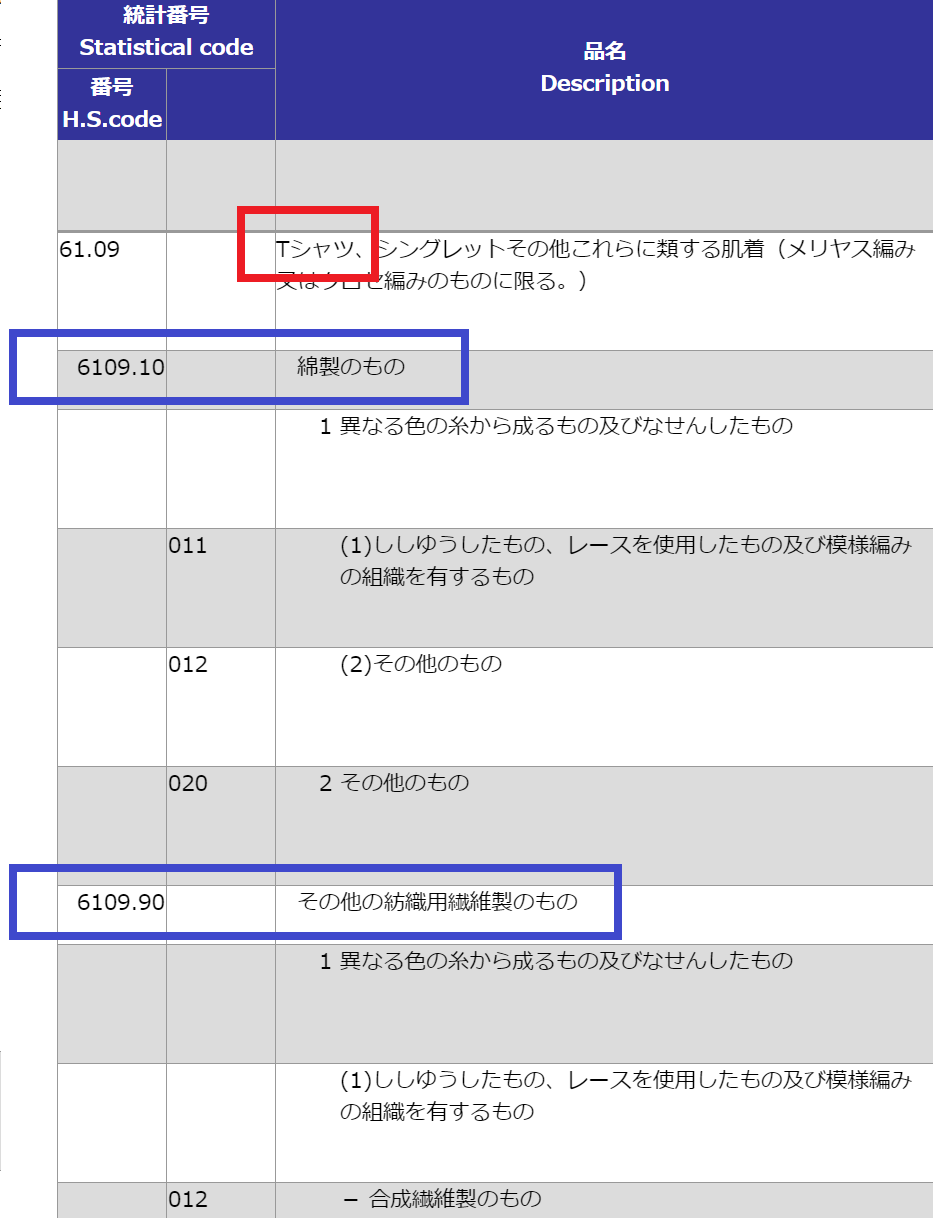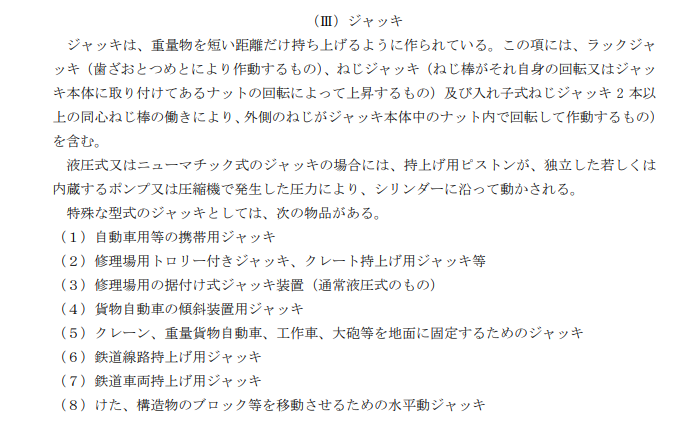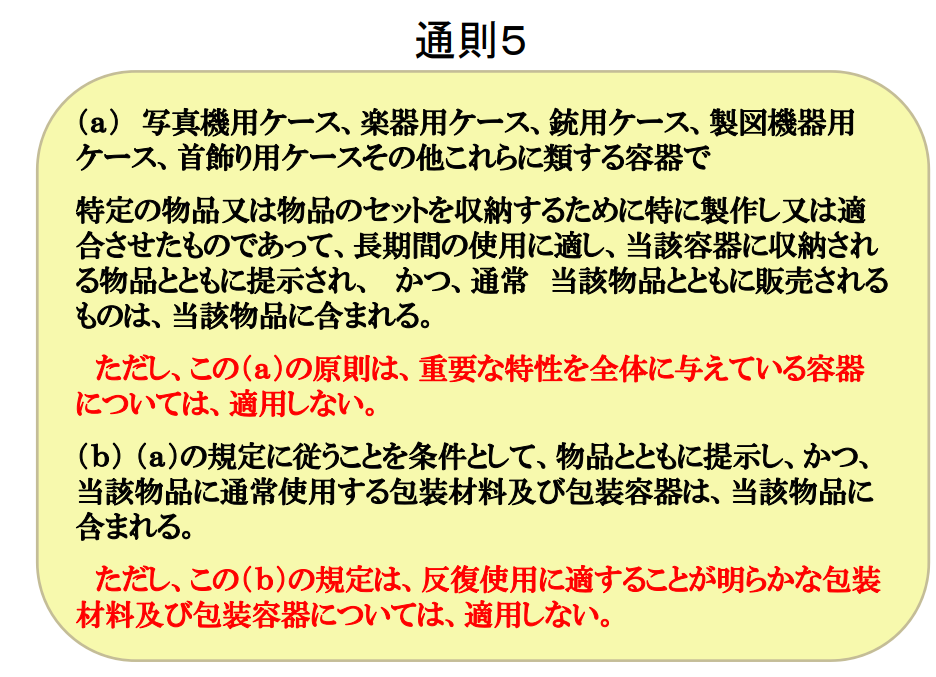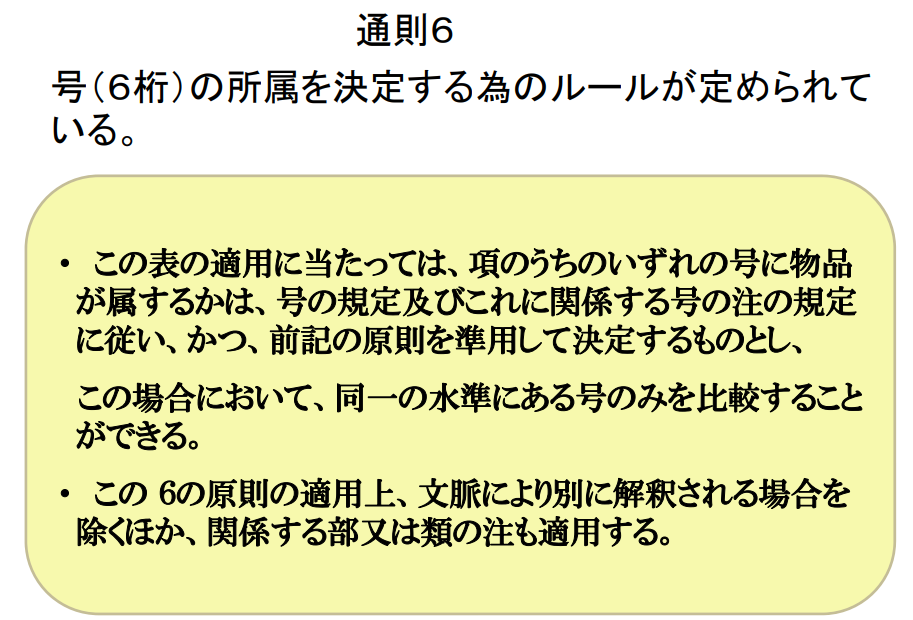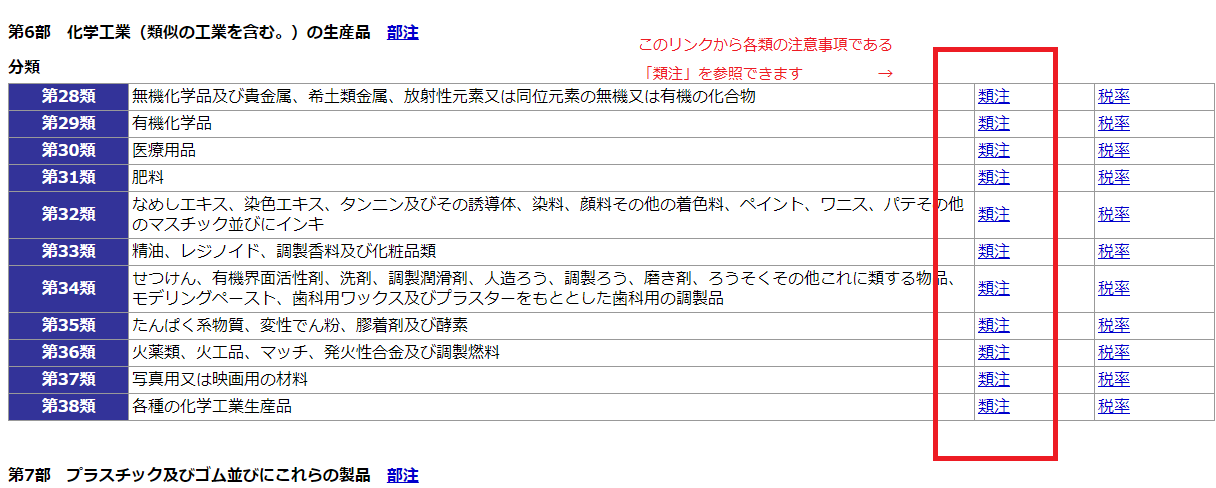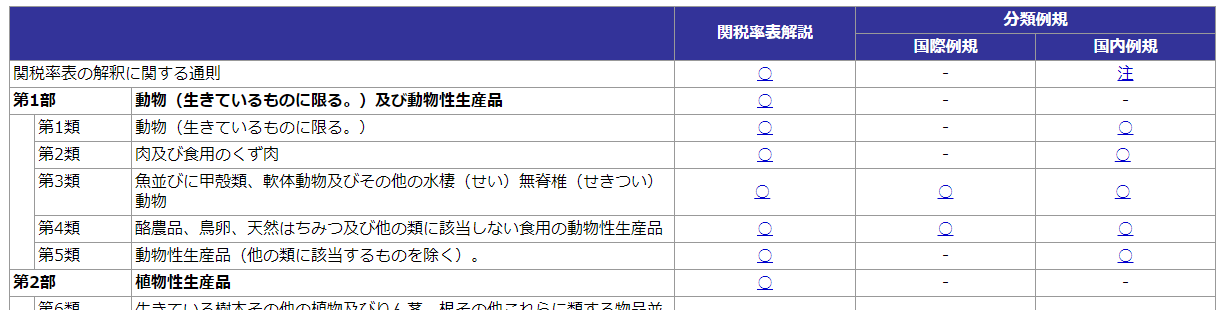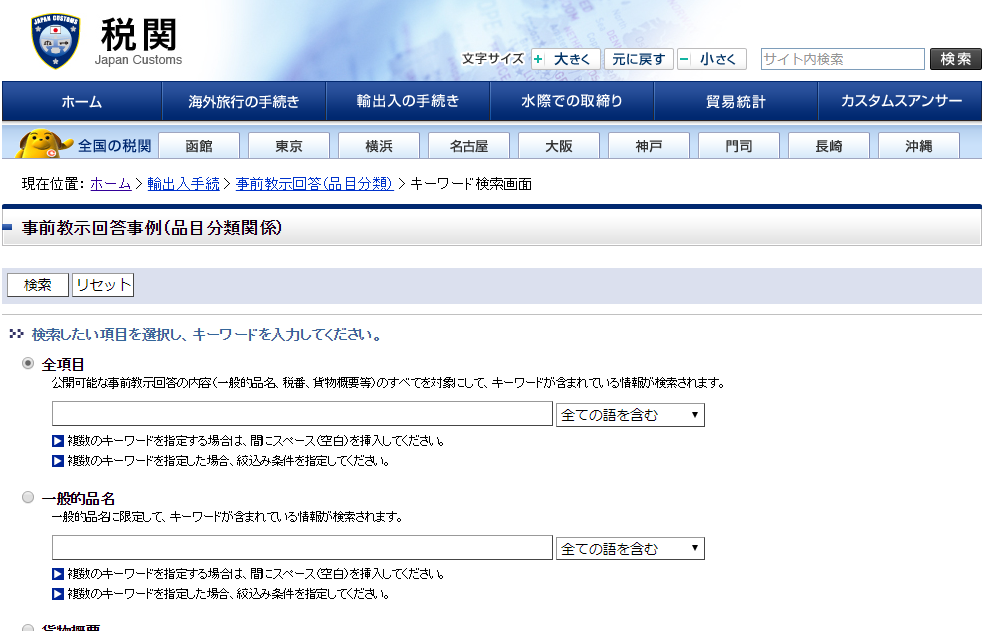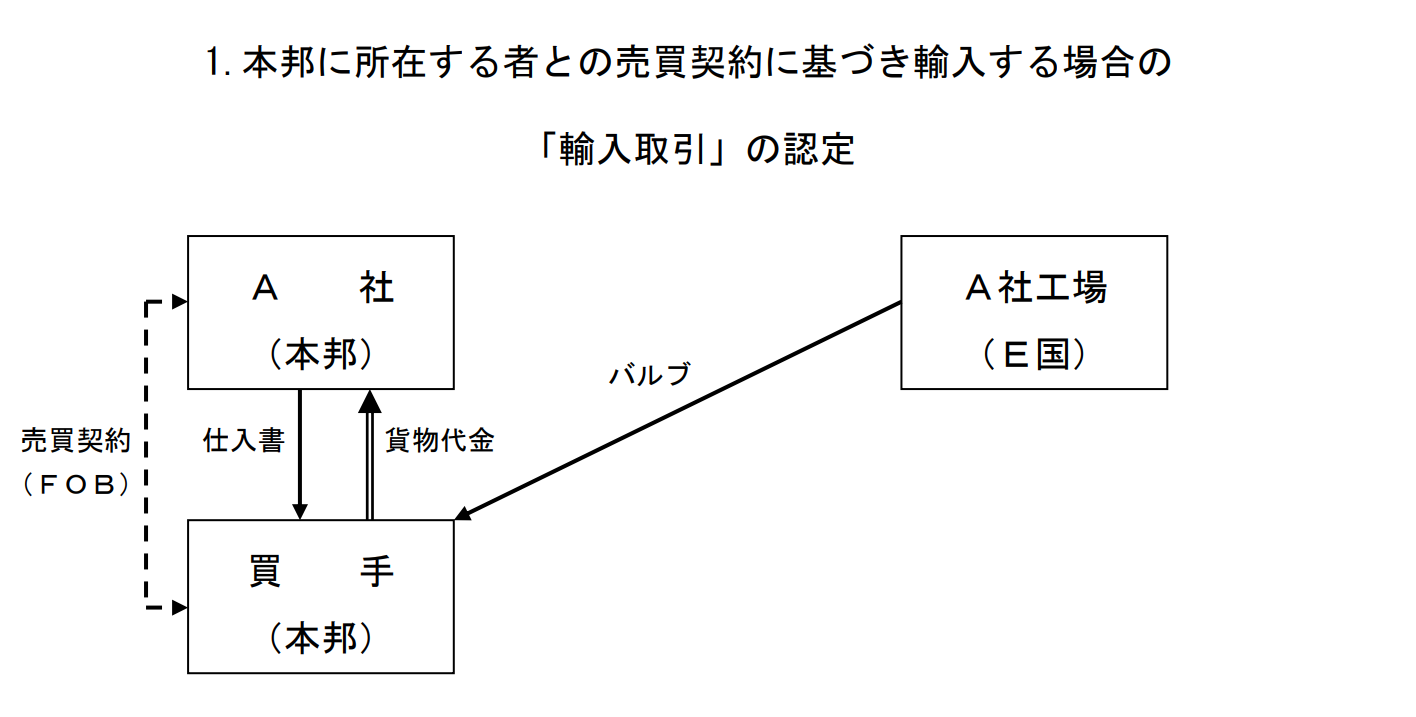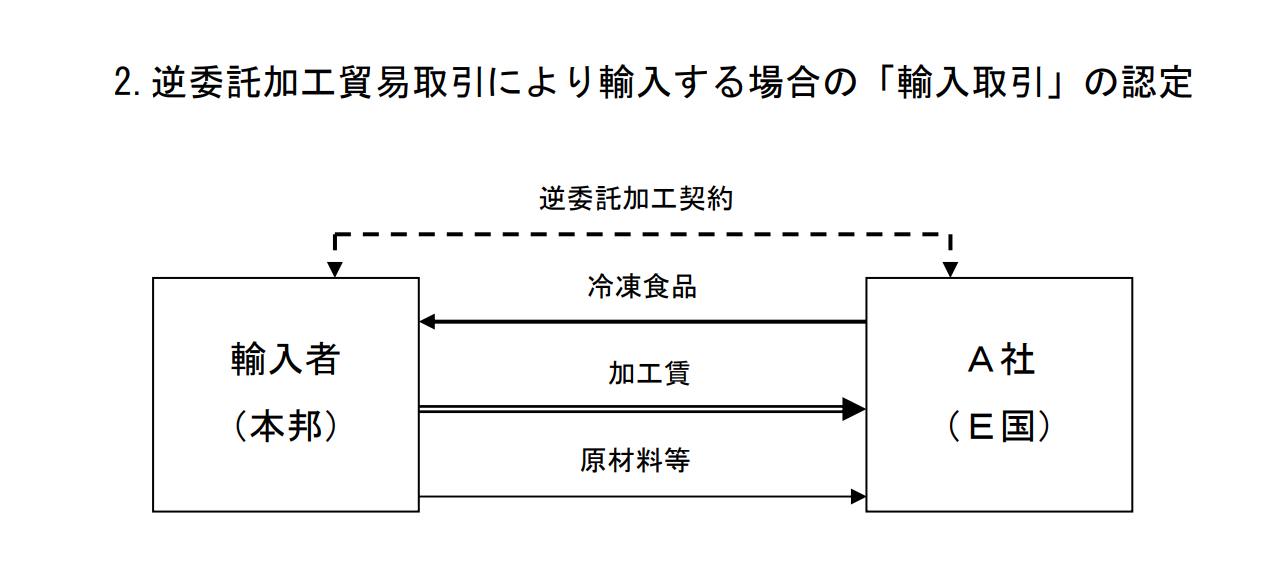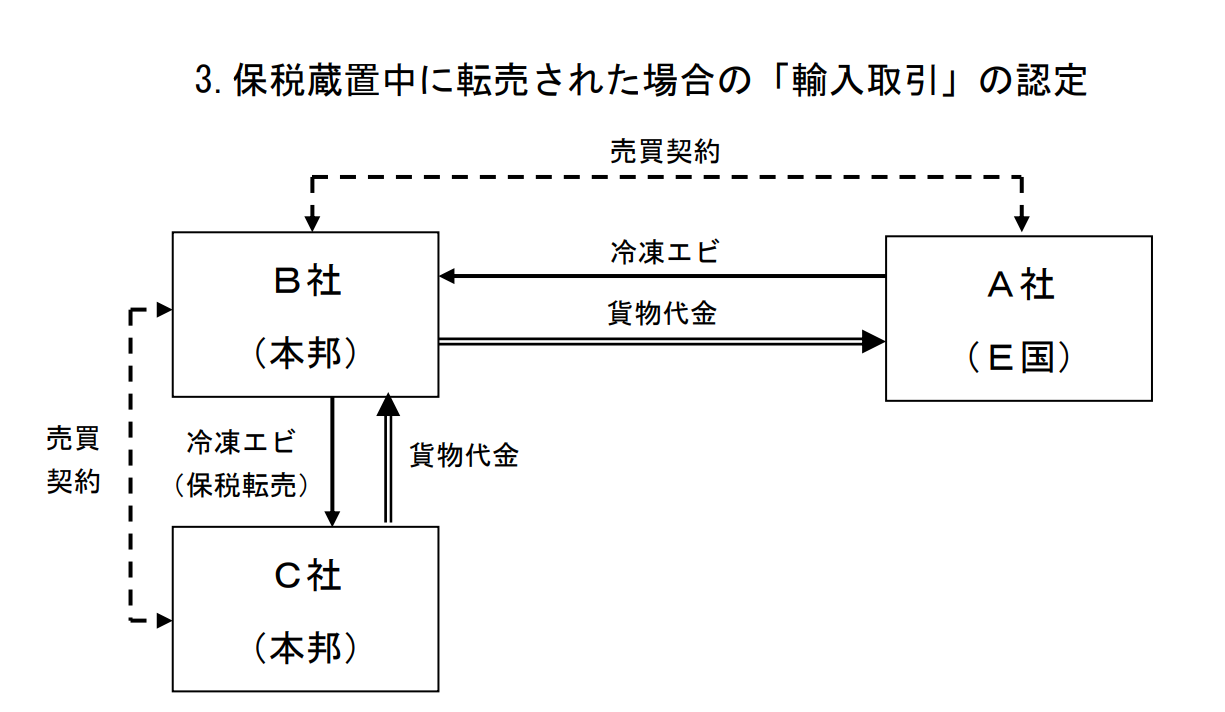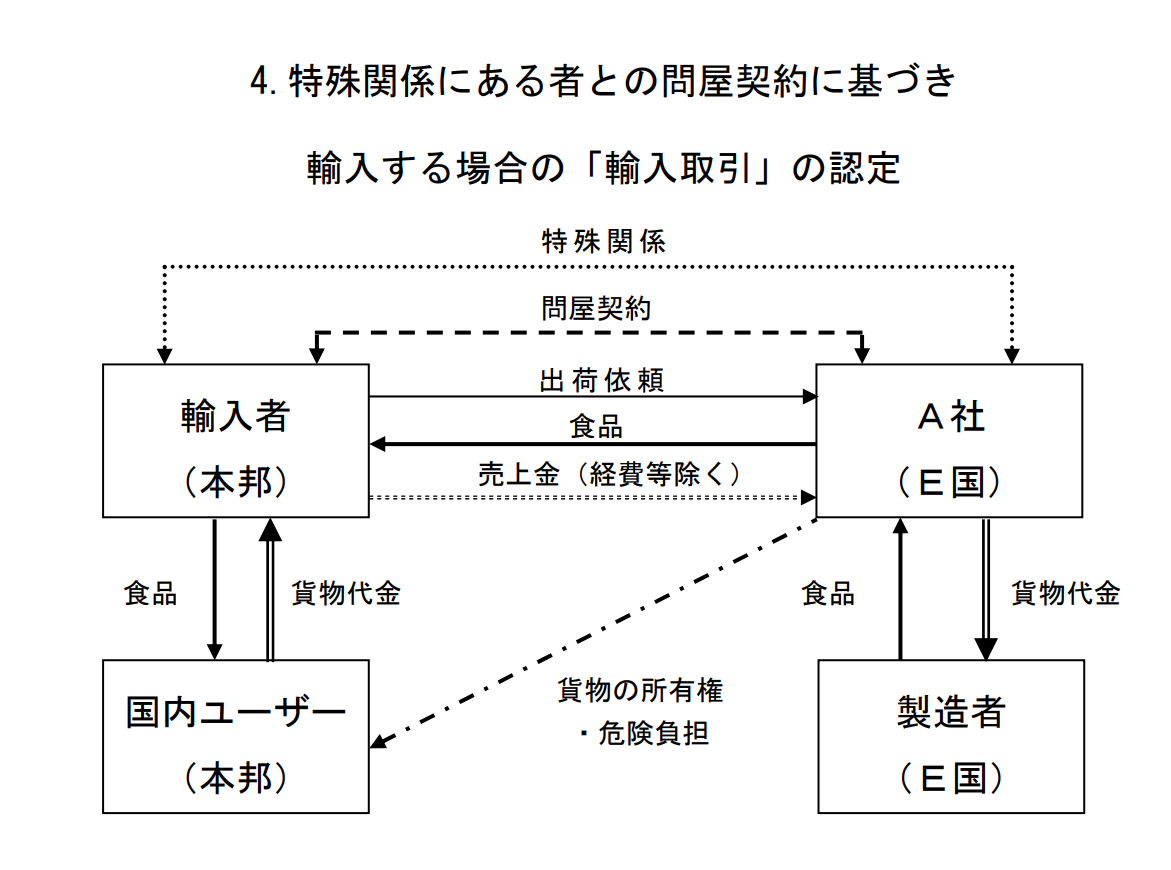日本版のHSコードから相手国に適用するHSへの変換ツールを作成しました。
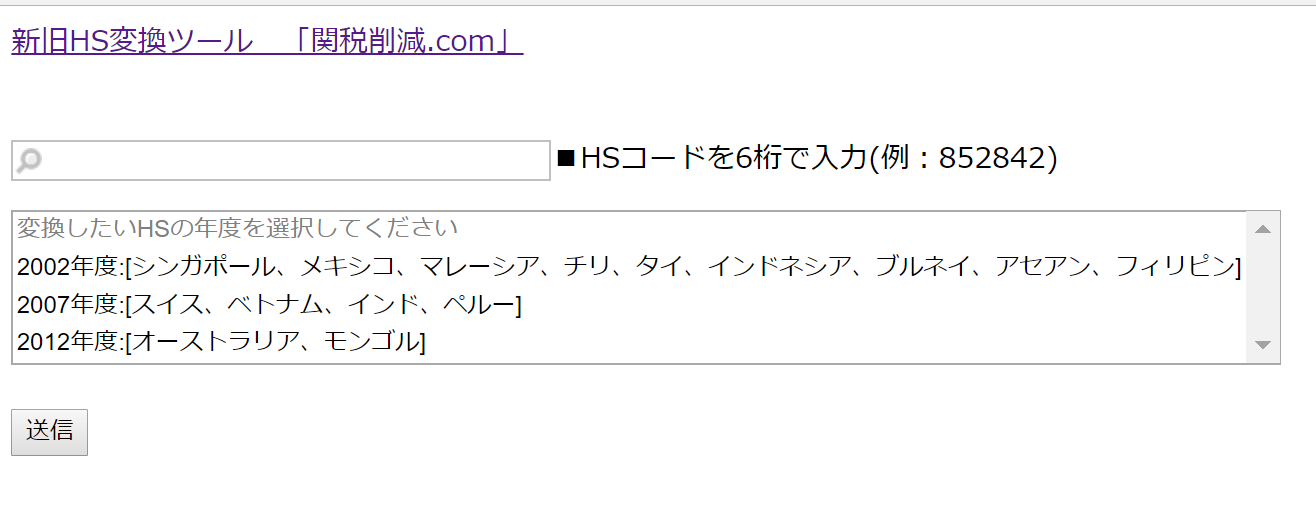
※プログラミング経験が浅いので見た目はよろしくないのですが
ちゃんと動きます。
原産地証明書に記載するHSコードは相手の国に合わせて6桁ベースで変更が
必要な場合があります。
例えば日本では2017年版のHSを使用するのに対し、
日ASEAN FTAでは2002年度版のHSを使用します。
2017年版のHSを知っていても過去のバージョンのHSがわからないというのは
FTA貿易実務担当者様にとって頭の痛い問題かと思います。
このような時に新旧HS変換ツールを使用して頂ければ、
現行2017年度版のHSと相手国の選択だけで過去のバージョンのHSを
検索する事ができます。
検索方法は虫眼鏡マークのある検索フォームに現行のHSを
6桁入力します(例:852842)
そして下の表にある変換したい年度、相手国を選択し送信ボタンを
押すだけです。
是非ご活用ください。